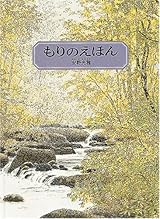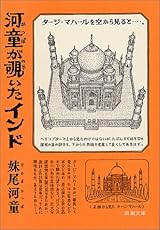その1「楽しませる悦びを知る」 (1/7)
――いちばん古い読書の記憶を教えてください。
高山:おそらく私は他の作家のみなさんと比べると、子どもの頃の読書経験というのがたくさんはなくて。でも親はわりと、私やふたりの妹に本を読ませたがっていたんじゃないかと思います。そんなに近いところに本屋さんがなくて、バイクで届けてくれる本屋さんが定期的に「こども文学全集」みたいなものを届けてくれていました。それを熟読したというより、読んでいはいた、くらいの記憶があります。自分で本を買って読むようになるのは10代中盤か、それ以降になります。漫画もそんなに読まない人間でしたし。それまでは図書館で読めるものをなんとなく読んでいましたね。青い鳥文庫みたいなものとか、冒険っぽいものとか、古典を子ども向けに分かりやすくしてあるものとか。
――プロフィールによれば、富山のご出身ですよね。
高山:あ、生まれたのは富山なんですが、わりとすぐに東京に越して、その後神奈川県の茅ケ崎にいきました。小学校に入る前です。富山は祖父母の家があって、夏休みに行ったり、妹が生まれる時に長期間滞在することもありました。祖父母の家は駅から5分とか10分の都会で、百貨店に大きな本屋さんも入っていて、そこにいくとすごく本を買ってもらえました。近くに本がなかったというのは茅ケ崎の時のことで、今は郊外型のショッピングモールがありますが、当時はスーパーも本屋さんも、そこまで近くにはなくて。図書館もバスを使わないと行けない距離でした。
――高山さんは後に美術大学に入るわけですが、小さい頃から絵を見たり描いたりするのは好きだったのですか。
高山:ああ、そうですね。安野光雅さんの『もりのえほん』というのがあって、あれは大人になってからもずっと見てました。自分で落書きもよくしていました。絵の教室にも通っていましたが、それはピアノ教室とかテニス教室とかいろんなことをやらされるなかのひとつで、そのなかでは一番続いていたかなというくらい。中学も高校も美術部ではなかったので、絵をしっかりやろうと思ったのは高校生の時、美大を受験をすることにしてからなんです。なのでそれまでは描くとしたら本当に、友達とマックに行くとトレイに敷かれた紙の裏側が真っ白だから、あれを裏返して友達4人くらいでボールペンで好き勝手描きながら喋る、とか。あとはノートに落書きして友達と交換しあうくらいでした。
――絵を描くのが得意だったり、まわりから褒められたりしたことは。
高山:見よう見まねでなんとなくできていたんですよ。絵を描くにしても文字を書くにしても。音楽とスポーツは全然できなかったんですけれど。で、やって褒められることは嬉しくてずっと続けていた、というのはあるかもしれないです。
――文字や文章も落書きで書いていたのですか。
高山:感じていることを書く時に、絵にするのと文字にするのとどっちが楽かな、という感じで、字が書きやすかったら字で書いていたし、絵で描きやすかったら絵で描くという感じでした。小さい頃はそんなに喋る子ではなくて、何か伝える時に口でうまく伝わらないことを絵で描くと分かってもらえたりしました。10代になると今よりもっと喋る子だったので、人と喋りながら字も書いて絵も描いて、みたいな感じでした。
――感想文や作文は得意でしたか。
高山:中学の時に1回だけ書いたものを「面白い」と言ってもらえた記憶があります。映画の「瀬戸内少年野球団」の感想だったかな。島の外から先生が来たり、島の外に行ってしまう女の子がいたりするので、島の内側と外側は違う世界になっている、みたいなことを書いたんです。現国の先生がとても思慮深い方で、褒める時も生徒の名前を出さず、「誰が書いたかは言わないけれど、この文章はとても良かったのでみんな読んでください」と言う人で。みんなは私が書いた文章だと知らないので、褒められた感覚は自分にしかなかったんですが嬉しかったです。今思えば、それが最初の呪いだったかもしれない。呪いはそのまま福音とも言い換えられるんですけれど。
――書くことの悦びを知ってしまったという呪いですか。
高山:そう、それと「ああ、面白いと言ってくれるんだ」という。映画自体が面白かったので、面白いことをどう面白いと思ったか書いて面白いと言ってもらったという、入れ子構造みたいですけれど、それが自分のなかで、「楽しんでもらえるんだ」という感覚になって。ふざけた絵を描いて友達に笑ってもらうのも嬉しいことなんですけれど、感想文を褒められた時はなにか、すごく強い光みたいなものがあって、その光に虫のようにふらふらーっと引き寄せられていく感じがありました。
――ところで、親御さんは本が好きだったのでしょうか。
高山:親は忙しかったこともあって、あまり本を読んでいなかったですね。でも、学生時代に読んだ本なのか、サリンジャーなどは家にあったんです。私もそれをちょっとは見たんですが、その時は反抗期だったのか「こういう気取った本はあんまり好きじゃない」という気持ちになって、そうした本ではなく、冒険小説や紀行文を手に取るようになりました。椎名誠さんの『アド・バード』とか、妹尾河童さんの『河童が覗いたインド』みたいなものとか。あとは船戸与一さん。そんなたくさん読んでいるわけではないんですが、『山猫の夏』とかを読みました。そういうものを読むようになったのは10代後半ですね。図書館とか学校の図書室とか、本を借りられるところで見つけたんだと思います。でも、まわりはお洒落な本を読む子が多かったんです。河出文庫の、あの、さらさらした表紙の文庫とか(笑)。
――ああ、昔の河出文庫って、カバーの紙がツルツルではなくてマットな感じでしたよね。
高山:そう。すごくお洒落な感じで、それこそ山田詠美さんの『蝶々の纏足』とか友人が貸してくれて。私もそういうのを読みつつ、冒険ものをチラチラと読んだりするような子だった気がします。