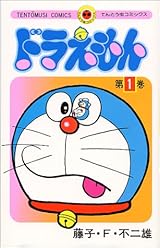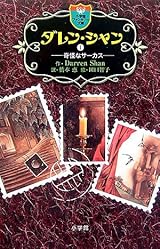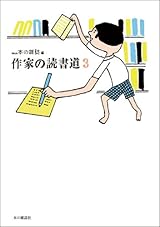その1「青い鳥文庫、星新一、海外ファンタジー」 (1/9)
――斜線堂さんは大変な読書家なので、愛読書のほんの一部しかうかがえないかと思いますが...。よろしくおつきあいください。いつもいちばん古い読書の記憶からおうかがいしています。
斜線堂:いちばん古い記憶は、こいでやすこ先生の『おなべ おなべ にえたかな』という、原っぱで草を詰んで最終的にタンポポのスープを作るというお話の絵本です。すごく好きで、夜になるとそれを読んでから眠って、幼稚園に行く時も持っていっていた記憶があります。なにがそんなに好きだったのか分からないんですけれど、最後にみんなでタンポポのスープを作る描写にすごく惹かれていました。
――周りに本がたくさんある環境だったのですか。
斜線堂:物心がついてから...幼稚園の年中さんくらいなんですけれど、身体が弱くてすぐ熱を出すようになってしまったので、私の病院通いが始まりまして。当然ながら病院はすごく苦手だったので、毎回断固拒否の姿勢でした。そうしたら「病院に行くたびに本屋さんで何か一冊本を買ってあげるよ」と条件を出されるようになって、そこから読書の習慣が始まったように思います。最初は『ドラえもん』を1冊ずつ買ってもらっていました。『名探偵コナン』もその病院ラインナップのひとつでした。でもそのうち親が漫画だとすぐ読み終えてしまうことに気づいてしまったんです。それで時間稼ぎのために文字の本を読ませようと思ったらしく、子供向けの文字の大きな星新一の本を買い与えてくれたんです。母親はあまり本を読まないんですが、母も星新一だけはずっと読んでいたようです。それが、私が自覚的に読書を始めた理由ですね。
――それまでは能動的な感じでもなかったのですか。
斜線堂:そうなんです。幼稚園の頃からふりがなが振ってあればなんでも読める子供だったので、漫画...それこそ集英社版の<世界の伝記>シリーズなども読んでいたんですが、勢いづいたのは星新一を読み始めた頃でした。こんなに面白いものがあるのかと思いましたね。SF要素があるところが『ドラえもん』の面白さと似ていて、そこからずっと星新一を買ってもらう時期に突入しました。
――学校の国語の授業は好きでしたか。
斜線堂:正直、最初の頃はあまり好きじゃなくて。教科書に載っている話はどれもこれも短すぎると思っていました。先に全部読んでしまっているから授業が退屈でした。
その頃から、私はとにかく落ち着きがない子供で、授業をちゃんと聞いていることができなくて。小学校2年生の時から脱走癖みたいなのが出ちゃったんですよね。教室から脱走してどこに行くかというと図書室で、それを繰り返して先生が手を焼いて、「もう、そこにいていい」みたいな感じになったんです。なのであんまり好きじゃない授業の時は図書室に行っていました。その時に読んでいたのは桜井信夫先生の『ほんとうにあったこわい話』という〈世界子どもノンフィクション〉のシリーズでした。親から「なんで授業から逃げるの」と訊かれて、「今は〈世界子どもノンフィクション〉を全部読まなきゃいけないから」みたいなことを言って怒られたりしたんですけれど。
『おまえが魔女だ』という、魔女狩りを取り上げた巻があって、それがものすごく好きで。ものすごく怖いんだけれど読んでしまっていました。
――今の斜線堂さんの源泉を感じます(笑)。
斜線堂:そうですね(笑)。〈世界子どもノンフィクション〉シリーズのなにがよかったかというと、載っていた話を休み時間に友達に話すと、すごく受けがよかったんですよ。「なんかさ、ファラオの呪いっていうのがあって、墓を暴いた探検隊が全員死んでるんだよ」などと話をすると、もう低学年の子供はそれだけで結構沸くんです。あの頃はみんな怖い話が大好きだったなと思います。
――語って聞かせるのが好きだったんですね。
斜線堂:そうですね。自分が考えた話でもないのに星新一のお話を語り直して人気を得る、というようなこともしていました。
――自分でお話を空想したり、文章を書いたりとかは。
斜線堂:小学校中学年の頃に、青い鳥文庫にもはまったんですね。ノンフィクションやショートショートとは違う長いお話があることを知り、面白いから自分でも書いてみたいと思いました。それで、自分が編集長という設定で友達を集めて、1冊の自由帳にみんなに小説を書いてもらって、雑誌を編集するようになるんです。月刊誌と週刊誌の2冊作って回し読みしていました。
――斜線堂さんはそこにどんな小説を書いていたのですか。
斜線堂:その時は青い鳥文庫のはやみねかおる先生の〈名探偵夢水清志郎事件ノート〉シリーズにはまっていたので、「自分は探偵ものを書くぞ!」という意志を強く持って女刑事二人が事件を解決するミステリーを連載していました。犯罪現場になった小屋をいったん燃やして新しい小屋を一晩で建ててそこで密室を作るといった、ありえないくらい自由な発想で書いていて、今考えると逆にそれ面白いなって思うんですけれど(笑)。その頃は、自分はめちゃめちゃ天才だと思って友達に読ませていたので、思い出すと「わー!(恥)」って気持ちになります。
――その頃にはもうミステリーには密室ものがあるとか、そういう認識があったのですね。
斜線堂:そうなんですよ。それこそ夢水清志郎のシリーズの『魔女の隠れ里』や『人形は笑わない』でそういう概念を学ぶなりすぐ自分でもやりたくなっていました。今なら密室を成立をさせる理屈をいろいろ考えちゃうんですけれど、その頃は「もうどうしても書きたいからこれでいきます」みたいな感じで書いていました。
高学年になるとすっかりパソコンが普及していて、当時の小学生は個人で作った掲示板に友達同士で書き込み合う文化だったので、みんな日常のこととかを掲示板上で報告し合うんですよ。あるいはイラストを載せたりとかね。そんな中私は友達の掲示板に延々と小説を書くという、今思うと半分荒らしだろうっていうことをしていました。自分と友達を主人公にしたファンタジーみたいなものを延々と綴ったあのログが残っていたら私は恥ずかしくて死ぬ...。さすがにもう残っていないと思うんですけれど。でも、友達と作っていた月刊誌とかは実家に残っていて、見つけると「わー!(恥)」ってなります。
――ファンタジーを書かれていたということは、読書でももなにかファンタジー作品に触れていたのですか。
斜線堂:ハリー・ポッター全盛期だったんです。小学1年生の時のクリスマスプレゼントがそれこそ『ハリー・ポッターと賢者の石』で、周りもみんなハリー・ポッターを読んでいました。そうしたら小3か小4の頃に『ダレン・シャン』が流行るんですよ。ハリー・ポッターの続刊を待っている子供たちが『ダレン・シャン』シリーズを読むようになって、ブームになっていました。『ハリー・ポッター』や『ダレン・シャン』は漫画に近い立ち位置だったというか。「今週の『ジャンプ』読んだ?」みたいな感じで「ここまで読んだ?」みたいな話をしていました。『ダレン・シャン』は人気がありすぎて図書室でも借りられないので、友達の1人が買ったとなるとそれをみんなで回し読みしていました。ファンタジーの名作を持っていると回し読みの輪に参加できるんです。ある子は『デルトラ・クエスト』、ある子は『ナルニア国ものがたり』みたいな感じで。『指輪物語』はさすがに分厚くてあまり人気がなくて、持っていても輪に入れていなかった。
やっぱり、私のクラスでは『ダレン・シャン』が一番人気でした。ちょっとグロテスクで怖い世界観だから、「いやーこれを読める自分達は大人だわー」みたいな風潮ができていました。小5の頃に同作者の『デモナータ』が発売されて、これが『ダレン・シャン』から更にグロテスクでハードな世界観で、あまりにショッキングなので読めない子も多くて。読める人はすごい!みたいな枠に入ってしまっていたんですよね。純粋に物語の筋が気になって読んではいましたが、自分の中でも周りに「あれ読んでるんだ...」と言われるのが嬉しかったり。そんな風にダレン・シャン(著者)の作品が本当に好きだったので、自分がファンタジーものを書く時は必ずヴァンパイアの要素を入れていました。ヴァンパイアについては『ダレン・シャン』の設定をそのまま流用していたのを覚えています。『ダレン・シャン』のヴァンパイアってかなり独特な設定なのに...。影響されやすいから『デモナータ』を読んだ後にチェスを勉強したりもしたなあ...。
――その頃はもう将来作家になりたいと思われていたのですか。
斜線堂:そうではなかったです。その頃はすごく目立ちたがりだったので、漫画家か政治家になろうと思っていました。当時は顔が広くて目立つ子が学級委員長になれる時代だったので、授業をさぼりまくる問題児だったくせに学級委員長をやり、結局生徒会長までやっていて、将来作家になろうというよりは、自分はこのまま目立って生きていくぞ、みたいな気持ちでした。今思うと本当になんなんだろうこの子供は、って人生をやり直したくなるくらい恥ずかしいんですけれど。
――内にこもるタイプではなく、わりと人前に出ていくタイプだったんですか。
斜線堂:そうなんですよね。もうとにかく落ち着きがなかったし。じっとしてられないから毎日面白いことを探してました。勉強が嫌いだったから、毎日が退屈で仕方がなくて。落ち着きのない私が唯一静かになる時間が、本を読んでいる時だったんだと思います。
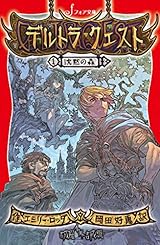
-
- 『デルトラ・クエスト (1) 沈黙の森 (フォア文庫)』
- エミリー・ロッダ,吉成曜,吉成鋼,岡田好惠
- 岩崎書店
-
- 商品を購入する
- Amazon