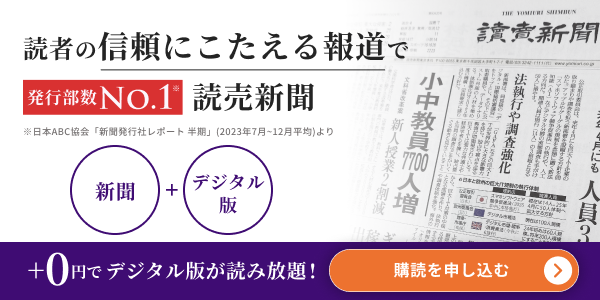大阪府警科捜研の「機械屋」が勇退、捜査機器の開発に没頭30年…「予断持たずに臨む」貫く
完了しました
物理学の視点から事件事故の証拠を調査する大阪府警科学捜査研究所の物理研究室から、今春1人のベテランが勇退する。小出健次総括研究員(59)。事故時の車のスピードや銃器の威力などを調べ、捜査する際に欠かせない機器やシステムの開発に30年以上携わった。「機械屋」を自称して地道な研究を続け、事件事故の解明を支えてきた。(鈴木彪将)

どれくらいの破壊力があったのか、どういった原理で衝突したのか――。事件事故を解明するため、物理学的な立証も重要なポイントになる。こうした疑問に答えるため、研究をしているのが物理研究室だ。
小出さんの大学時代の専門は農業機械。当時から農場で効率よく作業を進めるための機械を開発していた。
研究職に就くなど進路は様々考えられたが、ふるさとの大阪に貢献できる仕事を志して1987年に科捜研に。倒壊した建物の構造調査、事件で使用された爆弾のエネルギー測定……。携わった現場は多岐にわたり、捜査に役立つ機器をたくさん発明してきた。
そのうちの一つが、交通事故の車の速度を映像から鑑定するシステムだ。事故現場で行う再現実験で使用され、事故時と再現時のそれぞれの映像を使って正確な距離やスピードを算出する。初めて導入した約20年前は、ブレーキ痕など現場の痕跡に捜査の主眼が置かれており、画期的な開発だったという。「時間も忘れて研究に没頭していた」と笑顔で振り返る。
心がけているのは「予断を持たずに臨む」。これを強く意識する出来事があった。
2004年1月、藤井寺市で車がガードレールに激突して炎上し、運転していた男性と同乗の女性の遺体が見つかった。事前に別の車と接触する事故を起こしていたことから、当初は男性が当て逃げした後、焦って運転を誤ったことを事故原因とする見立てがあった。
だが、小出さんが燃え残った車体を鑑定すると、最初の接触事故でフットブレーキなどが故障していたことが判明した。後輪付近には、サイドブレーキを引いた時に生まれる痕跡が残されており、必死に引いていたことがうかがえた。
1
2