モスクワの赤い広場にひとつの霊廟があり、そのなかにレーニンの遺体が横たえられている。私は、このような公然たるロシヤ革命への侮辱、人民の新しき世代への侮辱、進歩する人間精神への侮辱、未来の無階級社会に対する侮辱が、ひとびとの批判もなしに数十年もつづけられてきたことのなかに、ピラミッド体制の驚くべき、恐るべき重さを知って、歯がみせざるを得ない。
「永久革命者の悲哀」 埴谷雄高
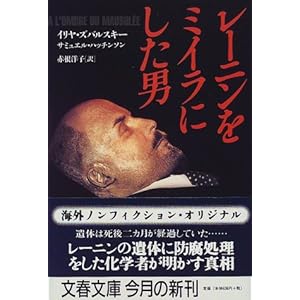 レーニンをミイラにした男……その政治的決定を下した人間でなく、そのものずばり遺体に防腐処置を下した男の話。いや、親子の話である。父の名はボリス・ズバルスキー、息子の名は著者イリヤ・ズバルスキー。共著者にサミュエル・ハッチソンとあり、おそらくは冒頭のレーニンの遺体処置をめぐるさまざまと、ソ連崩壊後についてのルポは彼によるものだろうか。まあ、いずれにせよ、レーニンの遺体に関わりを持った旧ソ連人科学者の回顧録である。おれにとってすれば、最近知ったいろいろの人物の名やエピソードなどが出てきておもしろかった。おれはiPS細胞と言われてもAppleかSONYかどちらの工作員かもわからぬが、こんな本を読んでいる。
レーニンをミイラにした男……その政治的決定を下した人間でなく、そのものずばり遺体に防腐処置を下した男の話。いや、親子の話である。父の名はボリス・ズバルスキー、息子の名は著者イリヤ・ズバルスキー。共著者にサミュエル・ハッチソンとあり、おそらくは冒頭のレーニンの遺体処置をめぐるさまざまと、ソ連崩壊後についてのルポは彼によるものだろうか。まあ、いずれにせよ、レーニンの遺体に関わりを持った旧ソ連人科学者の回顧録である。おれにとってすれば、最近知ったいろいろの人物の名やエピソードなどが出てきておもしろかった。おれはiPS細胞と言われてもAppleかSONYかどちらの工作員かもわからぬが、こんな本を読んでいる。
で、レーニンをミイラに……って、この遺体保存方法をミイラと呼ぶのかどうかわからんが、まあそうしようと言い出したのは同志スターリン。レーニン余命いくばくもないころ。これに対して痛烈に批判したのがトロツキー。ブハーリンとカーメネフもこれに同調する。しかし、結局のところスターリンが勝利をおさめる。そして、レーニンの死後、実際にプロジェクトを指揮したのが「革命の剣」フェリックス・ジェルジンスキーだった。そこで、ボリス・ズバルスキーにもお呼びがかかると。
ボリス・ズバルスキー
ズバルスキーはユダヤ人であり、二つの大学で理学士の学位を得ていたにもかかわらず、それが理由で大学や研究所で一流のキャリアを積む機会にめぐまれなかった。そしてまた、ユダヤ人に対するポグロムに怒りを燃やす若者でもあった。ゆえに、若き帝政ロシアの時代には社会革命党の活動にも参加していた。一家はわりと裕福であったにもかかわらず。
当時のロシアは貧富の差が他のどのヨーロッパ諸国より大きい国だった。ゲルシューニという男から、革命家の国外脱出や反体制新聞・書籍の密輸の手助けをしてくれないかと持ちかけられると、当時まだ高校生だった父は喜び勇んで引き受けた。
「ゲルシューニという男」って、ゲルシュニといえばサヴィンコフが『テロリスト群像』で「ゲルシュニからの手紙」で一章割くくらいの党指導者、大物じゃねえか。で、国外脱出を助けた中にこんな人物もいたという。
後年父から聞いた話によれば、父が国外脱出を助けた革命家の中にはあのトロツキーもいたという。夜陰に紛れてトロツキーを国境の手前数キロのところにある小屋まで案内した。二人ともそのまま小屋で眠ってしまい、翌朝、国境までトロツキーを送り届ける男に叩き起こされた、という話だった。
が、後年、著者が学会のためパリを訪れたところ、フランス人哲学者から図書館にトロツキーの自伝があると聞き読んでみたら、父の話とずいぶん違う内容だが、たしかに若き日の父が出てきたという。
……と、ここで同時に読んでいたレフ・トロツキーの自伝を持ちだしてみよう。「最初の脱出」の章だ。ちなみに、このはじめての脱獄でたまたま手に入れた旅券にあったのが「トロツキー」という名だった。一生涯それ自分の名前として通用するようになるとは想像もしなかった、と書いてある。まあいい、若きズバルスキー登場のシーンだ。
国境の非合法手段による通過は、ある高校生(ギムナシスト)の指導下に行われた。彼は現在高名な化学者となり、ソヴィエト共和国の学術機関の一つの会長におさまっている。
この男は社会革命党に共感を寄せていたようである。私が「イスクラ」の組織に属していることを知ると、急におどかすような非難の調子をこめて、
―きみは「イスクラ」の最近号に、テロリズム反対の卑劣な議論がのっているのを知っているのかね? というのであった。
そこで私が政治的原則について論じようとすると、高校生は辛辣な調子で、
―きみなんか、国境は通してやらないよ! ……という。
ちなみにこれ、澁澤龍彦訳。フランス語訳経由のもので……って、いまは関係なからいいや。
で、この高校生はある商社の外交員の起居している空き部屋を案内し、朝まで帰ってこないからそこにいろという。で、トロツキーが窓から入って寝ていると……。
まだ夜なのに、急に明るくなって、私は目をさました。見知らぬ男が私をのぞきこんでいる。山高帽をかぶり、片手に燭台、片手に棒をもった小男である。天上に映った大きな帽子の影が、私の方に近づいてくる。
―君は誰だ? 私は怒っていった。
―おかしな話だね、と見知らぬ男は悲劇的な調子で答えた。―おれのベッドに寝ているやつが、きみは誰だ、とおれに訊くんだからな!
で、このピンチは部屋の主が勝手に悪ふざけの好きな友人のせいだな! と早合点して難を逃れるわけだが。
……って、「レーニンをミイラにした男」の話だったか。そんでまあ、ズバルスキー父さんは結婚したり、大富豪モロゾフに雇われて化学工場と森林を任されたり、そこに呼んだボリス・パステルナークに奥さんを寝取られたりして、その後1917年の革命のさいに社会革命党の代議士になるんだけど、革命への熱はさめ、モスクワに戻ったら生活が困窮したけど、急にかつての恩師から国立生化学研究所の副所長に取り立てられて一気に大邸宅住まいになったりと。それで、ネップのおかげもあって、海外旅行なんかの豪奢な暮らしを楽しんだとさ。
で、当然、権力中枢にも食い込んでいこうとする。その中の一人がジェルジンスキー、そしてその後継者のゲンリフ・ヤーゴダ(……薬剤師出身=暗殺とかできると思っていたが、いまWikipedia先生見たらその経歴が書き換えられてて、でもなんか英語の出典がついてるから、新発見でもあったのかしらん)とも良好な関係をもった。このあたり、完全に秘密警察長官たちであって、ある意味ハラハラもんである。でもまあ、ともかく、ジェルジンスキーに取り上げられたお陰でレーニン遺体保存のかかわるようになって「指導者階級(ノーメンクラツーラ)」になれた、と。
粛清時代
息子も党幹部の通う学校に行って、ルイコフの娘、ジェルジンスキーの息子、スターリンの息子ヴァシリー(ワシーリー)もいた。ヴァシリーは先生にさされると、机を叩いて「ぼくはスターリンだぞ!」と叫んだらしい。しょうもない後半生を想像させる。別荘なんかで親しくしていたのはルイコフ、ブハーリンの一家であって、とくにブハーリンは博識で子供である筆者になんでも教えてくれたという。彼らは夕食の時など、ざっくばらんにスターリン批判ををしていたという。なんという死亡フラグ。
……と、話を飛ばして1934年、セルゲイ・キーロフが暗殺される。このニュースが報じられたことが、著者の感覚だと、こっから大粛清時代に入ったというきっかけに思われたようだ。この頃、著者は父の仕事を手伝い、レーニン廟の科学者チームにいたが、そこもNKVDの管轄下にあったという。
以後、いくつか粛清エピソード。
1937年のある日、仕事から戻った私は管理人から、政治局員グリゴーリー・オルジョニキーゼが自殺したと聞かされた。新聞もラジオも、彼の死因を心臓発作と報じた。しかし、検死にあたった法医学者は、絶対に口外しないという条件付きで七年後に教えてくれたところによれば、オルジョニキーゼの頭には弾丸が貫通した痕があったという。
グリゴーリー・オルジョニキーゼ、あるいはセルゴ・オルジョニキーゼ。『ベリヤ』の主要人物のひとりといってもいい、「セルゴおじ」。スターリン、ミコヤンとともにザカフカース派を形成したオールド・ボルシェヴィーク。ベリヤの庇護者にして邪魔者……。って、ベリヤの話になってもしゃあないが。『ベリヤ』によると確かに公式発表は心臓麻痺。ただ、その動向はスターリンの私設秘書アレクサンドル・ポスクレブィシェフ(ポスクリョーヴィシェフ? だいたいこいつに呼び出されると死ぬ)に呼び出されたところで描写が終わっている。
大粛清時代はこんな感じだったらしい。
恐怖はとうとう私たちにも迫ってきた。私たちが住んでいたアパートには36家族が暮らしていたが、そのうち34軒がNKVDによって封印されてしまった。
この中には赤軍の至宝、ミハイル・ニコラエヴィチ・トハチェフスキーなんかもいたという。つーか、モスクワも広いんだか狭いんだか。
で、著者も父の入院中、エジョフからいきなり呼び出しをくらう。
広い部屋に、大きな机を前にして、探るような目をした小男が座っていた。書記長に対する無限の忠誠心の証として、かれの背後の壁にはスターリンの巨大な壁画が飾られていた。
エジョフは私たちに椅子をすすめると、自分は立ち上がって、155センチの背の高さから私たちをじろじろと見下ろした。想像していたよりもっと小男だ、と思った。
だからコンプレックス持ったチビに権力を(……以下略)。この件は、「もしズバルスキー父が亡くなったらレーニンの遺体保存に支障があるか?」という確認で終わった。
でもって、著者はヤーゴダやルイコフ、ブハーリンの裁判も目の当たりにし、裁判記録と実際に行われていたものはぜんぜん違うぜって言っておきたかった云々。要するに「見世物裁判」というやつ。これを見た最後の生き残りだと著者はいうけれども、そうだとしたらとても貴重だ。
また、エジョフ粛清後、ベリヤ時代の話。
今回の大規模な反ユダヤキャンペーンの引き金となったのは、1948年のサロモン・ミホエルスの死だった。モスクワ・ユダヤ劇場の著名な演出家だったミホエルスは、ミンスクでトラックに轢かれて死んだ。少なくとも公式にはそういうことになっており、新聞にもそう発表された。頭と脚にひどい損傷を受けた遺体はレーニン廟付付属研究所に運ばれ、父とマルダシェフの手で葬儀のための修復処置が施された。詳しく調べてみたところミホエルスの遺体には銃弾による傷が認められたため、彼らはミホエルスの死は交通事故によるものではないと直感した。
しかしまあ、このスターリンのというか、ソ連のというか、ロシアのというか、反ユダヤ主義というのはなんだろうね。スターリン死後は変わったのかね。ようわからん。
でもまあなんだ、のちに「医師団陰謀事件」とかもあるわけだけど、権力者間で暗殺が横行したり、不可解な粛清が横行する中で、これを場合によっては治療し、検死する医師というものの立場。スターリンの検死に関わった医師たちがどうなったか、など。知りすぎた男、になってしまう。かといって、権力階層に取り入れられなければ、同志ラヴレンチー・パーヴロヴィッチとかにいきなり呼び出されて、「シベリアの収容所に行って収容者の健康改善してこい」とか言われる(もちろん人道的見地からではなく、労働力、生産性の問題として同志は収容所をつねに改善させようとしていたのだ)。
で、ついにユダヤ人でもある父も逮捕される。秘密警察はとうぜんエスエルだった過去も、ルイコフ、ブハーリン、ヤーゴダと親しくしていたことも調べあげ済みだ。ミホエルスの遺体修復も咎だ(トロツキーを助けたのまで調べられてたらアウトっぽいな)。で、二年近く拘置所にいて、スターリン死んだりして粛清は免れたけど、身体を悪くしてすぐ死んだ。
そんで、こういう状況下では家族も当然巻き添えになる。息子も職を解かれ失業。政治状況が緩和されていくまでは食えない時代が続く。友人の救いでポストを得る。まあ、死ななくてよかったね、と。
ルイセンコの話は……まあいいか、おしまい
ほんでまあ、もうぜんぜんレーニンの遺体保存についての方法だとか、エピソードについては紹介する気もない(独ソ戦はじまって真っ先に疎開させたのがレーニンの遺体で、むしろモスクワより奥地のほうがゆっくりじっくり保全作業ができて、状態がよくなって帰ってきたらしいってのはおもしろかった。しかし、そんな話じゃリトヴァクも救われまい)。そこらへんは今さら買って読んでください。そんで、興味深かったのは「科学の世界も一党独裁」の章で、最近ネットでちらちら耳にするルイセンコがソ連科学アカデミーを仕切ってた時代のエピソードで、ルイセンコの成功に触発された、荒唐無稽な「発見」を発表する「革新者」たちが雨後の竹の子のように現れたとか。そんで、著者もそんな「革新者」の陸軍将校の訪問を受け、彼はガンの特効薬を発見したと言ったが、聞いてみるとそれはウランだった。著者は「ウランはあぶねーよ」って追い返したんだけど、紹介者である同僚に「君は金の卵を逃したんだぞ!」って怒られて、なんでかっていうと、そういう政治方針で、「革新者」にバンバン予算が出てたんだって。真摯なソ連の論文に対する西側からの問い合わせには一切答えない反面で。まあなんつーのか、自由な科学と、科学の自由とか、そんなんちょっと思ったりしたのだった。
おしまい。

- 作者: イリヤズバルスキー,サミュエルハッチンソン,Ilya Zbarski,Samuel Hutchinson,赤根洋子
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2000/03/01
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 4回
- この商品を含むブログ (9件) を見る