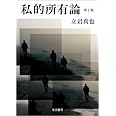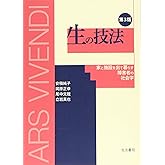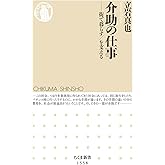戦後日本の最新医療で何が起こったのか知るために最良の書。
今でこそ精神医療は花形になっているが、50年前にはまだ医療として成り立っていないような状況だった。
そのような中で、患者の尊厳をめぐって壮絶な戦いが繰り広げられていた。
さまざま本からの丁寧な引用によって読まれた本であるが、情報が多すぎて著者の意図が見えなくなるところもあったが、資料としてこれだけまとまっているのは圧巻である。
この注文でお急ぎ便、お届け日時指定便を無料体験
Amazonプライム無料体験について
Amazonプライム無料体験について
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥460 - ¥500* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

造反有理 精神医療現代史へ 単行本 – 2013/11/21
立岩真也
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥3,080","priceAmount":3080.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"3,080","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"3uZtRGOFKApnBmwDKJ2B2GcLRNnFACtHNGeQK4mmnvsfR1RtkVnr4hZSrRQdEtnqPwHCNIgAymIuC2d27P70doymrT5FF%2BHUkMpATkGXqoqAMHl442eBBicqHg%2FimNqpQC7sLfcgzC8%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}]}
購入オプションとあわせ買い
精神障害者に現代社会はどう向き合ってきたのか――。
1960年代に、精神医学批判の運動があった。当時の学生運動の主張=大学解体とも関わりつつ、患者を社会に適応させようとする従来の医療のあり方に鋭い批判と糾弾を浴びせた。
「造反派」と名指しされたその動向と、彼らに批判された側、両者の実態を膨大な文献から掘り起し、肉薄する。
開放病棟、薬物療法や生活療法への問い、ロボトミー手術への批判などを具体的に検証し、
鎌田實、中井久夫、神田橋條治らの錚々たる医療者たちの若き日の模索と成果と挫折とはいかなるものだったのか考察する。
本書は、日本における精神医療批判史として、また今日の障害者のケア論につながるまさに注目作であり、著者の到達点である。
1960年代に、精神医学批判の運動があった。当時の学生運動の主張=大学解体とも関わりつつ、患者を社会に適応させようとする従来の医療のあり方に鋭い批判と糾弾を浴びせた。
「造反派」と名指しされたその動向と、彼らに批判された側、両者の実態を膨大な文献から掘り起し、肉薄する。
開放病棟、薬物療法や生活療法への問い、ロボトミー手術への批判などを具体的に検証し、
鎌田實、中井久夫、神田橋條治らの錚々たる医療者たちの若き日の模索と成果と挫折とはいかなるものだったのか考察する。
本書は、日本における精神医療批判史として、また今日の障害者のケア論につながるまさに注目作であり、著者の到達点である。
- 本の長さ434ページ
- 言語日本語
- 出版社青土社
- 発売日2013/11/21
- 寸法14.3 x 2.8 x 19.8 cm
- ISBN-104791767446
- ISBN-13978-4791767441
よく一緒に購入されている商品

対象商品: 造反有理 精神医療現代史へ
¥3,080¥3,080
最短で2月15日 土曜日のお届け予定です
残り5点(入荷予定あり)
¥1,980¥1,980
最短で2月15日 土曜日のお届け予定です
残り10点(入荷予定あり)
総額: $00$00
当社の価格を見るには、これら商品をカートに追加してください。
ポイントの合計:
pt
もう一度お試しください
追加されました
spCSRF_Treatment
3をすべてカートに追加する
一緒に購入する商品を選択してください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 出版社 : 青土社 (2013/11/21)
- 発売日 : 2013/11/21
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 434ページ
- ISBN-10 : 4791767446
- ISBN-13 : 978-4791767441
- 寸法 : 14.3 x 2.8 x 19.8 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 321,645位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 68,375位ノンフィクション (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

たていわ・しんや 専攻:社会学 1960年佐渡島生、新潟県立両津高校卒、東京大学文学部社会学科卒、同大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。この辺り、河合塾で働く。1990年~日本学術振興会特別研究員も。1993年~千葉大学部文学部、1995年~信州大学医療技術短期大学部を経て、2002年~立命館大学。現在同大学大学院先端総合学術研究科教授。同大学生存学研究センター、その雑誌『生存学』(生活書院刊)、『Ars Vivendi Journal』(オンラインジャーナル)、ウェブサイト『arsvi.com』(→「生存学」で検索)に関わる。最初の共著書が『生の技法』(1990、藤原書店)→2012:第3版を文庫版で生活書院より。最初の単著が『私的所有論』(1997、勁草書房)→2013:第2版を文庫版で生活書院より。電子書籍の自販も試行中→http://www.arsvi.com/ts/sale.htm
カスタマーレビュー
星5つ中4つ
5つのうち4つ
8グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
- 2014年5月17日に日本でレビュー済み『私的所有論』で社会学者として一生分の仕事をしてしまった感のある立岩先生ですが、
そこで完成した理念を実際的なところに応用してるのが、近年の医療倫理に関する著作群です。
『造反有理 精神医療現代史へ』は全共闘世代の「反精神医学」のラベルをはがして、成分として捉えなおす本と読みましたが、
精神医療という場で、これまで言われた色々なことが引用されており、胸を打たれるもの、胸クソ悪くなるものなど、さまざまです。
泰然とした論理展開で造反有利(同時にダメな部分もあったこと)を証明してゆきます。
このあたり今さら蒸し返しても、現状なしくずしのDSM−5に押し流されるだけなのが遺憾ですが、
病院という名の収容所のロビーなど、ケアの現場に一冊でも置いてあれば、医者を信用したくなります。
あと、文章が読みづらいとか言う向きがありますが、平明な書き方しかしてません。読み手が頭固いだけだと思うんだがどうなんだろう。
- 2013年12月29日に日本でレビュー済み今まで一方の側から語られてきた精神病理学を造反側と言われた側から問い直し、敢え
て今ここで「造反有理」と言い切る。間違いなく力作であると同時にチャレンジングな
一冊である。
精神医療に関心のある人ばかりではなく、最近のナショナリズムの動向、アールブリュッ
トに関心のある人は必読の本。それは、精神医療における精神科医の行動の歴史(ロボト
ミーから薬物療法へ)が決して一直線ではない道程(ある医者からは造反と呼ばれる)、
精神を’’直す’’医者たちの苦闘の精神史を語る、稀有な著作だからだ。
精神障害とは何か。それは機能障害とは違う、社会の側の問題としてある。そこでは本人
への医療的介入が問題となる。しかし、いったい精神障害のどこからが介入できるケース
なのだろうか。もしかしたら間違っているのは(精神障害を受け入れない体制、社会が)
おかしいのであり、彼ら精神障害者が人間の根源的な生を生きているとは言えないだろう
か。病が私達を逆照射する。この構図はアールブリュットでも同じである。それでも鬱病
で自殺したいと言う人に「自殺しなさい」とは言えないだろう。ここに医療の難しさがあ
る。その難しさをどう医者は考え生きてきたのかを実証的に文献を追って紹介している。
立岩さんの文章は相変わらず平易であるが、読みやすいとはいえない。それは、敢えて難
解にしているというわけでもない。じぶんの思考と記述の正確さに対して、真摯なだけで
ある。その生真面目さが、時に笑いを誘うような箇所もあり、小島信夫さんの小説を読む
ような読者であるなら、その文章の面白さは理解していただけるであろうか。もちろん著
者は意図的にこのような文体を採用しているのであり、たんに文章がへたなわけではない
ことは当たり前である。普通に書いたらこぼれ落ちることがあるので、このような文体な
のだ。逆に言えば、このようなvoiceを持った文体を書ける社会学者がもっと出てきてほ
しいものだ。
ただ小島さん的な書き方の弊害といおうか、生前小島さんは書いたことを見返したりしな
かったのと同じで(同じか?)、立岩さんも同じく推敲ができていない。誤植がたくさん
ある。ただ改訂が出れば、こういう簡単な文章の間違いはなくなる、という意味では、内
容は問題ない。
個人的には発達障害支援センターなどの職員の方が行っているSST(ソーシャル・スキ
ル・トレーニング)の前史である精神障害者の「生活療法」における問題点などは、基本
的に勉強していてほしい。介入というのは、それほど簡単なものではないのだから。
- 2020年12月30日に日本でレビュー済み非常に読みづらかった
著者は中立的であろうとする為なのか、両論併記ばかり 政治家の文章のようでした
この分野の研究者向けなのでしょう 註もしっかりついてますし 資料本みたいなものですね
購入検討の方は一度立ち読みすることをオススメしますね、、
まさに文系研究ってニオイを嗅ぎ取れる筈です
- 2017年7月21日に日本でレビュー済み評者はかねがね、精神科医が家族の蒙る暴力の問題に無関心なのは、患者家族をバカにしているからではないか、という疑いを抱いていたものです。この疑いは、半世紀近く前、東大医学部を中心に青医連なる反精神医学をかかげた、本書でいう造反有理集団の一員らしき医師が、ある雑誌に書いていた記事を読んでいて萌したのでした。それはまさに患者家族をバカにしきった文章だったのです。
といっても、半世紀近く前の記事なので引用するわけに行かないのが残念と思っていたら、本書を読んでいて、まさに絵にかいたような患者家族蔑視の文章が出ていたので引用します。
‥‥「問題は誰がなおしたいかということです。身体病の場合は主として本人がなおしたいのであり、精神病の場合は主として社会がなおしたいのです。」(吉田)という、患者当事者の言葉を引いて、次のように述べているのです。
「‥‥当たっている。社会と言っても小さな社会もある。家族に発病した人がいて、当惑する。ときにははっきり迷惑であり、疲労困憊してしまう。困るのは近所の人でもあるかもしれない。つきあい、扱いに困ってしまう。自らの身が危ないように感じられること、実際危ないこともある。それで精神病院で面倒を見てもらうことにする。‥‥」(p.300)。
評者はあっけにとられてしまったものです。「家族に発病した人がいて当惑する」だって?なにノーテンキなことを言っているんだろ。評者の知る限り、わが子が統合失調症の診断を受けると母親は一晩中泣き明かします。そう、「家族に発病した人がいて、頭が真っ白になり、嘆き悲しむ」のです。こんなことも分からないほどに、この、東大大学院卒でブランド大学の社会学教授さんは、人間性を失ってしまっているのでしょうか。その点、最近読んだ『精神障がい者の家族への暴力というSOS』(蔭山正子著、明石書店)では、保健師を長らく勤めていた著者によって、次のように正確にしかも暖かいまなざしで述べられています。
「子どもが精神疾患に罹患した親が、その衝撃から心的外傷後ストレス障害を引き起こす可能性があることも指摘されているように、家族が精神疾患を患うこと自体が、大きな衝撃となる。また、専門家とのコミュニケーションは必ずしも満足いくものではないことも実態であり、家族には怒りや無力感、自責の念など様々な感情が生じる。愛する家族が精神疾患であるという事実に直面することの衝撃や落胆も大きい。それまでの家族像を失う、喪失体験でもあるだろう。精神障がい者に対する社会的な偏見、そして患者自身(本人)やその家族の持つ内なる偏見が、より孤立した状況を強めてしまうことも少なくない。このような状況の中で、多くの家族が本人と同居し、疲弊しながらも療養生活を支え続けている、というのが日本の現状である」(p.39)。
まさに、東大病院の精神科医や東大出身の社会学者と言ったエリートたちの、患者家族に対する偏見差別のまなざしにこそ精神障がい者差別の根源があることを確認できた、本書は反面教師です。
といって、このような偏見差別が、精神病の家族原因論がとっくにすたれた今になっても残っているのも、家族当事者からの声が少なすぎるということがあるのでしょう。もちろん、蔭山氏の著書が家族会の協力の下に書かれたことに見るように、家族会の活動はあります。精神分裂病の名称を統合失調症に変えさせたのは、その最大の成果と言えます。けれども、とかくロビー活動に偏して与党代議士と仲良くなったりして、本書の中でも揶揄の対象になっているように、ジミンガージミンガー攻撃のターゲットになりやすい。必要なことは、家族当事者としての研究の積み重ねです。親にはそんな余裕がないので、可能性があるとしたら兄弟姉妹です。評者の知っている範囲では、精神障がい者兄弟姉妹には、PSWを目指す人が割といて、その中から家族当事者研究が出てくることが期待されるのですが、現実はそう甘くない。研究は顕名でしかできないから、自分自身の家族に及ぼす影響を考えなければならない。それでも知的障がい者の兄弟姉妹当事者研究は始まっていますが、研究成果を出版しても当人に読まれる気遣いがないからできることでしょう。
でも、こんな言い訳ばかり言っていても進展しないので、誰かがやらなければならない。一つの方法は、インターネット上の兄弟姉妹のサイトをテクスト・データとすることです。「人生めちゃくちゃにされたー」といった血を吐くような叫びなど、深刻な事例もあります。冒頭に引用した著者のノーテンキな発言も、親、特に母親にはまったく当てはまらないが、兄弟姉妹になら当てはまるところもあります。所詮、兄弟は他人の始まりですから。だから、この著者に個人的な恨みがあるわけでもないこともあるし、自戒の意を込めて、星を一つおまけしておきました。長文失礼しました。