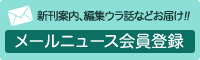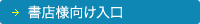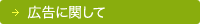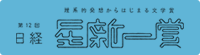1996年に当時のクリントン米大統領が「火星からの隕石に生物の化石と思われるものが含まれていた」と発表したことを覚えている人も多いだろう。これに先立って,地球の地層からも似たような化石が報告されていた。とはいえ,多くの科学者は懐疑的だった。これらの化石は生命体としては小さすぎるのだ。通常のバクテリアの1/5~1/100という小ささで,ナノスケールのサイズだ。
1998年になって,フィンランドのチームが生きたナノバクテリアを発見したと発表。さらに,人体からも見つかったと続けざまに報告した。骨や歯の材料となるハイドロキシアパタイトの殻をかぶったナノバクテリアは,腎臓結石など,さまざまな病気を引き起こす病原体として喧伝された。依然として懐疑的な研究者が多かったが,ハイドロキシアパタイトを主成分とするナノバクテリアからはタンパク質やDNA,RNAも検出されたことから,ナノバクテリアを検出する診断試薬なども販売されるようになった。
しかし,著者たちの研究からナノバクテリアは,生物ではなく,ハイドロキシアパタイトが周囲の生体分子(タンパク質やDNAなど)を取り込みながら結晶成長したものだということがわかってきた。こうしたナノ粒子は互いに融合しながら成長するが,その姿が分裂中の細菌に見えたのだ。
ナノバクテリアは生物ではなく,もちろん病原体でもなかったが,健康にはかかわっていた。体内のカルシウム代謝に大いに関係していたのだ。
著者
楊定一(John D. Young) / Jan Martel
楊は台湾の長庚大学(CGU)および明志科技大学の教授で,CGUナノ物質研究所所長。無機物と有機物の相互作用と,それらがどう健康に影響するかに関心を持ち,研究を進めている。ロックフェラー大学分子免疫学・細胞生物学研究所長を務めたことがあり,現在も特任教授として籍を置いている。マーテルは長庚大学・生物医学科学研究所の博士課程に在籍中。カナダ・ケベック州シェルブルックの出身で,血液が媒介する病原体や伝統療法を研究するために,楊のチームに加わった。
原題名
The Rise and Fall of Nanobacteria(SCIENTIFIC AMERICAN January 2010)
サイト内の関連記事を読む
ALH84001/ナノバクテリア/ナノ粒子/ハイドロキシアパタイト/最小の生物/火星の生物化石
キーワードをGoogleで検索する
ナノバクテリア/ALH84001/火星の生物化石/ナノ粒子/最小の生物/ハイドロキシアパタイト