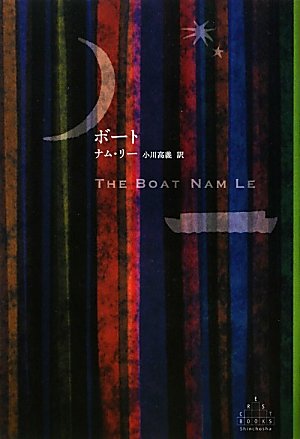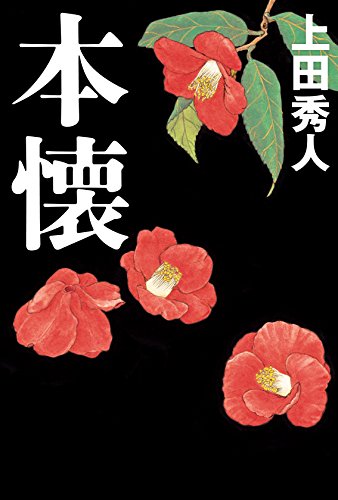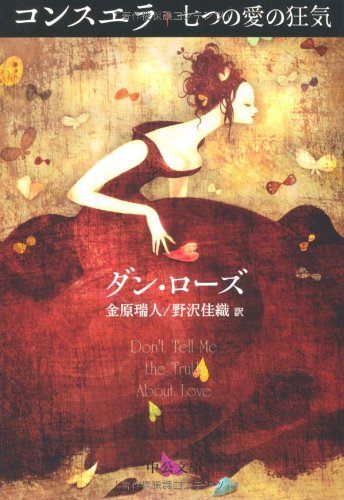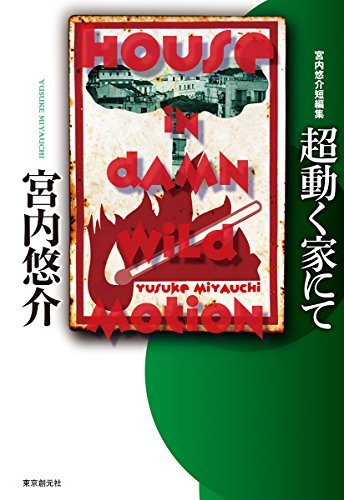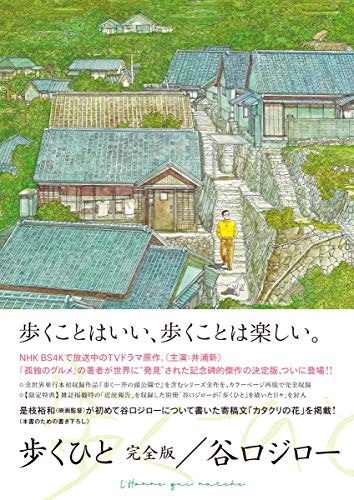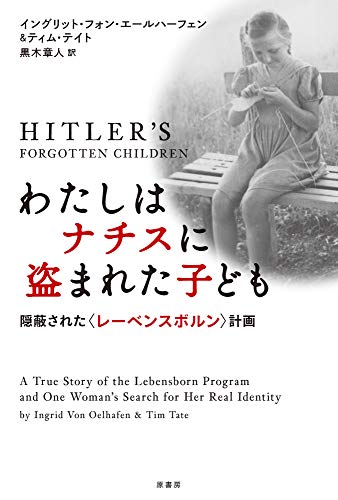書評
『小説家の開高さん』(フライの雑誌社)
ほろ苦い余韻残す男たちの短編
土方のマサ。ヒッピーのエンディ。大工のウィリー。オカマの次郎さん。熊撃ちの征三さん……武骨で、不器用で、率直で、酒飲みで、恋に一途で、ちょっとだめで、つまりいろっぽいのです、みんな。そんな男たちとの交差を描く物語が十編。ぼくとマサは脚割り場という、蟹(かに)工船でもっとも過酷で花形といわれる甲板の作業場につかされた。(「土方のマサ」)
一九七〇年、二十歳。「ぼく」の旅のはじまりは蟹工船だった。下船して世界各地を放浪、ニュージーランドで四年間鱒(ます)釣り。旅遍歴が紡ぐ物語には時代の空気、男や女の体温や気配、波の音、土の匂(にお)い、耳と眼(め)と鼻の記憶がたっぷり注ぎこまれている。
さていよいよ「小説家の開高さん」である。奇跡のような仕事に遭遇したのは一九八八年。
場所は、かつて耽読(たんどく)した釣り文学の古典『釣魚大全』の著者、アイザック・ウォルトンゆかりのダブ川。フライフィッシングの連れは座右の書『フィッシュ・オン』の著者、開高健。
じつは、釣り三昧(ざんまい)の一カ月の回想を綴(つづ)ったこの短編のなかに、釣り人としての開高健の本質をざぶりと洗いだす一行がある。わずか十三字。しかし誰もけっして書かなかったそらおそろしい一行が、「小説家の開高さん」の深淵(しんえん)をのぞきこませる。
コピーライターの短編デビュー作。ときおり警句や箴言(しんげん)が織りこまれ、計算ずくの構成に興をそがれるきらいはあるものの、それを嫌みに転ばせないのは、ほのかな含羞(がんしゅう)の気配だろう。
十編それぞれ、ざらつきのあるほろ苦い余韻がある。よい短編は読みおえたとき、しばらく黙りこみたくなるものだ。
ところで「骨董屋の善二さん」では、湯島の居酒屋「シンスケ」の主人が燗(かん)をつけるとき、徳利(とっくり)の尻をさりげなく撫(な)でて温度をたしかめる場面が描かれる。
その手つきは手練(てだれ)の痴漢にも似て自然であり、悩ましい。
ああもう。わたしもあの所作にはおおいに反応するものだが、当意即妙。「手つき」を「筆致」に置き換えてみれば、あら自著解説の一文になりますね。
朝日新聞 2009年9月6日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。