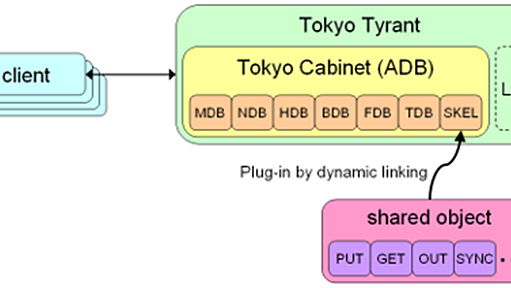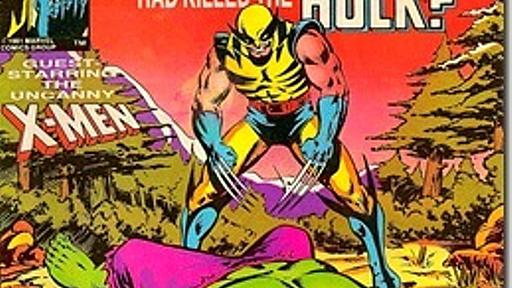サーバを安全に運用する施設として構築されるデータセンターですが、グーグルではそのデータセンターですら"落ちる"ことがあると想定してアーキテクチャを構築しています。 米グーグルが今年の5月に行ったイベント「Google I/O」で、同社のGoogle App Engine datastore leadであるRyan Barett氏が行った講演「Transactions Across Datacenters (and Other Weekend Projects)」のビデオがYouTubeで公開されました。 Barett氏は、担当しているGoogle App Engineのデータベースに関してグーグルが「multihoming」(マルチホーミング)と呼ぶ複数のデータセンターを用いた処理を実現している理由として、データセンターが自然災害や停電に見舞われたり、メンテナンスなどによるデータセンターの