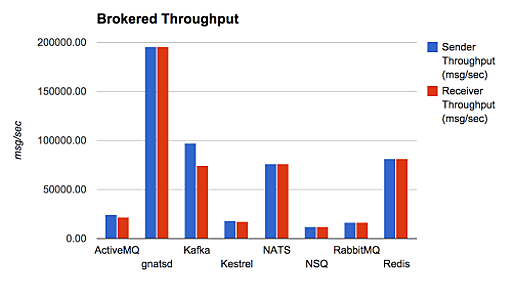eXcale開発チームの泉谷(@syguer)です。 今回は前回に続き、Message QueuingのためのミドルウェアであるRabbitMQでクラスタリングする方法について紹介します。 ※本記事ではバージョン3.x以降のクラスタ設定について紹介しています。2.x系とはコマンドや設定方法が異なる場合があります。 RabbitMQのクラスタリング RabbitMQではすべてのノードが起動しているactive/active構成でクラスタリングを行います。 クラスタリングは以下の2つの要素で実現されています。 1.クラスタ 複数のRabbitMQノードに互いを認識させてクラスタを構成します。 クラスタのノード同士は、5672(TCP)ポートをつかってお互いに死活を監視します。 監視の間隔はデフォルトで60秒となっています。 また、クラスタを構成するとノード間でキューを共有します。