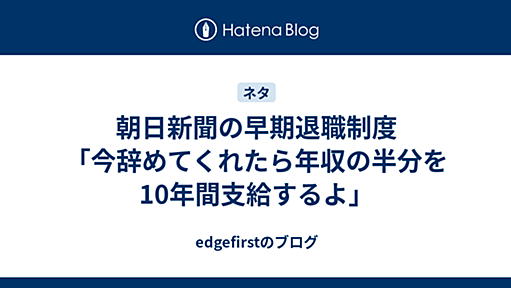新聞記者たちの不安を聞きに行く 【第二回】 日経新聞記者たちの小さな怒り オレたちの仕事はなくなるのか会社はどうなる 文:井上久男 【第一回】 はこちらをご覧ください。 [文:ジャーナリスト 井上久男] いま新聞各社は、生き残りをかけてネットの世界に新たな収益源を求めようとしている。だが、日経新聞を筆頭に、現場の記者から漏れるのは不満の声ばかりだ。 成功なのか、失敗なのか 「仕事がきつくなった・・・58%」 日本経済新聞の労働組合が今夏、「健康・福利厚生アンケート」で、1年前と比べて仕事の負担が増えたかなどを聞いた調査の結果だ。この背景には人減らしも影響している模様だが、組合報では「電子版の創刊で仕事がきつくなったと答えた人も全体の4割近くいた」と説明している。 実際、アンケートには、 「電子版独自コンテンツの取材が増えた分、忙しくなった」 「少ない人数で24時間カバーするので勤務時間が不