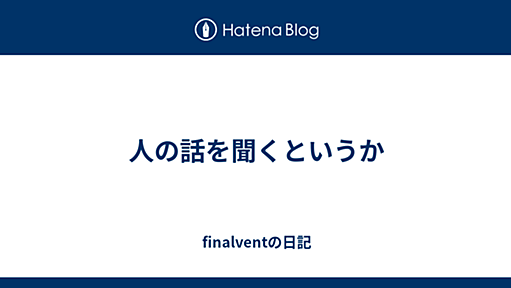苦吟するの言い換えや別の言い方。・新しい表現を苦心して生み出すこと苦吟する呻吟する悪戦苦闘する四苦八苦するもがき苦しむ
タグ
- すべて
- *clip (1031)
- *highbrow (1410)
- advertising (53)
- anime (117)
- architecture (27)
- art (260)
- astronomy (59)
- award (215)
- blog (315)
- blogosphere (49)
- book (4492)
- brain (20)
- business (117)
- cgm (4)
- checktest (39)
- cinema (975)
- color (8)
- column (48)
- comic (110)
- communication (445)
- critic (274)
- dance (41)
- design (95)
- dictionary (46)
- discussion (1)
- drama (92)
- encyclopedia (52)
- english (51)
- fantasy (314)
- fashion (17)
- flash (23)
- future (18)
- glossary (98)
- google (82)
- gourmet (12)
- hatena (25)
- hatenab (115)
- hatenad (7)
- health (12)
- history (51)
- idea (31)
- image (121)
- japanese (105)
- knowledge_community (160)
- life (9)
- lifehack (168)
- links (348)
- literature (1374)
- living_theater (122)
- lyrics (73)
- magazine (60)
- mail (1)
- management (27)
- map (4)
- marketing (28)
- mathematics (24)
- media_literacy (28)
- mental_health (80)
- moving_image (265)
- music (570)
- neta (131)
- news (44)
- online_music_distribution (49)
- pc (11)
- perfume (8)
- philosophy (118)
- photo (70)
- physics (15)
- poem (1225)
- portal (52)
- proverb (104)
- psychology (136)
- quantum_mechanics (30)
- ranking (411)
- reading (118)
- romance (208)
- rss (27)
- sbm (104)
- science (33)
- search (450)
- security (22)
- self-development (208)
- sf (511)
- sns (17)
- society (108)
- software (10)
- sound (9)
- spiritual (36)
- subculture (18)
- tale (104)
- technology (2)
- thinking (72)
- tips (66)
- tool (58)
- trend (51)
- trivia (37)
- twitter (1)
- usability (2)
- web (185)
- web2.0 (112)
- web_design (14)
- web_service (127)
- word (167)
- writing (190)
- あとでブクマコメント (31)
- あとで記事を書く (36)
- セルクマ (192)
- 俳句 (7)
- 十月 大江健三郎が暗 (1)
- 少女漫画 (58)
- 書 (7)
- 短歌 (141)
- book (4492)
- *highbrow (1410)
- literature (1374)
- poem (1225)
- *clip (1031)
- cinema (975)
- music (570)
- sf (511)
- search (450)
- communication (445)
関連タグで絞り込む (47)
- *clip
- *highbrow
- blog
- blogosphere
- book
- business
- column
- communication
- design
- dictionary
- english
- glossary
- hatena
- hatenab
- history
- idea
- japanese
- lifehack
- links
- literature
- magazine
- marketing
- media_literacy
- moving_image
- neta
- news
- poem
- portal
- proverb
- psychology
- reading
- romance
- sbm
- security
- self-development
- sf
- tale
- thinking
- tips
- web
- web2.0
- web_service
- word
- あとでブクマコメント
- あとで記事を書く
- セルクマ
- 短歌
writingに関するinmymemoryのブックマーク (191)
-
 inmymemory 2021/07/19
inmymemory 2021/07/19- poem
- writing
リンク -
「小説」や「物語」を書きたいひと向けの本を並べてみたよ☆ - がらくた銀河
「小説」とか「物語」とか書きたいひとへ。 わたしが読んで面白かったその手の本をテケトーに、イロイロとりまぜて並べてみるYO! えーと、まずはじめに、なんのかんのとバランスが取れていると思うのがこちら。 ストーリーメーカー 創作のための物語論 (星海社 e-SHINSHO) 作者:大塚英志講談社Amazon で、これをここから読むよりは、つまりお話の順序に従って、 物語の体操: みるみる小説が書ける6つのレッスン (朝日文庫 お 49-1) 作者:大塚 英志朝日新聞出版Amazon と、 キャラクター小説の作り方 (角川文庫 お 39-13) 作者:大塚 英志,寄藤 文平KADOKAWAAmazon いま絶版みたいだからこっちを↓ キャラクターメーカー 6つの理論とワークショップで学ぶ「つくり方」 (星海社 e-SHINSHO) 作者:大塚英志講談社Amazon物語の体操 物語るための基礎体
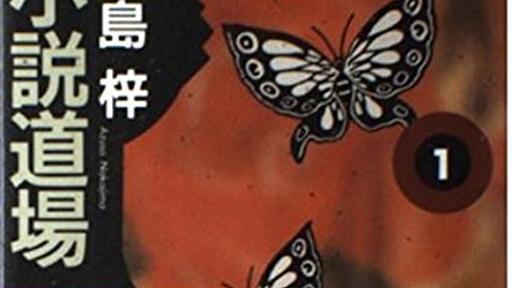

-
フラナリー・オコナー『フラナリー・オコナー全短篇 下』(1956-) / Pulp Literature
★★★★ 岩波新書 / 2007.10 ISBN 978-4004310952 【Amazon】 著者が様々な本から収拾した文章についての書き抜き。それらの引用をもとに、文章を書くための手立てを探っていく。基本から文章修業まで全38章。 著者は1930年生まれの元新聞記者。本書は『文章の書き方』【Amazon】の姉妹編で、技術論よりも精神論に重きを置いている。 感性を磨く・毎日書く・とにかく削るなど、多種多様な方策が載っているけれど、結局は序文にある「文は心なり」に尽きるのだろう。著者は文章の核心について次のように述べている。 (……)いい文章のいちばんの条件は、これをこそ伝えたいという書き手の心の、静かな炎のようなものだということです。大切なのは、書きたいこと、伝えたいことをはっきりと心でつかむことです。そのとき、静かな炎は、必要な言葉を次々にあなたに贈ってくれるでしょう。(p.ii)
-
-
意識の流れ - Wikipedia
意識の流れ(いしきのながれ、英: Stream of consciousness)とは、米国の心理学者のウィリアム・ジェイムズが1890年代に最初に用いた心理学の概念で、「人間の意識は静的な部分の配列によって成り立つものではなく、動的なイメージや観念が流れるように連なったものである」とする考え方のことである[1]。 アンリ・ベルクソンも時間と意識についての考察の中で、ジェイムズと同時期に同じような着想を得て、「持続」という概念を提唱している(ベルクソンとジェイムズの間には交流があったが、着想は互いに独自のものとされることが多い)。 この「意識の流れ」の概念は、その後文学の世界に転用され、「人間の精神の中に絶え間なく移ろっていく主観的な思考や感覚を、特に注釈を付けることなく記述していく文学上の手法」という文学上の表現の一手法を示す言葉として使用されて文学用語になった[1]。 この手法を小説の
 inmymemory 2009/05/03意識の流れ手法を用いたイギリスの小説家、ジェイムズ・ジョイス(『ユリシーズ』)、ヴァージニア・ウルフ(『灯台へ』)、キャサリン・マンスフィールド、ドロシー・リチャードソン、フォークナー(『響きと怒り』)
inmymemory 2009/05/03意識の流れ手法を用いたイギリスの小説家、ジェイムズ・ジョイス(『ユリシーズ』)、ヴァージニア・ウルフ(『灯台へ』)、キャサリン・マンスフィールド、ドロシー・リチャードソン、フォークナー(『響きと怒り』) -
-
物語の類型 - Wikipedia
この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。 他の出典の追加も行い、記事の正確性・中立性・信頼性の向上にご協力ください。 出典検索?: "物語の類型" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2018年10月) 人が接する数々の物語には類似のものが多く認められ、こうした物語を類型として捉えることは各ジャンル内で、あるいはジャンルを跨って多く行われてきた。ただし、物語の類型化には様々なアプローチがある。物語に登場する人物類型によるもの、物語を構成するモチーフによるもの、物語の構成そのものであるプロットによるもの、物語のストーリーによるもの、物語の表現様式によるものなどであるが、多くの場合はストーリー、プロットもしくはモチーフに基づく類型化を指す。 物語を類型に分けるということ
-
-
清水 良典 「2週間で小説を書く!」 - 情報考学 Passion For The Future
2週間で小説を書く! スポンサード リンク ・2週間で小説を書く! 文芸評論家が教える小説の書き方。 「自分が何かひとかどの、個性的な人間のつもりで得意になって語っているような小説なんか、誰も読みたくない。お前のことなんか、べつに知りたくないんだよ、と言ってやりたくなる。そういう冷たい目を向ける厳しい読者、というより何の関わりも興味もない読者の他人をも引きつけるような力を魅力というのである。」 そういう魅力のある文章を書くためのトレーニング方法が2週間分、この本に紹介されている。たとえば複数人数でリレー小説を書く、とか、最初の記憶を書く、人称を変えて書く、など。古今東西の名文を例にしての分析が参考になる。 小説は書いてみたいと思っている。たまに少し書いてみるが完成したためしがない。場面の描写はできるのだが、物語が作れない。物語を先に作ろうとして、思いついた筋を書き出してみると、ありきたりの
-
文章読本 (三島由紀夫) - 情報考学 Passion For The Future
・文章読本 三島由紀夫の文章読本。そもそも最初に「文章読本」を書いたのは谷崎潤一郎だった。川端康成や三島など多くの文豪たちが追随して同名の著作をそれぞれ書き下ろしている。読み比べると面白い。文章の書き方、読み方を教える内容という点では共通しているが、作家によって実用的な文章指導であったり、高尚な芸術論であったり、個人的な感慨エッセイ集だったりする。 三島由紀夫の文章読本は、書き手の実用性という面ではほぼゼロだ。一部に技巧論はあるのだけれど、読者が到底真似の出来ないようなことを書いている。たとえば会話文をどう書くべきかについては、米国の作家の意見を引用する形で、 「小説の会話というものは、大きな波が崩れるときに白いしぶきが泡立つ、そのしぶきのようなものでなければならない。地の文はつまり波であって、沖からゆるやかにうねってきて、その波が岸で崩れるときに、もうもちこたえられなくなるまで高くもち上
-
文章は接続詞で決まる - 情報考学 Passion For The Future
・文章は接続詞で決まる 「「てか」を好んで使う人は、すぐに新しい話題に移りたがる飽きっぽい人かもしれませんし、「ようするに」が口癖の人は、結論を急ぎたがるせっかちな人なのかもしれません。「でも」をよく使う人は、他人の言うことを素直に受けいれるのが苦手な頑固な人である可能性があります。「だから」を使いたがる人は、自分の主張を人に押しつけたがる押しの強い人かもしれませんし、「だって」を好む人は、言い訳が癖になっている、自己防衛本能が強い人かもしれません。」 接続詞の使い方を見ると隠れた性格がわかるという話。特に講義のような独話では接続詞は書き言葉の2,3倍も多く使われるそうだ。シーン別によく使われる接続詞ベスト5の比較が面白かった。文章のらしさは接続詞が決めている部分も多そうだ。 新聞:しかし、また、だが、一方、さらに 小説:しかし、そして、それで、だが、でも 講義:で、それから、そして、つま
-
文章をダメにする三つの条件 - 情報考学 Passion For The Future
・文章をダメにする三つの条件 文章術の類書は多いが、こうすると文章がダメになるという作文の「べからず」という視点で書かれているのが本書の特徴だ。著者は元読売新聞社のデスクで、大学や文化センターで作文を教えるベテラン。豊富な授業経験から学生たちが陥りがちな悪い傾向を3つみつけたという。 1 文章の意図がつかめない事実や印象の羅列 2 読み手が退屈する理屈攻め 3 読み手の興味をひかない一般論 私も学生時代は作文はあまり得意ではなかった。今思えば、授業という文脈では、書く動機が弱すぎるのだ。提出した作文にはそもそも書く意図などなかった。だから、原稿用紙を埋めるために理屈と一般論を展開していた。 こうした傾向を避けるためのコツとして、書くポイントをひとつに絞ること、書き手の特異な個人的体験に逃げ込むこと、細部の観察にこだわること、など多くのポイントが、学生の作文例を肴にして明解に語られている。
-
-
平凡なわたしが非凡な文章を書くために「不良のための文章術」
小飼弾氏の文が非凡なのは、弾氏が非凡だから。では、平凡なわたしは凡庸な文しか書けないのか? それは違う、やり方しだい。 その「やり方」を教えてくれるのが本書。 おっと、いそいで注釈を入れなければならないのは、この「非凡な文」について。「非凡な文」とは、読み手の心を動かすもので、納得・共感だけでなく、反発・批判も含まれる。感情のベクトルは関係なく、スカラーが大なるものこそ「非凡な文」なの。 そして本書、「不良のための」とは、要するにカネになる文章だということ。出版社が原稿料を払う気になる文章であり、読者がカネ出して買う気になる雑誌や本に載っている文章のこと。弾氏の文章もこれにあたる。 座右にしたい本書の目玉は、「凡庸な文が非凡な文に仕立て上げられていくプロセス」がこと細かに解説されているところ。最初は、箸にも棒にもかからない「書評」や「グルメガイド」の例文が出てくる。そいつを徹底的に調理しつ

-
人の話を聞くというか - finalventの日記
⇒本を読まない人間 私は本を何冊読むかというのはどうでもいいことじゃないか以下略なんだけど。 繰り返し読む本は、その著者の内的な感覚に耳を澄ましているという感覚がある。 というか、人の話を聞いているというか。 私は若い頃、今でもそうかな、人の話を聞かないとよく叱責された。この話は書いたけど、それは大半は私がさっさと話をマクロ処理してその権力性を脱色してしまうからのようだ。人の話を聞けというのは、ようするに命令なのだから。 それはそれとして。 私は、人の話を、自分としてはよく聞いている。声とか論理とか、特に、言葉と言葉使いの感性を。 特に、言葉のなかのある内的な感性の揺らぎみたいのを聞き分けようといつも無意識の努力をしている。 文章のうまい人や頭のよい人というのはいて、そういう人は、ある程度文章をそのままマシン的にかける。わかりやすく明解というか。でも、そこの内的な感覚はおもむろに欠落してい
-
首吊り芸人は首を吊らない。 本当の文学の話をしよう その2
本それ自体は不変であり、一方人々の意見は、往々にしてそれに対する絶望の表現でしかない。(フランツ・カフカ) 前回の記事から続いているような気がするが、それは気のせいかもしれない。 ◇◇◇ 愛は祈りだ。僕は祈る。 舞城王太郎は「好き好き大好き超愛してる。」という小説の1行目でこう書いた。「祈り」というものがなんであるか、それは後に考察されている。 祈りは言葉でできている。言葉というものは全てをつくる。言葉はまさしく神で、奇跡を起こす。過去に起こり、全て終わったことについて、僕達が祈り、願い、希望を持つことも、言葉を用いるがゆえに可能になる。 今となればこの言葉は実感できる。文章は、言葉というのは祈りとして働く。僕はこの前の記事で文学についていろいろ書いた。そして僕は僕らがどうあるべきかを書いた。何故なら、僕は僕が書いたことをひとつとして実現できていないからだ。言葉とは祈りなのだ。 戦後

-
デタッチメントとコミットメント - shumpei@blog
博士(総合政策) 矢尾板俊平責任編集! 本ブログにおける著作権は、矢尾板俊平に帰属いたします。 なお、本ブログの内容については、矢尾板俊平の所属する機関等とは一切関係なく、矢尾板俊平が発信する個人的見解や芸術的表現です。 村上春樹作品が人々に受け容れられる理由についてのヒントは、河合隼雄氏との対談である『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(1996年)のなかの村上春樹氏自身の発言にある。 村上春樹氏は、自身の表現方法について、次のように述べている。「そのデタッチメント、アフォリズムという部分を、だんだん「物語」に置き換えていったのです。その最初の作品が、『羊をめぐる冒険』という長編です」という段階があり、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』まで来たと述べている。また、「それから自分がもう一段階大きくなるためには、リアリズムの文体をこのあたりでしっかりと身につけなくてはならないと思

-
ストーリーとプロットの違い - 漫棚通信ブログ版
ストーリー、そしてプロットという言葉はよく聞きますし、わたしも使ってるのですが、このふたつの違いは何か。みなさんは、ぱっと答えられるでしょうか。 実はこれについてわたしが意識したのは、野田昌宏『スペース・オペラの書き方』(1988年早川書房)を読んだときでした。この本ではストーリーとプロットの違いについて、SF作家、今日泊亜蘭が自作を語る形で、このように述べられています。 そりゃそうだよ、お前、いいかね、『光の塔』で言ゃぁ……だ。 未来の連中が、自分たちの悲惨な現状をなんとかしようと、原子力を乱用してその原因を作った過去の歴史を改変しようと狙って未来から攻め込んできやがって……と、 これが『光の塔』のプロットよ。 それに対して、な。 まず、本の冒頭で主人公が木星から帰ってくる宇宙船のなかから窓外に奇妙な飛び火を見る。 そして地球に帰って来てから渋谷で原因不明の絶電現象に出会わす。 それから

-
ゆーすけべー日記: 「文章のみがき方」辰濃和男
サキとは彼女の自宅近く、湘南台駅前のスーパーマーケットで待ち合わせをした。彼女は自転車で後から追いつくと言い、僕は大きなコインパーキングへ車を停めた。煙草を一本吸ってからスーパーマーケットへ向かうと、ひっきりなしに主婦的な女性かおばあちゃんが入り口を出たり入ったりしていた。時刻は午後5時になる。時計から目を上げると、待たせちゃったわねと大して悪びれてない様子でサキが手ぶらでやってきた。 お礼に料理を作るとはいえ、サキの家には食材が十分足りていないらしく、こうしてスーパーマーケットに寄ることになった。サキは野菜コーナーから精肉コーナーまで、まるで優秀なカーナビに導かれるように無駄なく点検していった。欲しい食材があると、2秒間程度それらを凝視し、一度手に取ったじゃがいもやら豚肉やらを迷うことなく僕が持っているカゴに放り込んだ。最後にアルコール飲料が冷やされている棚の前へ行くと、私が飲むからとチ

-
わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる: 「レトリックのすすめ」でマスターしたい12の文彩
文章うまくなりたいくせに、ロクな努力をしていない。 文章読本や入門本、「○○の書き方」サイトを漁っては自己満足に淫する。量は質に転化するとはいうものの、駄文はいくら書いても駄文。カラまわりする向上心のギアをローに入れ、テクニカルな部分―― すなわち、「レトリック」に注力してみよう。 「レトリック」といえば、美辞麗句とか口先三寸とか、たしかに評判はよくない。「それはレトリックにすぎない」なんて、内容ゼロを非難する決り文句だし。 それでも、上手くなりたい。いままでの「書き方」だけでなく、違った彩りや味付けを目指したい。技巧が鼻につくかも恐れもあるけれど、さじ加減を考えて磨きたいもの。ネタ(選書)も大事だが、そのネタを引き立たせるのは技術だ。精進にちょうどいい本を読んだので、(わたしの勉強がてら)ご紹介~ ■ 文章の目的 著者によると、文章の目的は「人を説得するために書くもの/書かれたもの」だと

公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く