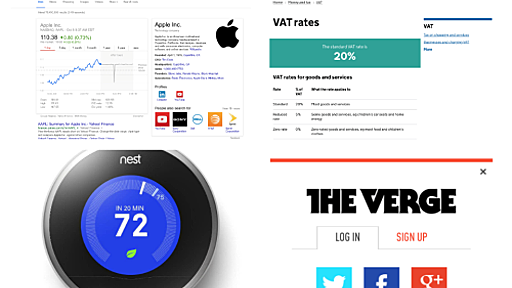スマートフォンの使い方が、脳に影響を与えることがあります。ある調査によると、毎日スマートフォンを使う人は、脳の体性感覚皮質が大きいことがわかりました。体性感覚皮質は、親指のコントロールをつかさどる部位です。 また、ほかの調査では、ほとんどのユーザーがスマートフォンを片手で操作していることが明らかになりました。スマートフォンを握っているとき、ユーザーは左右どちらかの親指で画面を操作しているのです。親指はユーザーにとってマウスのようなものですが、その動きには限界もあります。 親指はマウスの代わり デスクトップデバイスでは、ユーザーは画面の操作にマウスを使用します。ナビゲーションメニューまでマウスを動かすことは簡単です。なぜなら、マウスは手首の動きを制限しないからです。 しかし、ユーザーがスマートフォンを握っているとき、親指は限られた範囲でしか動けません。画面に親指が届かない領域があるのです。こ