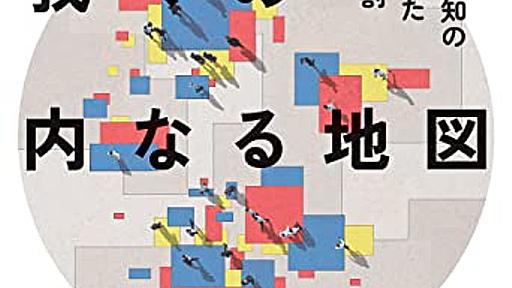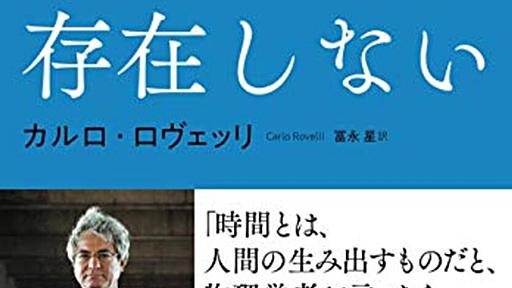エビデンスを嫌う人たち: 科学否定論者は何を考え、どう説得できるのか? 作者:リー・マッキンタイア国書刊行会Amazonこの『エビデンスを嫌う人たち』は、『「科学的に正しい」とは何か』の邦訳が先日刊行された気鋭の哲学者リー・マッキンタイアによる「科学否定論者を説得するための方法」についての一冊である。科学否定論者とは、たとえば人為的な気候変動は起こっていないと主張する気候変動否定者に、反ワクチン、反コロナ、果てには地球は平面だと主張する地球平面説を支持している人らのことを指している。 こうした科学否定論者に共通点は存在するのか。また、彼らにエビデンスを提供することでその考えを変えることができるのか。エビデンスを提供するといっても、どのように提供するのが最も効果的なのか。エビデンスで人の意見が変えられないのだとしたら、他に変える方法はあるのかを、様々な研究をもとにして紹介する──だけでなく、