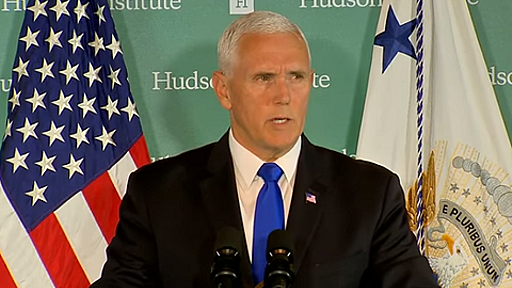2018年10月12日のブックマーク (26件)
-
 kiyo_hiko 2018/10/12
kiyo_hiko 2018/10/12 -
-
ヤマトホールディングス、自律飛行する輸送機を開発へ - ITmedia NEWS
ヤマトホールディングスは10月12日、米国のヘリコプターメーカー、Bell Helicopter(Textron傘下)と、自律飛行する輸送機を共同開発すると発表した。2020年代半ばまでに実用化する計画だ。 Bellは、輸送用の容器(ポッド)を搭載するeVTOL(電動垂直離着陸機)の設計、開発、製造を主導する。小型機は最大7キロ、大型機は453キロの荷物を積み、時速160キロ以上で飛行するとしている。ヤマトホールディングスは、これまで培った物流業務のノウハウを生かしポッドを開発。両社は2019年8月までにデモンストレーションを行う考え。 Bellのスコット・ドレナン氏(イノベーション部門バイス・プレジデント)は「両社が協力することで、新しい空の輸送方法を実現し、将来の大規模物流の先例を世界に示したい」としている。 関連記事 開発中の「空飛ぶクルマ」まとめ Uber、ロールスロイス……参入相

-
女性エンジニアだけどもう勉強会には行かないと思う
(15:30 追記しました) やるせないのでここに書かせてほしい。 この前初めてIT系の勉強会に行った。 いままで勉強会というものに行ったことがなかった。 IT技術者はよく勉強会に行く。同業の知人にどうして行かないの?と聞かれたときに、コミュ障だから…と答えたことがあった。 それも理由のひとつだけど、本当は、私が女性で、変な人に絡まれたら嫌だな…と思っていたからだった。 (自分で言うのもなんだけど)愛想がよくて優柔不断なせいか、変な人に絡まれることも少なくない。 そして何より、変な人に絡まれたときに気持ちを切り替えられず落ち込んでしまうタイプなので、あまり不特定多数と交流したくなかった。 最近は女性限定の勉強会やコミュニティも活性化していてとても良い傾向だと思う。 ただ、私が関心のある言語についての女性限定勉強会はなかったので、一念発起してあるコミュニティに顔を出した。 コミュ障だけど交流

-
Light Table docs
Getting Started ###Full tutorials Getting started with Light Table ###Opening and creating new files To create a new file, use the New file menu item in the File menu or press cmd/ctrl-n To open a file, use the Open file menu item in the File menu or press cmd/ctrl-shift-o ###With Clojure If you have some Clojure code in a file already, you can get going with inline eval by: Create a new file and

-
-
コロンブスの地図に隠されていた秘密、明らかに | ナショナルジオグラフィック日本版サイト
500年前の地図に隠れていた文字が解明され、地図製作者の情報源や、後年製作された重要な地図への影響が明らかになった。(IMAGES BY LAZARUS PROJECT / MEGAVISION / RIT / EMEL、 COURTESY OF THE BEINECKE LIBRARY、 YALE UNIVERSITY) 1491年に製作されたこの写真の地図は、クリストファー・コロンブスが初の大西洋横断に挑んだ当時に認識されていた世界の姿を表した地図として、最も良い状態で残っているものだ。コロンブスは航海の計画を立てる際、実際にこの地図の写しを使っていた可能性が高い。(参考記事:「コロンブスに勝てなかった“新大陸発見者”とは?」) この地図を描いたのは、ドイツの地図製作者ヘンリックス・マルテルス。地図には当初、土地にゆかりの伝説や解説文が大量にラテン語で記されていたが、その大半は時と共に

-
-
-
地球温暖化の影響は想定より深刻、IPCCが警告 | ナショナルジオグラフィック日本版サイト
地球温暖化を食い止めるために、森林破壊を防ぐべき場所として、新しい報告書はブラジルが鍵となる国のひとつだという。(Photograph by John Stanmeyer, National Geographic Creative) 世界の平均気温が産業革命前と比べて1.5℃上昇した場合、その影響と負担はこれまでの想定をはるかに超えるものになるだろうと、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が警告を発した。6000件におよぶ調査研究に基づいたこの「1.5℃の地球温暖化に関する特別報告書」は、韓国の仁川で開催されたIPCCの総会で10月8日に公表された。 世界の平均気温はすでに産業革命前から1℃上昇している。この10年間には、世界中の国や地域が、記録的な嵐や森林火災、干ばつ、サンゴの白化、熱波、洪水に見舞われてきた。報告書によれば、気温の上昇が1.5℃に達した場合、状況は大幅に悪化す

-
-
-
-
「この先のサイトには有害なプログラムがあります」という警告 | 初心者SEのとりあえずメモ日記
私は、http://mergedoc.sourceforge.jp/でeclipseをダウンロードしようとしたのですが、上記の画面が表示されてダウンロードできず。 真っ赤な背景に、恐ろしい警告なので、最初はおどろいてしまいました。 vectorや窓の杜でも 調べてみたところ、vectorや窓の杜などのサイトでファイルをダウンロードしようとした際にも、同様のことが起きるとの報告がありました。 vectorで“Google セーフ ブラウジング”が警告を表示 vectorでフリーソフト(下記に該当URL)をダウンロードしようとすると 「この先のサイトには有害なプログラムがあります…(Google セーフ ブラウジング)」と警告が表示されます。

-
-
獅音のチラ裏: PCトラブル:Windows Updateの再起動後、再構成準備中Mesから先に進まない
日常生活などで遭遇したちょっとしたトラブルを解決した方法、ゲームの小ネタなどをいろいろとさらしていくページです。情報は随時更新されていく、予定です。 最低1ヶ月に1回は発生する Windows OS のシステムアップデートですが、まれにアップデート前後で変なトラブルが起こることがあります。 そのなかでも比較的遭遇頻度が高いのが、「再起動後のシステム再構成(フェーズ3/3)画面で、Windows の更新準備中のメッセージから先に進まない」というものです。 この再起動後の画面では、システム起動中(=ファイルやディスク使用中)には行えない設定の変更や適用を行うようです。 (ちなみに Windows そのものが起動しているとまずいものは、更にその前の段階で更新されるようですが) このためか、上記画面の注釈として「電源を切らないでください」という文言が表示されています。 もしこの変更や適用の間に電源
-
クソくらえ、ブルジョワジー
就活相談をしている人のTwitterを見るとあら不思議 「早いうちから留学やインターン等で特別な経験を積んでおきましょう」「既卒は圧倒的に不利なので就留を勧めます」 わおすごい、留学とか就留とかそっちの世界では簡単にできるのね いや別にしなきゃいけないわけじゃないけどさ、その選択肢が当たり前のように提示できることそのものが、ああもう生きてる世界が全く違うんだなって感じ。すごい。分断社会ってこういうことなのね。大学通うためにはバイトで稼がなきゃいけない私どもとはベースが違うのよ。あなたたち「自己破産した。本当にごめんなさい」って50歳近くの親が泣きながら子どもに謝罪してくる光景見たことないでしょ。それはもうすごい見ものよ。一生忘れられないわ てか「ガクチカ」ってなによ。こっちが強いられてバイトしてる間に、実家の経済状況気にすることなくインターンとか起業とかボランティアとか留学とかやってる奴ら

-
半透明でも見やすいかもしれないvim color scheme - Qiita
vimのcolorschemeは世の中に大量にあります。 自分も色々参考にさせていただきながら試してみてました。 nanotech/jellybeans.vim w0ng/vim-hybrid altercation/vim-colors-solarized chriskempson/tomorrow-theme とはいえ、黒背景に設定している方向けに、彩度が抑えめのschemeが多いように思います。 自分はターミナルの設定を半透明にしていたため、黒背景を前提としているcolorschemeだと、全体的に濃淡の差が少ない見た目になってしまい、濃淡がはっきりしているschemeがいいのかな、と。 半透明でも見やすいのは無いものか まぁ、見やすいっていうのは主観や開くファイルタイプによって変わったりするので、絶対的なものはないのですが、 ひとまず、彩度が高めで、くっきりしたschemeを何個か

-
vim の マクロ記録、閲覧、削除
背景 vimをあまり使っていなかったので、マクロの使い方がよく分からなかったのですが、基本的な使い方が分かったので備忘録として残します。 マクロとは vimには打ち込んだコマンド(命令)の集合を保存して、何度も繰り返すなどできるマクロ機能があります。 マクロの記録 ノーマルモードの状態で、「qとアルファベット1文字(マクロ名)」を入力するとマクロが記録され、「q」で記録を終了します。 例) qa → マクロの記録 → q マクロの記録では、例えば 「i hoge esc」 と入力すると、「挿入モードへ切り替え、hogeと入力して、ノーマルモードへ変わる」というマクロを記録できます。 記録したマクロはノーマルモードで例えば 10@a (:は入りません)と入力することで 10回 aというマクロを実行します。 (上記の例では、10回 hogeと入力します) *vim初心者の僕は、よくノーマルモー

-
tmuxを必要最低限で入門して使う - Qiita
#はじめに 今回は、端末多重化ソフトウェアのtmuxを学習していきます。これにより、ターミナル画面を複数開いたり、ターミナルソフト独自のショートカットキーを覚えてペインを分けたりするみたいな非効率的な開発環境を改善していきます。 タイトルの「必要最低限」とは、これらの新しいソフトの学習に時間をかけたくないので、私が使っているtmuxの機能・設定だけをピックアップして本記事に記述するという意味です。 #開発環境 Mac OS X El Capitan Homebrew 1.6.3 (パッケージマネージャー) tmux 2.7 #tmux tmuxとは tmuxは端末多重化ソフトウェアと表現されるが、要は1つのターミナル上で複数のターミナルを立ち上げて同時並行で作業できるものと思ってもらえれば良い。 パッケージとしてインストールすることができ、サーバ側でインストールしていればSSHを通じてクラ

-
-
-
pathogen.vim を使って気軽に Vim のプラグインを管理する
1. まえがきVim では、今までいろいろなプラグイン管理ツールが開発されてきており、新しいものほど高機能になってきています。しかし、高機能過ぎて中で何をやっているのか分からない部分が増え、操作を間違うとわけが分からないことになります。 「久しぶりにプラグインでも更新してみるか」という時に、警告やらエラーやらが発生してしまうと本当に困ってしまうのです。 また、この手のツールは、Vim の設定ファイルにたくさんの設定を書いたりするのですが、時間が経つと書いてある意味を記憶しておくことが難しくなってきます。 そこで、pathogen.vim です。何年か前までは多くのユーザーに使われていたようですが、今 インターネットで検索しても、新しい情報がほとんど出てきません。しかし、その割には新し目の vim プラグインのインストールページを見ると、いまだに 「pathogen.vim でインストールす

-
-
Ansibleで開発用個人PCをセットアップする(vim,fedora,gnomeなど) - Qiita
はじめに この文章はAnsibleを用いて開発用個人PCをセットアップするときの手順・メモです。 Ansibleの情報は英語/日本語両方多く見られますが、個人用PCセットアップの例は少なかったので備忘録として残しておきます。 ※他の方も言われてましたが、個人用PCのセットアップなんてめったにないので自動化するメリットは少ないです。現実逃避 勉強用としてやってます。 要約 毎回やっている個人用PCのセットアップが(ほぼ)自動化できた。 でも個人用PCをセットアップする機会なんてあんまりない。 でも自動化できて気持ち的に満足した。 環境・対象 まず私の個人用PC環境は以下です。 Fedora 21 Gnome 3 Python 2.7.8 Ansible 1.8.2 ThinkPad X201 セットアップ対象は大きく以下です。(分類が微妙ですが) Fedora(yumでのインストールとか)

-
-

- 2018年10月13日
- 2018年10月12日
- 2018年10月11日
公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く