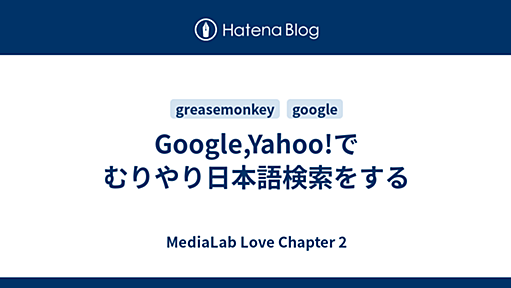幕張メッセで開催中の「CEATEC JAPAN 2007」で3日、次世代検索技術の開発を目指して経済産業省が進める「情報大航海プロジェクト」についての講演が行なわれ、慶應義塾大学環境情報学部教授の小川克彦氏がプロジェクトの意義と概要について解説した。 ● 次世代検索は「量から質へ」、知的情報サービスの実現を目指す 情報大航海プロジェクトは、経済産業省が2005年12月から開催した「ITによる『情報大航海時代』の情報利用を考える研究会」の参加メンバーを中心として、次世代の検索・解析技術の開発と、その技術を用いた事業について実証を行なうことを目的としたプロジェクト。現在、産学協同で技術開発や制度的課題の解決、実証事業などを進めており、次世代検索の共通技術のオープン化、標準化、法制度の整備などを行ない、新たなイノベーション創出環境の確立を目指すとしている。 小川氏は、「現在の検索技術は、数百億の
タグ
- すべて
- .Net (14)
- 2ch (71)
- 3D (98)
- 4K (30)
- 5G (17)
- 7pay (17)
- AI (205)
- ALS (166)
- AMD (37)
- AR (50)
- ATOK (31)
- AV (313)
- Adobe (83)
- Africa (50)
- Ajax (18)
- Amazon (294)
- Android (840)
- Anker (29)
- Apple (468)
- Asia (40)
- Asus (23)
- BTTF (22)
- Blu-ray (45)
- Bluesky (27)
- Bluetooth (98)
- C++ (43)
- CASIO (15)
- CCC (26)
- CG (15)
- CM (18)
- COVID-19 (480)
- CP+ (21)
- CPU (47)
- Canon (45)
- China (695)
- Christmas (21)
- Chrome (248)
- Chromecast (29)
- Copilot (17)
- CreativeCommons (34)
- DPZ (55)
- DRM (181)
- DVD (15)
- Darfur (116)
- DeNA (14)
- Dilbert (18)
- Dropbox (17)
- ESA (16)
- Earth (36)
- Egypt (19)
- English (86)
- Europe (73)
- FPD (48)
- Facebook (194)
- Felica (73)
- Firefox (122)
- Flash (82)
- Flickr (51)
- France (20)
- GPS (31)
- GR DIGITAL III (14)
- GXR (30)
- Galaxy (45)
- Georgia (22)
- Git (21)
- GitHub (14)
- Gmail (99)
- Google (1864)
- Google Drive (19)
- Google Home (35)
- Google+ (14)
- GoogleEarth (18)
- Gundam (137)
- HDMI (34)
- HTML (25)
- Honda (37)
- Huawei (94)
- IE (61)
- IIJmio (41)
- IME (25)
- ISAS (38)
- ISS (82)
- IT (137)
- India (14)
- Ingress (380)
- Intel (107)
- IoT (17)
- Iran (17)
- Iraq (22)
- JASRAC (102)
- JAVA (27)
- JAXA (465)
- JEITA (23)
- JR (69)
- JR東日本 (19)
- Japan (950)
- Jupiter (28)
- JustSystem (14)
- KDDI (54)
- Kadokawa (16)
- Keikyu (39)
- Kindle (82)
- KoderaNobuyoshi (105)
- Korea (306)
- LED (29)
- LGBT (16)
- LINE (106)
- LLM (32)
- LS北見 (35)
- LTE (16)
- Lenovo (18)
- Linux (32)
- Livedoor (42)
- Logicool (15)
- Luna (159)
- MIAU (85)
- MIT (14)
- MVNO (83)
- Macintosh (57)
- Mars (94)
- Mate 10 (14)
- Matrix (16)
- Mazda (18)
- Microsoft (681)
- MoriHiroshi (136)
- NASA (386)
- NEC (29)
- NHK (185)
- NTT (45)
- Netflix (19)
- Nexus (40)
- Nexus7 (20)
- Niantic (50)
- NieR (47)
- Nifty (34)
- Nikon (41)
- Nintendo (147)
- Nissan (48)
- OKGo (16)
- OLED (40)
- OS (24)
- OSS (68)
- OkadaYuka (111)
- Okinawa (63)
- Olympus (20)
- OpenAI (14)
- Opera (52)
- OriHime (21)
- PASMO (30)
- PC (62)
- PC遠隔操作事件 (28)
- Panasonic (104)
- Perfume (20)
- Persepolis (16)
- Pioneer (33)
- Pixel (135)
- PlayStation (124)
- Pluto (19)
- Pokémon GO (110)
- Qualcomm (21)
- RFID (15)
- RICOH (66)
- Russia (134)
- SARVH (14)
- SF (26)
- SNS (197)
- STS-124 (30)
- Safari (21)
- Samsung (58)
- Sanyo (55)
- Saturn (59)
- Sharp (35)
- Slack (29)
- Softbank (135)
- Sony (802)
- SpaceX (26)
- Starwars (118)
- Sun (46)
- Surface (15)
- Switch (85)
- TEL (21)
- TPP (29)
- TV (447)
- TWS (15)
- Tibet (30)
- Toshiba (71)
- Toyota (24)
- Twitter (712)
- UI (70)
- UK (186)
- UN (20)
- UNREAD (29)
- USA (634)
- USB (47)
- USB PD (35)
- USB Type-C (50)
- UX (18)
- UmedaMochio (70)
- VR (43)
- VSCode (31)
- Venus (17)
- Vietnam (21)
- Vim (21)
- VisualStudio (54)
- WW2 (31)
- WiFi (120)
- Windows (657)
- Windows 10 (104)
- Xperia (62)
- XperiaZ1 (20)
- XperiaZ4 (17)
- YAMAHA (33)
- Yahoo (130)
- Yokohama (52)
- YouTube (160)
- Zoom (19)
- academic (19)
- accident (51)
- advertising (25)
- airplane (124)
- animal (88)
- anime (740)
- application (211)
- aprilfool (42)
- art (263)
- asteroid (15)
- astronomy (489)
- au (166)
- audio (402)
- award (62)
- bag (17)
- bank (23)
- battery (99)
- bicycle (40)
- blog (396)
- book (764)
- booksearch (16)
- brain (111)
- browser (111)
- business (1942)
- calamity (85)
- calendar (23)
- camera (1095)
- campaign (66)
- career (26)
- case (331)
- cat (117)
- character (38)
- child (219)
- cinema (536)
- coffee (24)
- comet (20)
- comic (850)
- commented (52)
- communication (572)
- computer (419)
- confectionery (84)
- copyright (1331)
- crisismanagement (42)
- culture (81)
- design (313)
- development (407)
- device (435)
- diplomacy (393)
- disc (241)
- disease (152)
- display (21)
- docomo (167)
- dog (14)
- download (26)
- drink (28)
- eclipse (29)
- economy (234)
- education (219)
- election (150)
- electronics (135)
- energy (83)
- enquete (18)
- environment (235)
- etc (41)
- eva (117)
- event (454)
- evernote (36)
- exoplanet (43)
- exploration (241)
- fashion (19)
- finalvent (26)
- fitness (37)
- font (168)
- furniture (47)
- future (68)
- gadget (1423)
- game (815)
- gender (28)
- genocide (35)
- glasses (29)
- goods (30)
- government (639)
- haiku (16)
- hardware (111)
- hatena (338)
- headphone (171)
- health (876)
- history (710)
- hoge (89)
- iOS (138)
- iPad (33)
- iPhone (611)
- iPod (200)
- iTunes (66)
- illustration (44)
- image (86)
- influenza (53)
- instagram (50)
- intelligence (22)
- interior (16)
- interview (297)
- job (280)
- journalism (506)
- keyboard (59)
- language (89)
- law (1161)
- lens (84)
- library (20)
- license (14)
- life (1247)
- literature (21)
- live (30)
- mail (94)
- map (341)
- material (28)
- mathematics (118)
- meal (847)
- media (954)
- medical (603)
- medicine (71)
- middleeast (86)
- military (240)
- mixi (53)
- mobile (1441)
- model (44)
- money (417)
- motor (336)
- mouse (34)
- movie (957)
- music (955)
- nasne (16)
- nature (73)
- net (1669)
- neta (3259)
- news (62)
- nicovideo (39)
- novel (86)
- nuclear (89)
- office (23)
- okuhanako (21)
- oldmedia (31)
- p2p (85)
- patent (56)
- philosophy (24)
- photo (1202)
- physics (72)
- planet (33)
- politics (810)
- povo (17)
- privacy (373)
- programming (609)
- publication (132)
- publiccomment (39)
- railway (105)
- rakuten (34)
- reading (30)
- religion (178)
- review (305)
- robot (231)
- rocket (137)
- rss (32)
- rumor (81)
- sale (52)
- satellite (74)
- science (1815)
- search (214)
- security (1855)
- service (807)
- shop (64)
- sightseeing (26)
- society (475)
- software (587)
- space (899)
- spaceshuttle (45)
- spam (38)
- sports (53)
- spot (33)
- standard (118)
- stationery (106)
- storage (64)
- story (14)
- streetview (53)
- study (134)
- stupid (14)
- suica (34)
- summerwars (14)
- tablet (20)
- talk (81)
- technology (2139)
- terror (92)
- tips (511)
- tokikake (69)
- tool (195)
- toy (53)
- traffic (100)
- train (99)
- travel (156)
- trekking (42)
- trouble (431)
- usability (19)
- ustream (19)
- vaio (38)
- video (33)
- vocaloid (46)
- war (234)
- watch (18)
- weapon (49)
- wear (21)
- weather (149)
- web (947)
- wellcare (17)
- wikipedia (34)
- willcom (25)
- winny (52)
- wireless (98)
- wisdom_of_crowds (14)
- woman (27)
- word (124)
- work (331)
- world (211)
- writing (76)
- α55 (21)
- あかつき (20)
- かぐや (75)
- ここはどこでしょう (14)
- はやぶさ (120)
- はやぶさ2 (20)
- べつやくれい (17)
- アトピー (17)
- ウクライナ (35)
- エボラ出血熱 (16)
- カメラバカにつける薬 (26)
- カーリング (266)
- ガルパン (30)
- サカナクション (37)
- シン・ウルトラマン (16)
- シン・ゴジラ (39)
- ジブリ (23)
- ゼルダの伝説 (23)
- ゼルダの伝説BotW (39)
- タバコ (15)
- ダム (20)
- ドローン (18)
- パシフィック・リム (14)
- ブレードランナー (22)
- マイナンバー (20)
- マイナンバーカード (43)
- ヤマト運輸 (23)
- ロシア (16)
- ワクチン (64)
- 中部電力 (16)
- 京急 (15)
- 人とロボットの秘密 (20)
- 元号 (22)
- 北朝鮮 (25)
- 原発 (38)
- 図書館 (31)
- 地震 (106)
- 大山顕 (45)
- 大童澄瞳 (15)
- 家電 (99)
- 工作 (27)
- 広告 (18)
- 庵野秀明 (22)
- 建築 (24)
- 掃除機 (14)
- 新幹線 (36)
- 映像研には手を出すな (30)
- 有機EL (15)
- 東京オリンピック (31)
- 東京都 (35)
- 東日本大震災 (128)
- 林雄司 (15)
- 機械学習 (19)
- 民主党 (94)
- 江ノ島茂道 (14)
- 海賊版サイト (32)
- 漫画村 (14)
- 災害 (33)
- 炎上 (18)
- 生成AI (21)
- 睡眠 (31)
- 育児 (36)
- 自動運転 (35)
- 芸能 (18)
- 街歩き (29)
- 西浦博 (17)
- 訃報 (63)
- 豆 (37)
- 酒 (21)
- 量子コンピュータ (21)
- 防災 (57)
- 電力 (45)
- 電子書籍 (100)
- 風立ちぬ (16)
- 香港 (25)
- neta (3259)
- technology (2139)
- business (1942)
- Google (1864)
- security (1855)
- science (1815)
- net (1669)
- mobile (1441)
- gadget (1423)
- copyright (1331)
Japanとsearchに関するume-yのブックマーク (9)
-
 ume-y 2007/10/04
ume-y 2007/10/04- search
- technology
- Japan
リンク -
日本が目指す「Google対抗エンジン」は成功するか? | WIRED VISION
日本が目指す「Google対抗エンジン」は成功するか? 2007年9月 7日 IT コメント: トラックバック (0) Adario Strange 2007年09月07日 米Google社が検索市場を支配していることに、極東の隣人である日本人たちは恐れを抱いている。 日本のハイテク企業が集まって、Google社に対抗するための新しいコンソーシアムを立ち上げたのはそのためだ。 ネット版『Financial Times』紙の報道によると、このコンソーシアムはおよそ1億3000万ドルの予算をプロジェクトのために計上しており、NTTデータ、トヨタIT開発センター、トヨタマップマスター、NEC、日立製作所、ソニーコンピュータサイエンス研究所などの企業が加わって、さまざまな検索コンポーネントの開発に取り組むという。 しかし、この計画には大きな問題が1つある――それは、日本のハイテク業界自体が抱える問
-
Google,Yahoo!でむりやり日本語検索をする - MediaLab Love Chapter 2
GoogleやYahoo!には日本語のページに絞って検索をする機能がありますが、なぜか日本語のページでないものも引っかかることがあります。*1特に、英単語のみで検索した場合はこの様なことが頻繁に起こります。日本語のページを探しているのにもかかわらず、このようなことがおきると非常に不便ですので、私は次の対策を考えました。 日本語のページだけを検索結果に出したいのであれば、日本語でしか使われない文字を検索単語に含めればよいのです。私の場合は、ひらがな、カタカナをOR条件でひっくるめた検索単語を追加しました。つまり、検索単語が scandinavia だとすると、 scandinavia い or の or て or か or な...(検索クエリ数の限界まで) となります。 ここで追加した文字は 漢直ノート 個人による1-gramの差と「雑記/えもじならべあそび」の文字頻度 - 雑記/えもじな
-
Google、大規模日本語データの公開を検討 | スラド IT
3/20の言語処理学会内にて、Googleが主催する大規模日本語データ公開に関する特別セッションというのがあるらしい。Googleでは、日本語の言語処理研究推進のため大規模日本語データの公開を検討しており、その仕様を決定するために現場の研究者/技術者の皆様の声を吸い上げたいということのようだ。 ここで思い出したが、つい先日にYahoo! Japanが Yahoo!知恵袋のデータを情報関連技術研究コミュニティに対して無償で提供するというニュースがあった。 この時は、書き言葉と話し言葉の中間的存在としてブログやQ&Aサイトなどのテキスト情報が急増しており、これを研究対象として利用できることで研究の幅が広がるということだったが、Googleのデータも非常に多様かつ巨大な情報の塊を研究対象にできるというのは意義のあることだと思う。これを使って、どんな研究ができるだろう?
-
「検索技術はGoogleより上」――FASTが日本市場に攻勢
「『検索技術はGoogleより上』という信念でやってきた」――企業向け検索システムを手掛けるノルウェーFAST Search&Transfer日本法人の徳末哲一社長は、同社の検索技術への自信をこう表現する。検索技術を適用できる分野は今後広がるとし、「検索は、何かとんでもないことが起きる時期に来ている」と語る。 FASTはノルウェーのオスロに本社を置く検索企業。ノルウェー工科大学の技術開発の成果をもとに、1997年に設立された。Googleのようなロボット検索ポータル「alltheweb.com」開発でノウハウを蓄積。allthewebは2003年にOvertureに売却し、エンタープライズ検索一本に絞って成長してきた。 日本国内へは、2002年に日本アイ・ビー・エム(IBM)と提携して本格参入した。「楽天市場」の商品検索システムを構築したほか、日産自動車や日立製作所、ヨドバシカメラ、リクル

-
著作権法改正へ--検索事業者のデータ利用、著作権の許諾なしでも可能に - CNET Japan
政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍首相)はこのほど、著作権法改正に向けた改正法案の作成する方針を固めた。5〜6月をメドに「知的財産推進計画2007」を取りまとめ、政府として著作権法改正の骨組みを提示する。 今回の方針は、知的財産戦略本部下に設置されたコンテンツ専門調査会内で、2006年9月から検討を開始。毎月開催される会合では、現行の著作権法と現在のネット社会における問題点や矛盾点の議論が続けられてきた。 現行法では、著作物のキーワードや索引の編集・利用の際には、著作権者の許諾が必要で、ネットの検索サービスでは、データを蓄積する検索サーバを国内に設置することができない。一方、米国の著作権法は公正な利用なら著作権侵害にあたらないと認めており、GoogleやYahooなどのネット検索事業者の日本法人は、検索サーバを海外に設置するなどし、日本の著作権法の適用を回避している。 これに対し、今回の

-
「Google対抗ではない」--元担当者が語る情報大航海プロジェクトの真実
ネットビジネスに携わる企業が一同に介し、最新動向を紹介するイベント「JANES Way Episode2」が11月15日に開催された。経済産業省や企業、大学などの38団体が、画像や動画の検索・解析ができる国産エンジンの開発を進める「情報大航海プロジェクト」の元担当者が登壇し、プロジェクトの方向を語った。 2006年10月まで経済産業省で情報大航海プロジェクトを担当していた内閣官房参事官補佐の鈴木英敬氏は、「マスコミには、Googleに対抗してキーワード検索エンジンを、政府が主導し、税金を投入して開発すると言われているがそれは大きな誤解」と語り、情報大航海プロジェクトの目的を説明した。 鈴木氏はプロジェクトについて「検索エンジンを作ろうとはまったく思っていない」と説明する。「現在、キーワード検索といえばインターネット上にあるテキストの検索にとどまっている」と指摘した上で、情報大航海プロジェク

-
-
国産でGoogle越えを狙う情報大航海プロジェクトコンソーシアム発足 | スラド IT
ストーリー by yoosee 2006年08月01日 17時09分 果たしてGoogleは52の組織が共同で作っただろうか… 部門より JonMoo曰く、"今年に入って「国産Google」の掛け声で各所で報じられてきた 情報大航海プロジェクトコンソーシアムが正式に発足した。 記事によれば、31日に第1回総会を開催して規約の承認と 会長に東京大学生産技術研究所の喜連川優教授を選任したとのこと。 現在は52の組織(個人を含む)が参加しているとのことだが、 6月のCNetの記事では38団体となっているので若干増えているようだ。 まだ何も見えてない段階ではあるが、 経済産業省の担当者インタビューを読んでも特に Googleを越えるような感じは見えてこない。 同様の国策Googleの試みにはEUの Quaeroがあるが、日本の予算はQuaeroの400億円規模にかなり及ばない と思われる。 ちょっ
-
 1
1
公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く