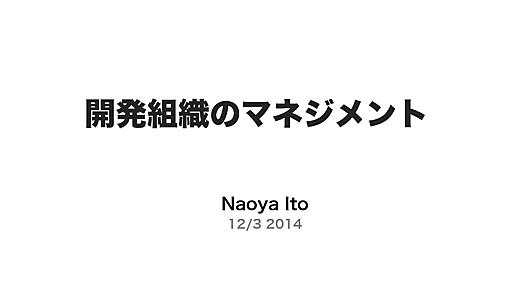数ヶ月前に「ジョブ型組織」と「メンバシップ型組織」の違いについて考える機会があり、Twitterに呟いていた。その流れでスクウェア・エニックス時代のことをいつかnoteの記事にまとめようかなどと呟いたらスクウェア・エニックスの時田貴司さんからも「楽しみにしてます」とリプを頂けたので時間ができた今、マガジン「ゲームデザイナーの仕事」の番外編として書くことにした。まず、最初に断っておきたいことがある。私はスクウェア・エニックスに2005年7月から2008年3月までの間、「プランナー」という肩書きで在籍していた。契約形態は、2005年7月から2007年3月までアルバイトで、2007年4月から2008年3月まで契約社員であった。所属プロジェクトは、2005年7月から9月までは研修生という扱い、2005年10月から2007年12月までは「ファイナルファンタジーXI」、2008年1月から3月まで「小さ