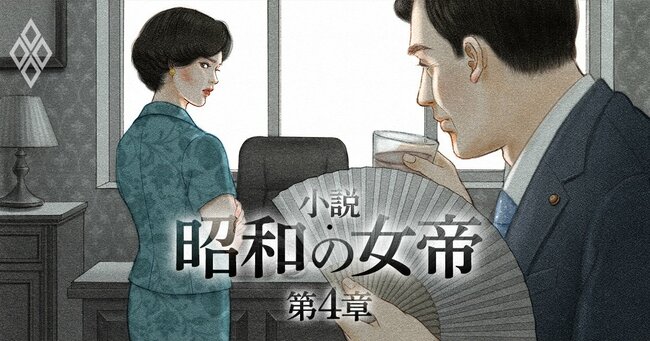写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
高額療養費の制度改正により、自己負担限度額が段階的に引き上げられることになった。『医療費の裏ワザと落とし穴』292回では、70歳以上の人の改正のポイントを徹底解説する。これまでは優遇されてきた高齢者の医療費負担は、どのように変わるのか。(フリーライター 早川幸子)
高齢者優遇の社会保障から
全世代型の社会保障への転換
前回(第291回)の本コラム(治療が続けられない…「高額療養費」制度見直しで自己負担限度額はこんなに増える!【70歳未満・所得区分ごとに試算】)では、25年8月から段階的に行われる「高額療養費」の制度改正のうち、「70歳未満」の人の引き上げ内容について解説した。
高額療養費は、医療費が家計の大きな負担にならないようにするために、1カ月に患者が支払う医療費の自己負担分に上限を設けた制度だ。通常の自己負担割合(年齢や所得に応じて1~3割)を支払うのは医療費が一定額までで、その上限額を超えた部分の医療費については負担が軽減される仕組みになっている。
この自己負担限度額は、「70歳未満」と「70歳以上」では異なる金額が設定されており、以前は高齢者の負担はかなり優遇されていた。だが、全世代型の社会保障制度への改革が進む中で、高齢者にも容赦ない負担増となってきている。
今回は、25年8月から引き上げ予定の高額療養費について、「70歳以上」の人の自己負担限度額の見直し内容について、詳しく見ていきたい。
ひと昔前までの日本の社会保障は、給付を受けるのは高齢者が中心で、負担は現役世代に頼るという構造になっていた。人口構造がピラミッド型で、労働力人口が豊富な時代はそれでも大きな問題はなかった。
だが、日本は世界に類例のない超高齢社会となっている。24年の高齢化率(人口に占める65歳以上の人の割合)は29.3%で過去最高を更新した。さらに、今年は団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者になり、医療や介護などの社会保障費が増大する「25年問題」が現実のものとなる。
そのため、世代間でも、同世代の間でも、負担と給付の公平が担保されるような「全世代型の社会保障」への改革が進められてきた。つまり、高齢者を一律に優遇するのではなく、年齢に関係なく経済的な負担能力に合わせた構造に作り変えることになったのだ。高額療養費も、この改革項目のひとつに挙げられており、これまでも段階的な見直しが行われてきた。