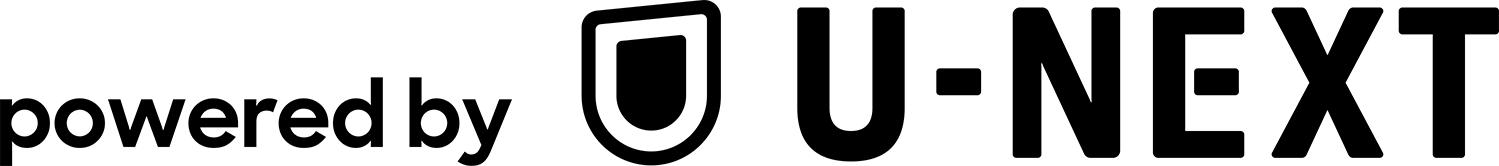大九明子監督作品は初めて。目下ブレイク中の河合優実を、ちょい役じゃなく本格的に観たのも初めて。またジャルジャル福徳さんの原作は未読。ジャルジャルのコントもほとんど見たことがないので、福徳さんの言葉づかいのクセなどから本作のセリフ回しを推し量ることもできない。
そんなお初づくしの本作に、どこか青山真治作品に相通ずる匂いを嗅ぎ取ったといったらまったくの的外れになるだろうか。実際、映画のスタイルなどまるで違うのだけれど。
本作を観ながら、大学生の三浦春馬、幼馴染の榮倉奈々、義理の姉である小西真奈美、亡き親友で幽霊の染谷将太らが一見風変わりな物語を繰り広げる青山監督の『東京公園』をぼんやり思い出したりしていたのは、本作の登場キャラクターにも、この青山作品に通底する「なにか」が感じられたからだ。
はた目には「独りよがり」「こじらせ系」といったコトバで片付けられそうな本作の主人公たち(萩原利久と河合優実)も、『東京公園』の作中人物と同じく、若くして心の裡になにがしかの喪失感や不在感を抱えていたり、「自分の中の他人」を扱いあぐねているようにみえたのだ。そこがまた共感ポイントでもある。
本作でもう一つ印象的だったのは、『ボーン』シリーズでお馴染みポール・グリーングラス作品のような“激しい”カメラワークだ。
特にそれは萩原利久、河合優実、伊東蒼それぞれの独白シーンで顕著になる。手持ちカメラのショット、不意なズームアップなどで対象を捉え、まるで激しいアクションシーンのように長台詞をカット割りで刻む。その結果、溢れる想いの告白現場を覗き見ているような臨場感が立ち上がってくるのだが、同時に気恥ずかしさも覚えてしまった…。
そのほか全体的な印象でいうと、「セレンディピティが多すぎやしない?」とか「名ゼリフ、金言、言葉あそびのオンパレードが出来すぎでしょ」とか「アノ位牌の前で大型犬のようにじゃれ回るのはあかんやろ」とか、おおむね原作由来と思われる「難点」の数々(原作未読のため勝手な憶測だが)を、大九監督は力技で寄り切ったという感じだろうか。とはいえ上映時間127分はさすがに少し長いなとは思った(ことに終盤など)。
出演者たちに目をやると、多くの人も指摘するとおり、さっちゃん役を演じる伊東蒼が圧巻のひとこと。冒頭シーンの学生バンドで歌うメガネ女子の姿によって、さりげなく、しかし決定的に印象づけてからのあの展開、この展開には、ホント胸張り裂けそうになった(余談だが、彼女は若い頃の池脇千鶴にうっすら似ている)。
そんな彼女の一人勝ち(役得もあろうが)によって、割を食ったのは河合優実だろう。立ち姿の「普通っぽさ」などさすがに見事だが、映画前半の「こじらせ系女子」のイメージが後を引き、心の隅でバイアスをかけて見てしまう。のちに主人公が憶測する彼女の悪しき言動だって“必要”以上にハマりすぎな感が否めない。裏を返せば、それは演技力の証なのだろうが…。このあたり演出のさじ加減が問われるところだろう。
ついでに言うと、彼女は「目尻の皺」より唇の方がはるかに魅力的だと思うので、終盤の主人公の台詞としぐさにはちょっとナットクいかない(笑)。それと最近、旧作邦画をよく観るせいか、河合優実は若い頃の長門裕之に似ているなと思った。
一方、思わぬ伏兵だったのが、ヘンテコメニューをズラリと並べた喫茶店(カフェにあらず)のマスター役に扮した安斎肇。ろくに演技らしい演技もしてないのだが(笑)、絶妙な間合いとフシギな存在感で場をさらう。
映画ファン的には、伊東蒼が夢の中で作り笑いをする仕草(『散り行く花』)や萩原利久の強烈な寝ぐせ(『メリーに首ったけ』)など万人がピンとくるだろう。個人的には、足を引きずりながら坂道を走る主人公のイタさに、根岸吉太郎監督作『狂った果実』のラストシーンを思い浮べた(ちなみに同作はニガテ)。
また、ドビュッシー作曲「月の光」を使った映画は数々あるが、本作のラスト・シークエンスにギターで奏でられるそれは、家族の解体と再生を描いた黒沢清監督の『トウキョウソナタ』のラストシーンを思い出させ、じんわり胸が熱くなった。










 あんのこと
あんのこと ナミビアの砂漠
ナミビアの砂漠 朽ちないサクラ
朽ちないサクラ 由宇子の天秤
由宇子の天秤 牛首村
牛首村 少女は卒業しない
少女は卒業しない 劇場版 美しい彼〜eternal〜
劇場版 美しい彼〜eternal〜 左様なら今晩は
左様なら今晩は 高崎グラフィティ。
高崎グラフィティ。 恐怖人形
恐怖人形