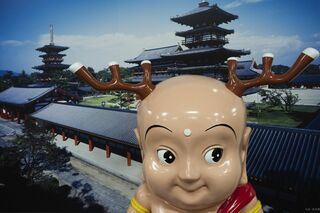人の手が入り始めた「みんなの森」
人の手が入り始めた「みんなの森」
人の手が入らなくなったことで、全国各地にあるスギやヒノキの人工林は荒廃している。三重県尾鷲市の「みんなの森」もそんな人工林の一つだったが、現在進行形で生物多様性を回復させるプロジェクトが進んでいる。「みんなの森」プロジェクトはなぜ生まれたのか。プロジェクトを主導するLocal Coopとは何か?(篠原匡:編集者・ジャーナリスト)
◎第1話:荒れた人工林を復活させる!三重県尾鷲市「みんなの森」で進行中の生物多様性回復プロジェクトとは?
第1話で触れたように、Local Coopとは、自治体の役割を補完するという目的の下、Next Commons Lab(NCL)の代表理事を務める林篤志が中心となって生み出した概念でありプロジェクトである。一言で言えば、住民自身による自治をベースに、地域やコミュニティを再設計しようとする取り組みだ。
公共サービスは自治体が担ってきたが、人口減少社会に突入した今、自治体だけでは手が回らなくなりつつある。住民が主体的に参加する場を作り、地域の課題解決や自分たちの暮らしの改善につなげる。そんな行政を補完するためのプラットフォームと位置付けられている。
もっとも、この行政のサブシステムという機能は、Local Coopの一面を表しているに過ぎない。
だいぶ大きな話になるが、NCLと林がLocal Coopを通して実現しようとしているのは、「コモンズ」の再生や再定義によるポスト資本主義社会の具現化だ。
本来、森や海のような自然はみなが共有すべき社会の共通資本だが、市場主義経済をドライバーとする今の資本主義の中で、森や海が持つ本来の価値はほとんど顧みられることなく放置されてきた。経済学で言う、負の外部性である。
それは、地域コミュニティに根ざしたローカルコモンズでも同様だ。