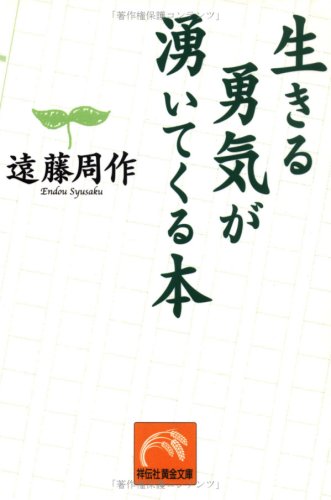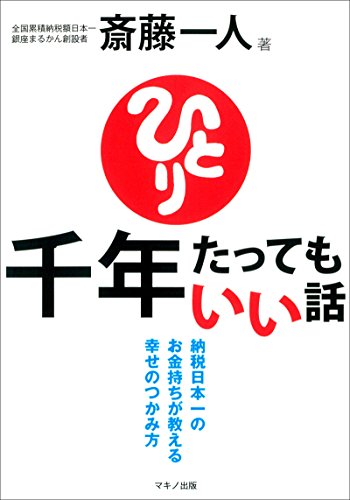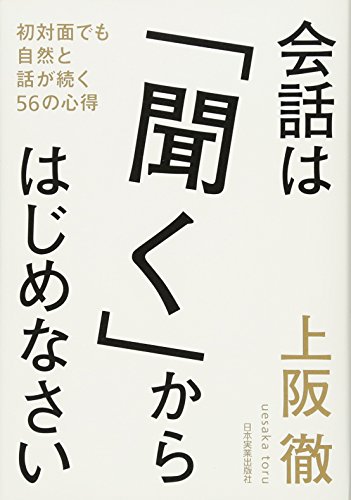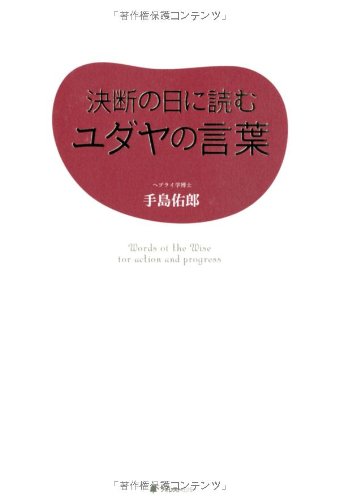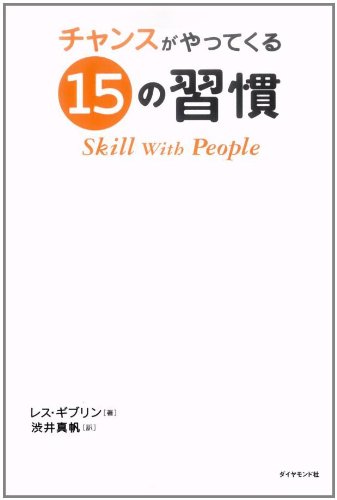人だけでなくモノにも感謝の心を
人間以外にも、例えば植物に心は通じるものでしょうか?
科学的にどうなのかはさて置き、良い言葉や良い心は良い環境を作っていくというのはあるかと思います。

以下は遠藤周作さんの書籍より引用です。
最近、ある本を読んだ。
トムプキンズとバードという人の共著『植物の神秘生活』(工作舎刊)という本である。
本にはびっくりするような話が書いてあった。
米国のうそ発見機検査官であるバックスターという男が出来心で、発見機の電極を竜血樹(ドラセナ)という植物につけてみた。
すると驚いたことに竜血樹はどうやらバックスターの心の動きがわかるようなのである。
好奇心にかられたバックスターはそれを確かめるため、この樹の一枚の葉を焼こうと考え、心に炎の燃える光景を思いえがいた。
瞬間、竜血樹につけた機械の針ははげしく動き始めたのである。
樹は人間と同じようにおびえたのだ。
彼の報告を読んだ人たちのなかには同じ実験を試みる者が次々と出てきた。
ヴォーゲルという人は実験の結果、植物が人間から葉をちぎられる時、どんな不安を持つか、またそういう人間の心ない気持ちにどういう反応を示すかを立証した。
彼の女友だちのウイリーはユキノシタの葉を二枚つんで、ひとつを枕元のテーブルにおき、毎朝、生きつづけるよう念じ、他の葉には関心を払わなかった。
すると枕元のテーブルの葉はもうひとつの葉が枯れてもイキイキとしていたという。
この本を読んでから、私は仕事に飽きると窓ぎわの植木鉢のそばによって、色々と話しかけては遊んでいる。
本に書いてあることが確かかどうか、私にはわからない。
しかし、本当に世の植物に人間の心が通じるなら、我々の世界はなんと心あたたまるすばらしいものに変わるだろう。
「きれいな花を咲かせてくれよ」と花や木に話しかけられるのはディズニー映画の空想だけではなかったのだ。
『生きる勇気が湧いてくる本』祥伝社黄金文庫
人だけでなく、あらゆるものに心が通じると考えるのは素敵なことかもしれません。
例えば自分の愛車に名前をつけるだけでとても愛着がわき、まるで相棒のように洗車するのも愉しくなったりしますし、つい話しかけたくなっちゃいます。
他にもスマホに名前を付けておけば、置き忘れなんて起こらない気もしますね!
また、そのように自分の持ち物や日々の暮らしの中にあるもの、一つひとつに対して感謝の心を持てる人はとても魅力的に見えますよね。
相田みつをさんの名言
『しあわせはいつも
じぶんのこころがきめる』
あなたの毎日がワクワクに溢れますように。
自分の強みを伸ばそう!
ついつい、自分の欠点にばかり目がいってしまい、強みを伸ばすよりも足りない事に注力しがちになります。

もちろん欠点を補うことや、基本を身につけることは大切ですが、強みに目を向けることも忘れずにいたいものです。
以下、タル・ベン・シャハーさんの書籍より、わかりやすい例え話を引用させていただきます。
ドナルド・クリフトンとポーラ・ネルソンによる著書『強みを活かせ!』には、動物の子どもたちをバランスよく成長させることを目指している森の学校の話が出てきます。
最初の日、子ウサギが学校に行くと、ランニングとジャンプの授業を受けることになりました。
子ウサギはこの科目が大好きでした。
子ウサギは学校から帰ったあとも興奮さめやらぬ様子で、翌日学校に行くのが待ち遠しくてしかたありませんでした。
2日目、学校へ行くと、授業は空を飛ぶことと水泳でした。子ウサギはそのふたつが全然できなくて、学校が大嫌いになりました。
子ウサギはすっかり落ち込み、しょんぼりと家に帰りました。
家で子ウサギが学校をやめたいと話すと両親は、「学校へは行かなくてはいけないよ。まんべんなく何でもできて初めて、将来成功することができるんだ」と取りあってくれません。
次の日、子ウサギが学校へ行くと、今度は空を飛ぶ授業と水泳の補習を受けることになりました。子ウサギはその能力が足りていなかったからです。
一方、ランニングとジャンプの授業は取りやめになりました。
こちらの科目はよくできているから、それ以上の練習は必要ないとされたのです。
これはたとえ話ですが、残念ながらこれに似たようなことが学校から企業までのほとんどの組織で、実際に行われています。たしかに弱い部分を無視するべきではありません。
私たちは社会で暮らしていくために、基本的な計算や読み書きも学び、仕事に必要なスキルを習得する必要があります。
しかし同時に自分の強みも無視することなく、才能や能力を育てるために最大限の力を注ぐべきです。
『次の2つから生きたい人生を選びなさい ハーバードの人生を変える授業2』大和書房
人はだれしも本来凸凹があって、自分の凸部分は足りない人の力になり、逆に自分の凹部分は相手に補ってもらうことでチームとして成果に繋げていけるはずですよね。
ちなみに自分の強みに気がつけないという、別の悩みがある時は、「ストレングスファインダー」のテストを受けてみることもオススメです。
自分の知らなかった強みと出会えるかもしれません。
なるべくなら自分の足りない部分や欠点に囚われすぎず、自分の強みに目を向けていきたいものですね。
ピーター・ドラッカーさんの名言
『あらゆる者が強みによって報酬を手にする。
弱みによって、人は何かを成し遂げることはできない』
あなたの毎日がワクワクに溢れますように。
反論の前に「私、ちょっと変わってますから」を入れておく
お客さんや関係性が深くない人と話す際には、特に宗教や政治、野球の話をするのはNGと昔から言われています。

自分が正しいと思っていることと、相手の意見の相違があった際にも「自分の方が正しい」をぶつけるのは注意が必要と斎藤一人さんは言います。
自分が正しいと思ったときは正しいっていっちゃだめだよ。
よく覚えておきなよ。
自分が絶対、これ、正しいってなったとき、「私が正しいんです」
っていうと必ず喧嘩になるからね。
そういうときは必ず、
「自分は少し変わってますから。
私、変ですから、こういう考えもあるけど気にしないでください」っていわないと、その前にいろんなこと、いってた人から全部、反感買うからね。
で、精神論って喧嘩しないことだよ。
敵を作らないっていうのが精神論だよ。
だから、精神論で喧嘩してるやつ、おかしいんだよ。
宗教同士で喧嘩してるとかっていうのはね、「右のほおを打たれりゃ、左のほっを出しなさい」とかいいながら、宗教家ってすぐ喧嘩するんだよ(笑)。
ここでいろんなこと聞くとね、普通の人より頭、よくなっちゃうから、頭よくなったら、頭いいふりしちゃ、だめなの。「私、少し変ですから」
っていわないとね、だめだからね(笑)
だから、精神論でさ、もめたらばかばかしいからね。もめないことです。
『千年たってもいい話』マキノ出版
たとえ自分が正しいと思っていても、一言「私は少し変ですから」と付け加えるのも優しさですね!(笑)
特に精神論的なもの、価値観などは捉え方で違うのでそれに対して相手を説得し合うのは得策ではないようです。
余計な揉め事に巻き込まない、巻き込まれないのも自分自身の機嫌を良くしていくためにも大切ですね!
ジョン・F・ケネディさんの名言
『互いに相違点があることは認めよう。
たとえ今すぐ相違点を克服できないにしても、少なくとも多様性を認められるような世界を作る努力はできるはずだ』
あなたの毎日がワクワクに溢れますように。
内にあるアイデアを引き出すのは質問される事
会話というのはとても大切ですね。
なかでも話を聞くことは、相手にとっても重要でアイデアを生み出す際、頭の中にあるものを引っ張りだすきっかけになると言います。

以下は上阪徹さんの書籍よりそのエピソードです。
あるアーティストの方へのインタビューでした。
芸術分野で多大な実績を残している方。
そういう人たちはアトリエにこもってウンウンとうなりながら作品をつくり上げてくものとばかり私は思っていたのです。
ところが、出てきたのは意外な話でした。
アイデアは、複数のスタッフや関係者で、ワイワイいろいろな話をしたり、質問をしたりしながら考えていくというのです。
なぜですか、という私の問いに、アーティストの方は極めて明快に答えてくださいました。
優れたアイデアは人間の脳の奥底に間違いなく眠っている。
それは、アトリエで一人でウンウンうなっていても、出てくるものではない。
ところが、誰かとコミュニケーションを交わしていると、思わぬ形でひょんとそれが外に出てくることがある。
自分一人では取り出すことができないアイデアや記憶、発想を、頭の中から引っ張り出してくるためにも、誰かに何かを聞いてもらったりして刺激を与えることが欠かせないことなのだと。
相手の脳の奥底に潜んでいるものを引っ張り出すと言う意味でも、相手に質問を繰り出し、いろいろな角度から話を聞いて、刺激していくことは大いなるプラスになるということ。
聞かれて話すことは、思わぬ仕事の成果を生み出す可能性も秘めているのです。
『会話は「聞く」からはじめなさい』日本実業出版社
リモートワークや会議の減少などで直接会話することが減っているだけでなく、会話やコミュニケーションが減っている場合も多いかもしれません。
「日々の雑談も大切」との考えもありますし、話を聞くことで役に立てることもたくさんあるということは覚えておきたいところですね!
三木谷浩史さんの名言
『楽天を始めたころ、私が思ったのは「最大のコンテンツはコミュニケーションだ」ということでした』
あなたの毎日がワクワクに溢れますように。
『始めたということは、すでに全体の半分以上まで来ているのだよ』
何かを始めたけど続かないとか、3日坊主になった経験がある人は多いと思います。
辞めてしまう理由は様々ですが、「もう諦めそう」と言う時に思い出したいのは、「それを【始めた】という事実自体が素晴らしいのだ」という事かもしれません。

以下、寺島佑郎さんの書籍より引用です。
十五世紀のユダヤの賢人イツハク・アラマは、スペインのサモラに生まれ、そこでユダヤ教学院の最初の院長になった人です。
彼を募ってスペイン全土から多くの学生が集まってきました。
しかし新入生は学院長アラマの講義について行くのは大変でした。
すぐに学問をあきらめようとする若者が続出します。
そのたびに彼は学生に声をかけました。
「始めたということは、すでに全体の半分以上まで来ているのだよ。
もう少し辛抱して続ければ、きっと講義にもついて行けるし、発見もたくさん出てくるよ。」
じっさいその通りなのです。
多くの人は、後一歩でゴールに到達するとか、またはゴール圏に入るのに、その前でギブアップして、みすみす成功を失うのです。
さあ、あなたも気を取り直して、また続けましょう。
7日間続けたら、もう7日間さらに続けてみるのです。
そうすると、さらに続けられるはずです。
成長は階段を登るように、段々と積み重なっていくと思いがちですが、実は成長には踊り場があると言います。
途中成長が感じられず、むしろ退化しているとさえ感じることも。
でも、その踊り場を乗り越えた先には、その時にしか見えない新しい景色も待っているはず。
そう信じて続けることは成長には不可欠なんでしょうね。
「始めたということは、全体の半分以上まできている」
これを心に刻んでおきたいものです。
稲盛和夫さんの名言
『いまこの1秒の集積が1日となり、その1日の積み重ねが1週間、1ヵ月、1年となって、 気がついたら、あれほど高く、手の届かないように見えた山頂に立っていた と、いうのが私たちの人生のありようなのです』
あなたの毎日がワクワクに溢れますように。
偏見に満ちた攻撃は【無効化】する
SNSがここまで広がったことで、一般の人も他人から否定されたり、偏見に満ちた発言を受けることがあるかもしれません。

そんな時、それを否定するよりも【無効化する】という方法もあるそうです。
その一例を明治大学教授、堀田秀吾さんの書籍より引用させていただきます。
以前、サッカーのキング・カズこと三浦知良さんが、現役を続けていることに対し、元プロ野球選手で野球評論家の張本薫さんから、某テレビ番組で「若い選手に席を譲らないと。団体競技だから、伸び盛りの若い選手が出られない。だから、もうお辞めなさい」などと言われたことがありました。
スポーツ選手の年齢に関する偏見が、もとになった発言です。
この発言を受けて、ネットもメディアも炎上しました。
しかし、キング・カズは、やはり役者が違います。
次のように返したのです。
「張本さんほどの方に言われるなんて光栄です。『もっと活躍しろ』って言われているんだなと。『これなら引退しなくていいって俺に言わせてみろ』ってことだと思う。張本氏の「侮辱」のことばを「激励」ととらえたのです。
これには、世間も当の張本さんも絶賛。
アスリートの先輩に対して顔を立てつつ、攻撃の無効化に成功しました。「反動蹴速迅砲【はんどうしゅうそくじんほう】」というのは、サッカーマンガ『キャプテン翼』の中で、ある登場人物が使う、相手のシュートをそのまま蹴り返すカウンターシュートのことです。
キング・カズの切り返しは、相手の攻撃を見事に返して点を取ったということで、まるで反動蹴速迅砲のようでした。
こういった無効化は、必ずしもすぐに効果があるとは限りませんし、空振りに終わることもあるでしょう。でも、そこであきらめてしまっては何も変わりません。
不毛に見えても、少しずつ上書きしていくことで、いつか認識が変わるときが来るかもしれない…。
そう信じて、意識的に偏見に立ち向かい、矯正しようとする姿勢も大切です。
『「勘違い」を科学的に使えば武器になる』秀和システム
一人ひとり人は皆違うもの。
ですから意見も違っているのは当然ですが、「相手が間違っている、そして自分は正しい」の主張の応酬では精神的にも参ってしまいます。
「相手の間違いの『間』が抜けない人は『間抜け』と呼ばれる」と言われます(笑)
「間違っている!」と相手も否定ばかりしているのではなく、ただ「違っているんだな」と淡々と受け入れる。それも大事です。
自分への意見も、それを否定するという方法以外にも、無効化するという考え方も身につけておきたいものですね!
池上彰さんの名言
『自分が賛成するような意見だけではなくて、自分が読んでいて不愉快な意見とか、自分の考え方とは違う意見にも接してみる』
あなたの毎日がワクワクに溢れますように。
笑顔の呪文「はい、チーズ」
悩み事や考え事していると、ふと自分の表情が険しくなっている事に気がつくことが良くあります。
そんなタイミングで人と会ったり、話したりすると、相手にとって印象は良くないものになってしまいますね。
せっかくなら、いつでも相手に良い印象をもっていただきたいもの。

そこでレス・ギブリンさんの書籍から、そのためのポイントを学ばせていただきたいと思います。
10人中9人までが会った瞬間にあなたを好きになってしまう…実はあなたには、そんな魔法の力が備わっています。
さらにあなたには、会った瞬間に相手を親切で友好的にする力まであるのです。
それは…
「会った瞬間に笑顔を向ける」
ことです。
その力を使うためには…
◇どんな人間関係も、最初の数秒でその後の雰囲気が決まってしまうことを頭に入れておきましょう。
◇人は、相手の態度を見て、それと同じように行動する傾向が強いという法則を利用しましょう。
会った瞬間に、挨拶よりも何よりも、まず目を合わせ、心からの笑顔を向けましょう。
さて、次に何が起こるでしょう?
相手もあなたと同じ行動を取るわけですから、あなたの笑顔に笑顔で返してきます。
しかもあなたの笑顔に迎えられて、気分もよくなっているはずです。
人と人とが関わるとき、そこには必ず雰囲気が生まれます。
この雰囲気は、あなたでも、相手でも、どちらでも作ることができます。
どうせなら、あなたの有利になるように、あなたが雰囲気を作りましょう。
あなたが太陽のようにあたたかく接すれば、相手も日光を返してきます。
けれども、北風を送れば、北風を返してくるのです。
ところで、この雰囲気作りは、タイミングが肝心です。
会ったら、何か言う前に、まず笑顔を向けるのがコツです。
それであたたかい友好的な雰囲気が生まれます。
また、声や表情はあなたの内心の情をあらわにしますから、声の調子や顔の表情も重要です。
人と会うときは、プロのモデルにならって、晴れやかな笑顔から始めることを常に忘れないでください。
そのためには、心の中でひとこと、呪文をつぶやけばいいのです。
「はい、チーズ」
これは効果抜群ですよ。
『チャンスがやってくる15の習慣』ダイヤモンド社
返報性の法則やミラーリング効果というのもありますが、何をおいても自分の機嫌を自分でとりつつ、目の前にいる人に対して笑顔で接する。それだけで嫌な印象を与えることはまずないはずですね!
眉間の皺をやめて「はい、チーズ」の呪文で笑顔でいられるようにしていきたいと思います!
竹田和平さんの名言
『わくわく生きるコツはニコニコにあり』
あなたの毎日がワクワクに溢れますように。