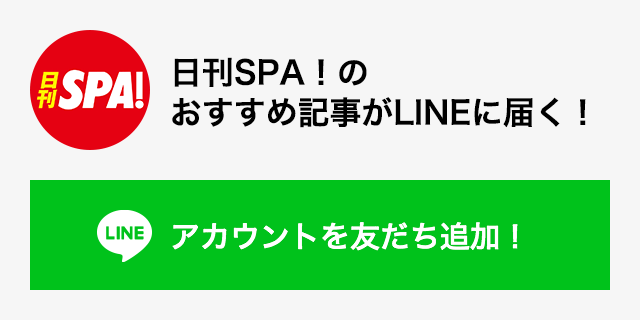冒険はしずかに始まる【押上駅 ・ 東京スカイツリー】/カツセマサヒコ
ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイがスタート。願いは今日も「すこしドラマになってくれ」
そのとき私は、死んだ目をしていた。
地上350メートル。墨田区にある東京スカイツリーの展望台は、人間の生っぽいニオイと熱で満ち満ちていた。
私のすぐ横にいるカップルは興奮気味に自撮りを連発していて、私はそのカメラに写り込まないように必死に上体を反らしながら、どうにか夜景を見ようとした。
しかし、窓に反射した自分の顔は干物のように疲れていて、一度でもそっちに意識が向いてしまうと、なかなか外の景色に焦点が合わない。
なぜこんな場所に、ひとりでいるのか。
あれはまだ、イチョウの葉が街を黄色く染めるより前。新橋の古い喫茶店で、この連載の担当編集者と初めての打ち合わせがあった。
緊張していた私は、頼まれてもいないのに自分の半生を語り始めた。ざっくり言うと、こんな内容だ。
私は、渋谷と吉祥寺を繫ぐ井の頭線沿いに生まれました。年を重ねるほど「都会の人だ」と言われることが増えて、ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がします。けれど、昔から街に対する好奇心が弱かったせいか、今でもひとりで知らない店に入ると、大量の汗が噴き出てしまうのです。さらに、この貧乏舌も厄介です。何を食べても美味く感じてしまうので、バーミヤンが美味い。松屋も美味い。チェーン店ばかりに逃げてきたから、「この辺り、いい店知ってます?」という日常会話がすこぶる怖い。そのことが、40歳も近くなった今になって、猛烈に恥ずかしいのです。
サブカルチャーの概念をさらに5回ほど捻じ曲げて具現化したら完成しそうな眼鏡をかけた編集者は、私の弱音をしずかに聞き終えた後、ティーカップを置いて言った。
「じゃあ、千本ノック、いってみましょうか」
千本ノック?
「普段なら入らないお店、行かない街に、あえて行ってみるんです。それで、恥ずかしくなったり億劫になったりしながら、少しずつ、東京に馴染む努力をしてみる。そういう連載は、どうですか?」
あのとき、「無理です」と即答すればよかったのに。
わずかに悩んだ末に、見切り発車で「やってみます」なんて言ってしまったものだから、絶望している今がある。
この展望台の下には、1400万の生活と人生があるという。この連載中に、そのうちのいくつかに触れることを考えるだけで、憂鬱だった。人と深く関わるのが面倒だから自営業を続けているくらいなのに、知らない街での出会いなんて、まっぴらごめんだ。しかもそれを、毎週繰り返すなんて。
ため息を吐き出すと、ふと隣から、すすり泣く声が聞こえた。
さっきまで自撮りが連発されていた場所で、ひとり泣いている女性の姿がある。
私はすぐに、思いを巡らす。
失恋か、友情の終わりか、仕事でクビになったとか。
そして考える。これは、エッセイのネタに使えないだろうか。たとえばこの後、彼女の元恋人が偶然やってきて、「どしたん?」と軽率に心配する展開になれば、今日の取材はそのドラマをオチにできるのに。
そんな妄想をしたところで、担当編集からメッセージが届いた。
「どうですか、人生初のスカイツリーは」
私は「もう帰りたいです」と打ってからすぐに消し、「順調です」とだけ返した。
暗くなったスマホの画面に、疲れた自分の顔が映る。せめて早く帰れるように、誰かすこしドラマになってくれ、とまだ見ぬ出会いに願った。
1986年、東京都生まれ。小説家。『明け方の若者たち』(幻冬舎)でデビュー。そのほか著書に『夜行秘密』(双葉社)、『ブルーマリッジ』(新潮社)、『わたしたちは、海』(光文社)などがある。好きなチェーン店は「味の民芸」「てんや」「珈琲館」
冒険はしずかに始まる【押上駅 ・ 東京スカイツリー】
【関連キーワードから記事を探す】