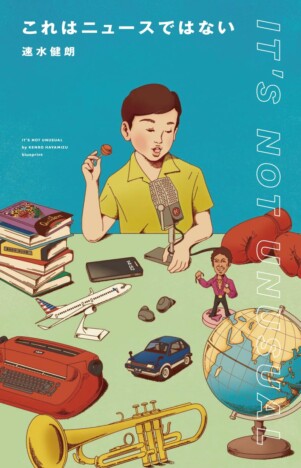古代朝鮮に倭の拠点はあったか? 歴史学者・仁藤敦史に聞く、古代東アジア史の一大争点「加耶/任那」の実態

『古事記』『日本書紀』を史料として扱うための方法論

――本書の中でも細かく検証されていましたが、『日本書紀』には信憑性に疑問符がつくような箇所も少なくないそうです。しかし、だからと言って史料として役に立たないというわけでもないのですよね。
仁藤:天地開闢や神々の話から始まるので、神話的なところはあるのですが、そこを強調して信憑性がまったくないのかというと、そんなことはありません。大正時代の歴史学者・津田左右吉が始めたいわゆる「記紀批判」――『古事記』『日本書紀』への批判の方法があるのですが、それは『古事記』『日本書紀』を史料として扱うための方法論です。怪しい話だからといって、それを全部捨ててしまうのではなく、外国史料や金石文、さらには考古学の発掘成果などとのクロスチェックをして、史実であろう箇所を注意深く腑分けしていくのです。本書も基本的に同じ方法論で史料を読み解いています。
――その手さばきと言いますか、それを通じて曖昧模糊としていた「加耶/任那」という国の輪郭が次第にはっきりしていくところが、本書の読みどころだと思います。その中でも中盤、「ヤマト朝廷の任那支配」の歴史的根拠とされる『日本書紀』の神功紀四九年条「加羅七国の平定」の記事は潤色であると判断しつつ、『日本書紀』の編者による「百済記」記事の年代移動を指摘していくあたりは、歴史ミステリを解き明かしていくような面白さがありました。
仁藤:ありがとうございます。ただ、その議論自体は、実は明治時代からあるものです。その基礎となる議論を「紀年論」というのですが、そもそもなぜ神武天皇の即位を紀元前660年に設定したのかを問うものです。推古天皇の頃、中国から新しい暦が入ってきたのですが、その暦では干支が一周する60年サイクルで、世の中が変革する年がくるとされているのです。さらに、そのサイクルが21回くるごとに大革命が起こるとされている。だから、60×21で、1260年ごとに大革命が起こる。つまり、推古天皇の頃から1260年さかのぼって設定されたのが、紀元前660年になるわけです。
――なるほど。
仁藤:それがまず、ひとつの定点になっています。そして、もうひとつの狙いが、神功皇后と卑弥呼を同一視させることだったのです。そのために、わざわざ中国史料を引用するなどして、「卑弥呼」プラス「台与(とよ)」イコール「神功皇后」という図式を、意図的に作ったようなところがある。で、その2点が決まると、そのあいだはアコーディオンのように伸び縮みすると言いますか、それによって120年生きた天皇が出てきてしまったり、いろいろと自由自在なところがあるのです。
――それによって「加耶/任那」に関する記述にも、年代的なズレが生じてしまったと。
仁藤:そうです。神功皇后のときに任那との関係ができたという風にしたいがために、記述を120年、ないし180年スライドさせている可能性が高いということです。
近代は都合の良いように歴史を利用している
――ここまでの話を聞いていて思いましたが、滅んでしまった国の歴史については、誰も責任を持たないようなところがありますよね。
仁藤:まさにその通りです。「加耶/任那」のように、それを継承する国がない場合は、そういったことが起こりがちなのですよね。『日本書紀』が引用している「百済三書」というのは、あくまでも百済の視点から見た「加耶/任那」の歴史です。滅ぼされる存在ではあっても、「加耶/任那」が主体となって語られることはありません。そこが歴史の悲劇です。たとえば、7世紀の終わりから10世紀の初めにかけて、「渤海」という国がありましたよね?
――現在の中国北東部から朝鮮半島北部、ロシアの沿岸地方にかけて存在したという国ですね。
仁藤:その国について今、中国と韓国のあいだで議論になっているようなのです。「渤海」という国も「加耶/任那」と同じように継承国がないのです。そのため、これまでは北朝鮮も含む朝鮮半島史の中で語られてきたところがあるのですが、最近中国が「渤海は中国の地方史である」と言い出しているようで。実際、朝鮮族という人たちが中国の満州あたりにいるので、その人たちの歴史と合わせて中国の地方史として考えるべきであると。ただ、その解釈はどうも現代政治と関わっているようです。もし仮に北朝鮮が崩壊した場合、韓国と中国のどっちに属するのかという問題ですね。歴史に政治が介入してくる側面というのは、今なお少なくありません。
――先ほどお話された「任那日本府」の話も、ちょっと似たようなところがありますよね。
仁藤:そうですね。近代以降、日本の場合は明治政府が古代史を利用しようとする側面がかなりありました。みなさんご存知の聖徳太子などは、まさに明治政府によって翻弄された人物だと思います。聖徳太子が推古天皇の摂政として外交を取り仕切ったみたいな話は教科書にも書いてあると思うのですが、そこで「摂政」ということが強調されるようになったのは、大正天皇の摂政になった裕仁――のちの昭和天皇の存在をクローズアップさせるためだったと言われています。先ほどの話と同じで、現在の状況を過去に投影することによって、正統性の根拠としたわけです。あと、日露戦争のあと明治政府は不平等条約の撤廃のため、小村寿太郎などが尽力するわけですが、過去にもそうやって大国を相手に堂々と渡り合った人がいたということで、聖徳太子が持ち上げられたところもあるようです。
――まさに山岸凉子の『日出処の天子』的なイメージですね。
仁藤:そうですね。近代は都合の良いように歴史を利用しているところがあり、任那日本府の話も、そういう性格が強いように思います。あと、もうひとつ付け加えるのであれば「出兵」を安易に考えていたところもあるようです。出兵して戦いに勝ったら、そこが領土化されるかのようなイメージですね。しかし、現実的に考えると兵站がもたないわけです。誰がどうやって現地で食料を調達するのか。兵站の部分を整備しないと軍隊など活動できないわけで。ましてや船といっても大型船がある時代ではなかったので、万単位の軍隊が海を渡るなんてことは絶対にありえない。663年の「白村江の戦い」で、ようやく万単位の動員ができるようになったのですが、その場合だって九州に拠点が必要だったわけで。戦いの局面だけではなく、そのバックグラウンドまで考えていくと、任那を領土的に10~20年占拠するみたいなことは、なかなか難しいと思うのです。
――出兵しても、全員が戻ってきたわけではなく、場合によっては、現地に居ついてしまう人もいたでしょうし。
仁藤:そうなんです。「任那日本府」の正体は、そういうことなのではないかというのが、実は本書の結論です。「任那日本府」というのは、ヤマト王権の出先機関などではなく、百済による加耶諸国への侵略に抵抗する勢力の総称だったのではないか。その内実は、倭からの使者、倭系の在地豪族集団を合わせたもので、そこに強固な組織は存在しなかった。向こうにいる2世、3世は必ずしも倭の臣下とはいえないわけです。そこが今回の本で強調したところでもあります。ハワイやブラジルに行った移民の2世、3世たちの全員が日本贔屓かというと、必ずしもそうではないじゃないですか。そもそも国籍でもって主義主張を割り切るという発想自体、国民国家的な考え方だと思います。
――古代史は他の時代と比べて不確定な要素が多く、政治に利用されることも多いように思います。それでもなお惹きつけられる古代史の魅力はどんなところにありますか?
仁藤:古代史には、都市や国家、戦争といった現代に繋がるもののルーツがあります。そこを明らかにしないと、現代の都市や国家、戦争の根っこも見えてこないでしょう。もちろん、産業革命以降、あるいは国民国家の成立以降、世界が大きく変わっていったところはあるのですが、そもそも国家とは何かを考える上で、やはり古代を抜きには語れないと思うのです。
■書籍情報
『加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか』
著者:仁藤敦史
価格:990円
出版社:中央公論新社
発売日:2024年10月21日
■関連情報
国立歴史民俗博物館
住所:千葉県佐倉市城内町117
入館料:総合展示 一般600円
休館日:原則として毎週月曜日、年末年始
※要HP確認 https://www.rekihaku.ac.jp
お問い合わせ(ハローダイヤル):050-5541-8600