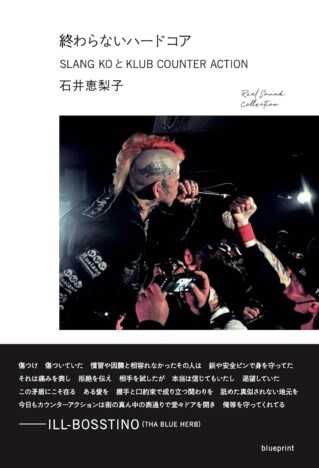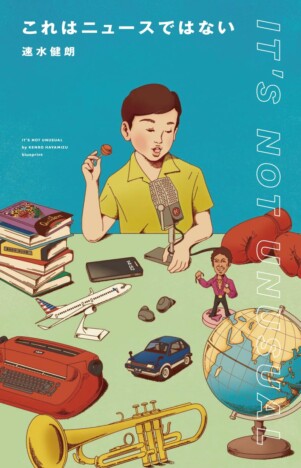『セプテンバー5』“報道人”の視点に限定した新しさ “未来への覚悟”も抱かせる力作に

1972年、当時は東西に分断されていたドイツの古都ミュンヘンで、第20回オリンピック競技大会が華々しく開催された。その会期真っ只中の9月5日未明、過激派組織「黒い九月」がイスラエル選手団の宿舎を急襲。マスク姿のテロリストが人質をとって籠城する姿は、全世界にTV中継された。各国に拘束されている同志約200名の釈放を求める犯人側と、ドイツ政府の交渉は決裂。最終的には空港で壮絶な銃撃戦が繰り広げられ、人質全員を含む計17名が死亡。オリンピック史上最悪の事件として、多くの人々の心に傷痕を残した……。
映画『セプテンバー5』は、その衝撃的事件を間近で報道し続けた米ABCスポーツのスタッフたちを描いた、実録ドラマの傑作である。そこには現代のメディアが抱える諸問題に直結する、さまざまな示唆が含まれている。同時に、手に汗握るサスペンス映画としても、驚くほどクオリティが高い。

現実に起きた事件をドキュメンタリータッチで描いた作品という点で、ポール・グリーングラス監督の『ユナイテッド93』(2006年)を即座に思い出す人も多いだろう。監督・脚本のティム・フェールバウム自身、同作からの影響を公言している。誰もが知る悲劇的結末に向かって、恐ろしいほどスリリングな群像劇が展開するという作品構造も似ているが、グリーングラスがひたすら「当事者」の視点にこだわったのに対し、『セプテンバー5』はあえて「報道人」の視点に限定することで、独自のテーマとメッセージを打ち出してみせた。そこに本作の映画としての新鮮さがある。
それまでスポーツ中継や選手への取材などをおこなってきたTVクルーが、ある日突然、テロ事件という非常事態に直面。マニュアルなしの手探り状態でリアルタイムの事件報道を試みる。その凄まじい緊迫感と臨場感を、『セプテンバー5』は全編にわたって見事に映像化している。そのスリルと生々しい空気感を、リアリティをもって表現するために、実に多彩な工夫が凝らされているのだ。
まず、選手村近くに設営されたABCスポーツ特設スタジオの緻密な再現。映画全体が主にこの建物内で進行するため、極めてリアルかつディテール豊かにセットが組み上げられている。スタジオや副調整室を埋め尽くす機材も、70年代当時の設備と同じものを極力かき集めて使用しており、なかには博物館から借りた貴重品まであるという。見るからに年代物の機械に囲まれ、タバコの煙が充満した副調整室の描写は、昭和世代のノスタルジーをもかき立てるかもしれない。

その日、生放送を指揮することになる若きプロデューサーのジェフリー・メイソンは、この副調整室から各所に指示を出し、情報収集や素材確保に四苦八苦しながら、綱渡りのような放送を続けていく。ジャーナリストとしての使命、社会人としてのモラルの間で揺れながら、ついには人命に関わる大失態まで犯してしまう彼の姿は、観ていて胃が締めつけられるようだ。監督のフェールバウムは、メイソンの顔を照らすTVモニターのフリッカー(明滅)の度合いまで、観客の心拍数をコントロールする効果的演出として活用したという。
この閉塞感満点の密室劇的シチュエーションがスリルを高めているのは間違いないが、かといって動きがないわけではない。副調整室、スタジオ、編集室、重役室などの場面転換がテンポよくおこなわれ、場面によってはフレキシブルに建物の外へとカメラが飛び出す。さらに、登場人物が行き交う廊下の撮り方もすこぶるうまい。「ドアを開ける」「ずんずん歩く」といった動作すらも躍動的かつ劇的な見せ場として成立させてしまう演出は、『ソーシャル・ネットワーク』(2010年)のデヴィッド・フィンチャーも想起させる。限定空間をいかにスリリングな劇的シチュエーションとして成立させるかという部分で、韓国映画『テロ,ライブ』(2013年)や、デンマーク映画『THE GUILTY ギルティ』(2018年)といった非ハリウッドの傑作群との共通性も感じずにいられない。