装甲車に操縦席複座型があるワケ 戦車は単座 狭い車内でなぜ操縦手を2名座らせるのか
およそ地上を走行する自動車で、複座といえば教習所の教習車くらいでしょう。戦車も複座はまずありません。ではなぜある種の装甲車に限って、複座がわりと普通に見られるのでしょうか。もちろん納得の理由アリ、です。
意外と小回りの利かない装輪式 乗用車と比べても…
対して装輪式の場合は、車輪の向きを変えることで方向転換します。
クルマの運転でも、Uターンするのにはそれなりの広さの場所が必要になり、たとえば小型乗用車トヨタ「ヴィッツ」の最小回転半径は4.5m、トヨタ「クラウン」になると5.3mとなっています。
これがより大きな装甲車ではどうなるのでしょうか。4×4(四輪駆動)の軽装甲機動車は約6.5m、ドイツの8×8のボクサー装甲車(全長7.93m)では21mにもなります。同じ8×8の16式MCVは全長8.45mあり、ボクサーの例を見ても20m以上は必要でしょう。ちなみに、装輪式なのに車輪の向きを変えるのではなく、装軌式のように左右の回転数を変えて方向転換するフランスのAMX10RCという装甲車もあります。

乗用車界隈では、最小回転半径が5m以下なら小回りが利くクルマと言われるようです。Uターンできる場所が無ければハンドルをぐるぐる回しながらバックと前進を繰り返し、切り返しをしなければなりません。それでもある程度のスペースは必要です。16式MCVは道路をそのまま走れる戦略機動性には優れますが、細かく動く戦術機動では意外と小回りが利かないのです。
そして、基本的に戦闘においては、戦車も装甲車もその装甲が一番厚くなっている正面を敵方向に向けて行うのが理想であり、できるだけ装甲の薄い側面や後面を敵に晒したくありません。そのようなわけで、小回りの利かない装輪装甲車が戦場で素早く後退や方向転換したい場合には、少々、工夫が必要になってきます。
最新記事
- 激変した”横浜のジャンクション駅”に新道路もう1本! 「駅前ぶち抜きトンネルの“続き”」開通あと少し その続きも!?
- 速ぇぇ! 「世界初の独自開発超音速ジェット機」が最後の”ガチ飛び”! その速度は? JALも出資「21世紀版コンコルド」製造社の機体
- 「うちにある敵の兵器、いる?」 イスラエルが「拾った」ロシア製兵器をウクライナに供与提案 じつは“伝統的なやり方”って!?
- 「衝撃的」 日本の航空ファンにある意味「最も愛されている建物」内部公開にSNS歓喜! 外観とギャップは建物自体も…?
- 「これスポーツカー用ですよ!?」 オバケエンジン積んじゃった「伝説の軽トラ」 はナニモノ? 中古車市場では驚愕の金額も
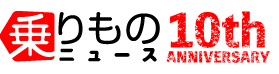





副操式かどうかは割り切った軽装甲の末の運用思想の差であって、装輪/装軌の差では無いのでは? …と思います。
スェーデンのS戦車は装軌式でありながら後方操縦席を持つ事は、よく知られています。
大戦中のイギリスの装軌自走砲で、砲を後ろ向きに積んでしまったが思いのほか使い勝手が良かったハナシも有名です。
設計者に直接取材した内容でない様子。それなら、もう少し周辺情報の分析をしてから書きませんか?