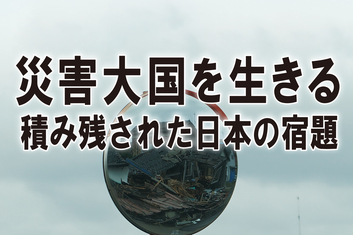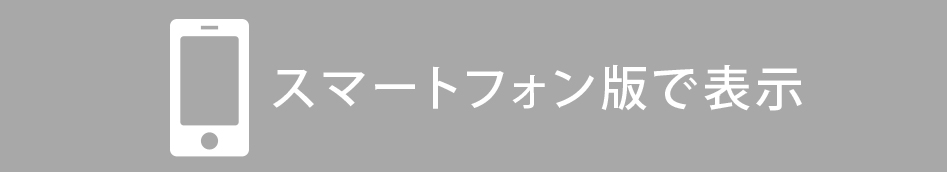今年のスギ花粉の飛散は、1月中旬から各地で始まった。これは観測史上もっとも早く、また過去10年間でもっとも多くなるという予測が出ている。特に西日本では、平年比で2倍以上、昨年比で8倍以上の地域もあると予想される。
こうした予測を紹介すると、すぐに鼻をムズムズさせる人もいるのではないか。そして毎年この季節になると、いつもスギを呪う声が広がる。「スギを全部伐れ!」という意見が強まる。花粉症対策で、もっとも注目されるのはスギの伐採なのである。
だが、あまりにも短絡的だ。飛散花粉を減らすほどスギを伐ることが可能なのか、そして伐れば効果はあるのか。花粉症対策の根幹について考察したい。
非現実的な「スギの伐採」という対策
最初に花粉症の歴史について触れておこう。
世界で最初の花粉症が確認されたのは19世紀の英国で、イネ科牧草の花粉症だった。続いて米国でブタクサの花粉症が社会問題になった。そして日本のスギ花粉症は1964年に初確認された。その後ヒノキやシラカバなどの花粉症も見つかるが、日本の場合はスギの花粉症が7割を占めるため、とくにスギに問題があるかのように考えがちだ。
スギ林は、日本の森林の約2割、448万ヘクタールを占める。生えているスギの本数は、概算で80億~100億本といったところか。スギの年間花粉生産量は、通常1ヘクタール当たり300キロ、豊作年は1000キロになるとされるから、毎年全国に飛散するスギ花粉の量はどれぐらいか……興味ある方はご自身で計算してほしい。
ただ、スギの木を伐り本数を減らせば、飛散花粉も減るのかどうかは微妙だ。たとえば間伐で本数を減らすと、翌年から花粉飛散量は増加したという研究結果が、森林総合研究所から出ている。なぜなら間伐したことで残したスギに光がよく当たり、枝が伸びて花粉を多く稔らせるからである。まるで逆効果なのだ。
では、皆伐するか。それも現実的ではない。まず伐る人員も予算もない。林業従事者は、すでに約4.4万人しかいず、現在でも人手不足だ。伐採量を増やすのは至難の業だろう。
しかも皆伐は、森林土壌を攪乱する。はげ山に豪雨が降れば崩落が起きる。近年の気象を考えれば、災害リスクは大幅に増す。それにスギ花粉は風に乗れば200キロメートルも飛ぶという。つまり身近なスギを伐採しても、花粉は遠くから飛んできて降り注ぐのだ。