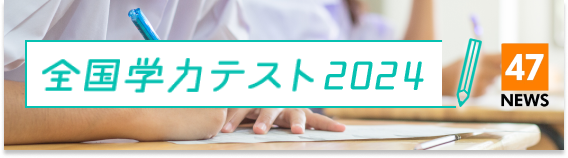(番外編4)「謹」 霊を封じるために祈る
漢字には怖(こわ)い残酷(ざんこく)な字が多いです。その代表的な字を紹介(しょうかい)しましょう。
まず「飢饉(ききん)」の「饉」や「僅少(きんしょう)」の「僅」の右側の字形がイラストの一番上にありますので、この文字と、その古代文字を見てください。両手を交差して縛(しば)られた巫祝(ふしゅく)(神様に仕える人)が、火で焼殺されている姿(すがた)です。頭上にある「口」は顔の「くち」ではなく、神への祈(いの)りの言葉を入れる器「口」(サイ)です。
干(かん)ばつで降雨(こうう)のない時に、巫祝は雨乞(あまご)いの祈りをしたのですが、それでも雨が降(ふ)らないときは、巫祝自らが焼かれ、祈りにささげられたのです。
飢饉などの行き倒(たお)れで死んだ人は不遇(ふぐう)の死ゆえに強い霊力(れいりょく)を持っていると恐(おそ)れられていて、地中に粘土(ねんど)で封(ふう)じ込(こ)められました。「饉」の右側の字形は、そのことを示(しめ)す文字で「ねばつち、ぬる」の意味があります。
「饉」がこの字形をふくむのは、雨が降らず飢饉となったので、巫祝を焼いて祈るためです。それと「食」を合わせた「饉」は凶作(きょうさく)のことです。
行き倒れを葬(ほうむ)り、霊(れい)を封じるために祈ることを「謹(きん)」と言い、「つつしむ」意味となりました。また「僅」も「凶作」の時に穀物(こくもつ)の実りが僅(わず)かという意味です。「勤(きん)」の「力」は鋤(すき)の形で、「勤」は飢饉を救うための農耕(のうこう)に勤労(きんろう)することです。
「嘆(たん)」「歎(たん)」はともに「なげく」意味の漢字ですが、「嘆」の右、「歎」の左の字形の古代文字を見ると、最初に紹介した文字と同形です。これは雨を求めて、神への祈りの言葉を唱え、巫祝を焼き、神様に「なげき」訴(うった)えるという字でした。「歎」の「欠」は口を開き、なげく人の姿です。
最後に「漢字」の「漢」を紹介しましょう。でも「漢」はもともとは地名で、飢饉との関係を示す説明はなさそうです。
陝西(せんせい)省から東南に流れている川「漢水」のことです。その流域(りゅういき)の王だった劉邦(りゅうほう)が紀元前202年に建てた王朝が「漢」と呼(よ)ばれ、「漢字・漢文・漢方」など中国の意味となりました。(共同通信編集委員 小山鉄郎)
【編注】今回テーマの漢字「謹」は常用漢字です。