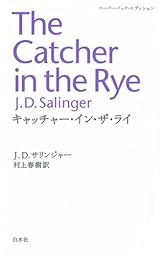作家の読書道 第198回:久保寺健彦さん
7年ぶりの長篇『青少年のための小説入門』が話題となっている久保寺健彦さん。この新作小説にはさまざまな実在の名作が登場、久保寺さんご自身の読書遍歴も投影されているのでは? 聞けばやはり、幼い頃から本の虫だったようで――。
その3「海外の名作を読む」 (3/6)
――高校もその距離を通ったのですか。
久保寺:いえ、これは通ってられないなと思い、家から近いところに入学しました。高校時代は安部公房がすごく好きで、新潮文庫で短篇集がたくさん出てきたので、どんどん買って読んでいましたね。その頃から、「そういえば海外文学って読んでないな」と思い、意識的に読むようになりました。それこそカフカとかへミングウェイとかドストエフスキーとか、ビッグネームがいくらでもいる。でも、僕が住んでいた足立区の本屋さんで『罪と罰』を買おうと思っても、下巻しかないんですよ。たぶん上巻を買って読んで挫折した読者がいたんでしょうね。『ライ麦畑でつかまえて』も4軒くらいまわっても置いてない。だから新宿の紀伊國屋書店まで行って買ったんですけれど、これは駄目だと20歳になってから実家を出て下宿しました。
――『ライ麦畑でつかまえて』という名作があるといった情報は、どこから耳に入ってきたんでしょう。
久保寺:日本の作家のエッセイを読んでいると名前が出てくるじゃないですか。筒井康隆さんも読書家なので、いろんな作家の名前が出てきますよね。それこそガルシア=マルケスとか。そういうのを読んで、「なんかすごそうな作家だな」という知識が蓄積されていったんだと思います。
『ライ麦畑でつかまえて』は、初めて読んだ高校生の時はあまりピンとこなかったんですよね。たぶんタイトルから、勝手にものすごく爽やかな話だと思い込んでいたんです。そうしたらああいう感じじゃないですか。えらく内省的だし、攻撃的だし。ただ、ずっと何か引っかかっていたので30代になってから読み返したら、すごくよくて。「これは稀有な作品だったんだな」と思いました。40代になって村上春樹さん訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』で読み返して、やっぱり素晴らしいと思って。今でもすごく好きだし、本当に世界中で読まれているのは当然だよなと思いました。
――『ライ麦畑でつかまえて』は若いうちに読んだほうが心に響く、とよく言われますよね。でも久保寺さんの場合は違ったわけですね。
久保寺:やっぱり、自分が10代というものをもう経験して、だいぶ距離を置いてみられるようになっていて、10代の限界が分かるからかもしれません。ホールデンって減らず口を叩くじゃないですか。「俺は全然傷ついてない」みたいなことを言うけれど、大人になると「いや、君めっちゃ傷ついているでしょ」というのが分かる。たぶん、同じ年代の頃に読んでもそれが分からないと思うんですよね。ああ、強がりなんだなと分かる歳になってからのほうが、より痛切に感じる。あの小説は17歳のところで終わっているけれど、読み返すたび「今、ホールデンは何歳かな」って思いますね。果たして生き延びられているのか、どんな大人になっているのか。もしもあのままだったら、もうリカバリーできないくらいの傷を受けているかもしれないなと思う。だから大人になって読むほうが、感じる切実さが違うんです。
話がそれますが、メアリー・マッカシーの『アメリカの鳥』という小説があって。「ライ麦畑」は1950年代に出ていますが、『アメリカの鳥』は1960年代でベトナム戦争の頃なんです。主人公は19歳の大学生なのに、カントの哲学の教えを守ろうとしている。フリーセックスとかの時代にそんなことを言っている子は当然ズレているわけで、さんざんな目に遭うんです。時代にそぐわないという意味でホールデンに近いところがあるんですが、減らず口は叩かないし、よりナイーブ。この話もすごくよかったですね。これは40代の頃に読んだんですけれど。
――ところで好きな作家のエッセイから他の作品を知るということですが、北杜夫さんに限らず、好きな作家は小説だけでなくエッセイも読んでいたんですね。
久保寺:読みました。遠藤周作さんの狐狸庵先生のシリーズも好きでした。筒井さん、井上ひさしさんのも読んでいて、筒井さんは『腹立半分日記』というのがあるんですよね。それで日記も面白いかなと思って、高校生の頃に真似して自分も日記を書きだしたりしました。後で役立つかなという気持ちもあって。いまだに書いているので、30年くらい続いていることになりますね。
――ノートに書いていたとしたら、もう相当溜まっているのでは。
久保寺:相当ですね。でも、基本的にどこに行き、誰と会って、何を食べたかくらいしか書かないので1日分が1行か2行くらい。たまに何か大きな出来事が起きた時だけ長文になるので、ぱっと見返した時に視覚的に「あ、ここは何かがあった日だ」と分かります。読んだ本の記録もつけていますよ。普段は「何を読んだ」「何を買った」程度ですが、読んですごくいいか、逆にすごく悪かった時には批評というか感想文を書いたりはします。
――日記が「役立つかな」と思ったのは、小説の執筆に役立つかな、という意味ですよね。作家になろうという気持ちは持ち続けていたわけですね。
久保寺:大学生の頃は「絶対に就職しない」と思っていました。僕の頃って、まだバブルがはじける前で景気が良かったんですよ。フリーターっていう言葉も出だした頃で、何しても食っていける空気がありました。だから、まずは就職しないで作家になろう、と。さきほど言っていた「医者と作家の兼業」は、高校生の時に微分積分とかが全然駄目で文系に変更したので、医者を放棄して作家一本で、ということに決めていました。
――あれ、大学の学部ってどちらでしたっけ。
久保寺:立教大学の法学部でした。全然勉強してなくて、引っかかったのがそこだけだったんです。でも僕は作家になりたいわけで法律なんて興味がないから、入ったはいいけれど苦痛で苦痛で。結局1年留年しましたし。5年生なのに1年生の時に取るはずの保健体育の単位が残っていたりして。