

メルマガ「週刊 Life is Beautiful」で「なぜ日本は原発を止められないのか」という連載を始めた。通信業界の東京電力に相当するNTTで働いていた経験を活かし、霞ヶ関や東電のエリートが何を考えてあんな行動に走るのかを解説する。ちょうど良いタイミングで先日の「さようなら原発10万人集会」での坂本龍一氏の「たかが電気のためになんで命をさらさなければいけないんでしょうか」という発言が注目を集めているので、このブログでもひと言書いておく。 「たかが電気」という発言に対して「電気を止めたら死んでしまう病人がいる」「真夏にクーラーがかけられなければ、熱中症で死ぬ人がいる」と噛み付いている人がいるが、これらの指摘は大間違いである。日本は、原発を止めたぐらいで、病人の生命維持装置が止まってしまったり、熱中症で死ぬ人が増えたりする国ではない。 本当の理由は別のところにある。日本経済が重度な「原発依
政府・与党が議論しているエネルギー基本計画の政府案には、核燃料サイクルを推進するなどというとんでもないことが書かれています。 しかし、核燃料サイクルは、現状では進めようとしても進められないのが現実です。 なぜ、核燃料サイクルを進められないのか、ひろく大勢の皆様と問題意識を共有していきたいと思います。 ----------------------------- 本音と建前の乖離 まず、なぜ経産省と電力会社は、破綻しているのが明白な核燃料サイクルを強引に進めようとしているのでしょうか。 電力会社はこれまで立地自治体に対して、使用済み核燃料は原発敷地内のプールで一時的に冷却保管するが、一定の時間が来れば青森県の再処理工場に搬出するので、使用済み核燃料は立地自治体には残らないという約束をしてきました。 一方、再処理工場がある青森県は、使用済み核燃料は、再処理の原材料であるという位置づけで県内への

Robert Geller; ロバート・ゲラー @rjgeller これまでも公の原発再稼働すべきかどうかの議論は「安全かどうか」の二者択一の類のです。しかし、人間がつくるものに、原発を含めて、必ずリスクがあります。したがって、二者択一論を貫けば、原発を含めてどのものでもリスクがゼロでないため、全てのものは「安全ではない」となります。#risk 2013-04-10 05:38:58 Robert Geller; ロバート・ゲラー @rjgeller 議論の枠を変えないといけません。「二者択一」(安全、安全ではない)から、「リスクの定量的、客観的の評価」へ切り替えないといけません。リスク評価(不確実の評価を含めて)とその冷静な説明は専門家の仕事です。そのリスクを背負っても良いかどうかの判断は市民と政治の仕事です。#risk 2013-04-10 05:44:54 Robert Geller

先日ご紹介した『ハゲタカ』の著者、真山仁さんのもうひとつの名著『ベイジン』を読了。『ハゲタカ』とはまた違う意味で衝撃的でした。この本、今のタイミングで日本人が読むとかなり複雑な気持ちになると思います。 〜以下、ややネタバレ気味に『ベイジン』のあらすじが書かれています。あらかじめご了解の上お読み下さい。〜 2008年に出版されたこの小説は、中国が北京オリンピックにあわせて世界最大の原子力発電所を稼働させるという計画をたて、そのために指導顧問として日本から派遣された原子力技術者が、中国の技術者を指導するという話です。 その中で一貫しているのが、「世界最高の技術力をもち、世界で最も安全な日本の原子力発電」の関係者が、「中国の危ない原発の建設&運営を指導する」というトーン。中国人労働者や技術者がいかにいい加減か、日本人技術者がいかにきまじめで安全に気を遣っているかが、延々と描かれます。 ちきりんは
先日、計画停電よりも市場メカニズムを使うべしという野口悠紀雄氏の提言を紹介したが、この鈴木亘氏の提言もいい。 SYNODOS JOURNAL - 市場メカニズムを活用すべき電力不足対策 鈴木亘 http://synodos.livedoor.biz/archives/1720131.html <現在行われている計画停電に対し、首都圏の人々は「東北の人々のことを思えば、これぐらい仕方ない」「国民がひとつになって危機を乗り越えよう」と、不便さによく我慢をしている。病院や老人ホーム、在宅医療をつづける患者にとっては、まさに命の問題が発生しているが、本当によく耐えている>。 <しかしながら、本来、計画停電や総量規制のような「社会主義的な手段」は、命の問題にとっても、生産活動にとっても、非常に「非効率」である。早い震災復興を望むのであれば、こうした手段をつづけたり、大規模に行うことは望ましくない。生
今日の甲州はよく晴れましたが、まだまだ朝晩はかなり冷え込みます。本格的な春の到来が待たれるところです。 さて、深刻さを増す福島の原発事故ですが、これについて最近考えていることをここで少し。 まずこれを書く前にここでお断りしておかなければならないのは、私は別に原発の推進派でも反対派でもなく、あくまでも今回の原発事故の及ぼす影響に憂慮している一国民だということです。 しかしそうは言ってもとにかく気になっている疑問が、なぜここまで原発というものが怖がられるのか、という問題。 私がなぜこんなことを考えたのかというと、CNNの(元オフェンシブ・リアリストの)ザカリアの番組のブログの記事の中に、「過去数十年間にわたる原発の事故による死者というのは、他のエネルギー関連の死者数よりも遙かに少ない」ということが書かれていたからです。 たとえば石炭だと中国や最近のニュージーランドでの炭鉱の事故で大量の死者を出
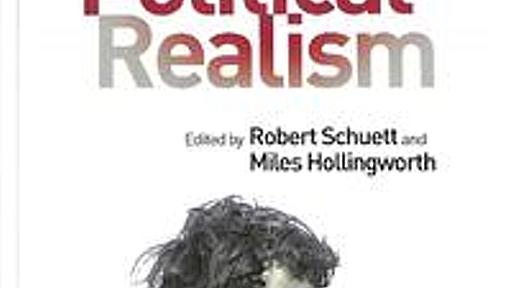
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く