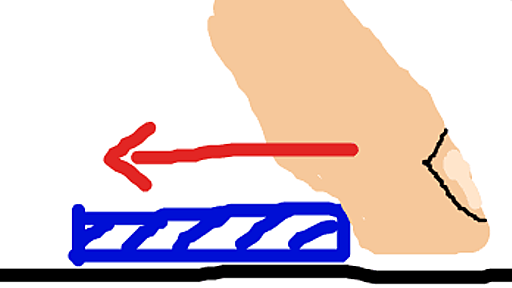UXデザインのコンサルティングではよく品質優先度マッピングというものを行います。これは開発プロジェクトの上流工程において、実装を検討している機能をリストアップし、そのひとつひとつについて想定する利用者の割合や利用頻度の観点からグルーピングし、実装の優先度を決める作業です。 これを行う目的は、UIをできるだけシンプルに保つことにあります。ユーザーが求める機能をすべて盛り込むと、当然UIは複雑になり、誰にとっても使いにくいものになります。また蓋然性のバランスが取れていない要件はプログラムを複雑にし、バグが増える原因になります。 UIデザインにおけるパレートの法則(結果の大部分は全体の一部によって生み出される)は、「ユーザーの80%は全機能の20%しか使わない」というものです。その20%に注力し他の優先度を下げることで、製品の利便性は向上するはずです。 Core, Important, Nice