エッシャーの絵といえば「無限」を描いた騙(だま)し絵のトリックが有名だ。たとえば、建物の屋上に階段の回廊があって、そこを上り続ける人がいる。回廊を一周まわると元に戻って、階段は続いていく。そんなエッシャーの絵は、これまで錯視図形の応用で、それをちょっと具象的な光景の中に描いたもの、くらいに考えられてきた。しかし本書では、もっと驚くべき絵画の仕掛けが隠されていることが明らかにされる。著者の近藤滋

エッシャーの絵といえば「無限」を描いた騙(だま)し絵のトリックが有名だ。たとえば、建物の屋上に階段の回廊があって、そこを上り続ける人がいる。回廊を一周まわると元に戻って、階段は続いていく。そんなエッシャーの絵は、これまで錯視図形の応用で、それをちょっと具象的な光景の中に描いたもの、くらいに考えられてきた。しかし本書では、もっと驚くべき絵画の仕掛けが隠されていることが明らかにされる。著者の近藤滋


■単行本 『労働・自由・尊厳──人間のための労働法を求めて』 相澤 美智子 2025年1月23日 配信開始(2021年3月16日発行) 『岩波講座 世界歴史(第13巻) 西アジア・南アジアの帝国 16~18世紀』 荒川 正晴 編集委員/大黒 俊二 編集委員 他 2025年1月23日 配信開始(2023年1月27日発行) 『岩波講座 世界歴史(第14巻) 南北アメリカ大陸 ~17世紀』 荒川 正晴 編集委員/大黒 俊二 編集委員 他 2025年1月23日 配信開始(2022年2月25日発行) 『岩波講座 世界歴史(第15巻) 主権国家と革命 15~18世紀』 荒川 正晴 編集委員/大黒 俊二 編集委員 他 2025年1月23日 配信開始(2023年3月24日発行) 『岩波講座 世界歴史(第16巻) 国民国家と帝国 19世紀』 荒川 正晴 編集委員/大黒 俊二 編集委員 他 2025年1月23

「民藝のみかた」 [著]ヒューゴー・ムンスターバーグ 今日の現代美術ブームの背景には、作家の署名を必要とする自我表現としての個人主義があるように思える。 僕が大衆芸術と呼ばれるグラフィックデザインを起点とした1960年代はモダニズムの台頭する時代で、僕が地方で幼年時代を過ごした頃は土俗的産物として民藝(みんげい)が生活環境を支配していたように思えた。 民藝もグラフィックも大衆という同根を源流にしていたにもかかわらず、近代デザインを確立するためには民藝はどことなくうさん臭く、この時代から排除されており、土俗的環境からいきなり西洋近代主義に洗脳されたために、僕の内部の民藝的土俗性を追放せざるを得なかった。が、わずかに残った土俗的尾骶骨(びていこつ)によって、あの時代の僕の演劇ポスターが生まれた。 さて、その時代に民藝がすたれかけた理由は、有名性を否定し、あくまで実用を目的として芸術的な試みを無

「それ」のあったところ: 《ビルケナウ》をめぐるゲルハルト・リヒターへの4通の手紙 著者:ジョルジュ・ディディ=ユベルマン 出版社:新曜社 ジャンル:アート・建築・デザイン 『「それ」のあったところ』 [著]ジョジュジュ・ディディ=ユベルマン 哲学者アドルノによる「アウシュヴィッツ以降、詩を書くことは野蛮である」は、詩人のみならず、以後を生きるすべての表現者に大きな困難を背負わせた。ひとつの民族をこの世界から抹消しようとしたヒトラーの蛮行は、それを経てなお、かつてと同じように芸術にいそしむことに根源的な疑問を突き付けた。 事実、世界最高峰と称されるドイツの画家、ゲルハルト・リヒターでさえ、アウシュヴィッツを「描く」のに、題材となる写真と出会ってから60年もの時を要した。リヒターが重い腰を上げるきっかけとなったのは、本書の著者であるフランスの哲学者ディディ=ユベルマンによるアウシュヴィッツ論

目 次 凡 例 解 説 イタリア・ルネサンス芸術論(池上俊一) 美 学 1 ジョルダーノ・ブルーノ 紐帯一般について 模倣論 2 ジュリオ・カミッロ 模倣について イデア論 3 フェデリコ・ズッカリ 画家・彫刻家・建築家のイデア 理想都市論 4 アントニオ・フィラレーテ 建築論(第二書) 建築論 5 セバスティアーノ・セルリオ 建築七書(第四書) 庭園論 6 アゴスティーノ・デル・リッチョ 王の庭について 色彩論 7 フルヴィオ・ペッレグリーノ・モラート 色彩の意味について 絵画論 8 レオン・バッティスタ・アルベルティ 絵画論 9 ジョヴァン・パオロ・ロマッツォ 絵画神殿のイデア 彫刻論 10 ポンポニオ・ガウリコ 青銅の鋳造術について(第一章) パラゴーネ 11 フランチェスコ・ドーニ 素描論(第六章) 工芸論(陶芸) 12 チプリアーノ・ピッコルパッソ 陶芸三書(第一書) 工芸論(金
音楽、絵画、小説、映画など芸術的諸ジャンルを横断して「センスとは何か」を考える、哲学者の千葉雅也さんによる『センスの哲学』。「見ること」「作ること」を分析した芸術入門の一冊でもあり、『勉強の哲学』『現代思想入門』に続く哲学三部作を締めくくる本書は、2024年4月の発売以来、累計55000部のベストセラーに。 『寝ても覚めても』『ドライブ・マイ・カー』などの監督作で知られ、話題の最新作『悪は存在しない』に続き、映画論『他なる映画と』全2冊を出版した濱口竜介監督との対談が実現。大学時代からの旧知の仲でもあるというふたりの待望の初対談は、「鑑賞と制作」(見ることと作ること)の深みへと展開した。「文學界」(2024年9月号)より一部抜粋してお届けします。 大学時代の二人の出会い 濱口 人によっては意外な組み合わせだと思うかもしれないですが、千葉くんと私は同い年です。誕生日が2日違い。私が浪人したの

December 2, 2023 | Art | casabrutus.com | photo_Keisuike Fukamizu text_Toko Suzuki バンクシーの代表作《花を投げる人》は実はパレスチナ問題を描いた作品です。ガザ地区でイスラエル軍とハマスの戦闘が続く今こそ、バンクシーがパレスチナで活動してきた20年間をおさらいし、作品を通じて訴えてきたメッセージを改めて考えてみたい。2002年にバンクシーに直接インタビューし、『Casa BRUTUS』2020年3月号の特集「バンクシーとは誰か?」では、ともにパレスチナを取材した鈴木沓子さんにご執筆いただきました。 ヨルダン川西岸地区のベツレヘムに描かれた《花を投げる人》。圧倒的な武力を持つイスラエル軍の軍事占領と攻撃に投石で抗議したパレスチナのインティファーダ(抗議運動)をモチーフに、顔を半分隠した男の手に、石ではなく花

まつい・ひろみ 東京大学大学院総合文化研究科准教授。博士(美術史)。専攻は、フランスを中心とする近現代美術。著書に『キュビスム芸術史:20世紀西洋美術と新しい<現実>』(名古屋大学出版会、2019年)、翻訳にデイヴィッド・コッティントン『現代アート入門』(名古屋大学出版会、2020年)など。 この連載では、数回前から美術史的著述における「触覚」をめぐる議論について辿り直している。辿り直す、といっても、それらの諸議論はわかりやすい一本の系譜を成しているわけではない。それぞれの著者は、別の著者の「触覚」の議論と共通の知識や前提から出発している場合もあるのだが、そこからどのように作品分析に展開していくのか見ていくと、この連載の他の記事でも述べてきたように、驚くほどの多様性に満ちていることがわかる。過去の「触覚」の議論を承けていることを明らかにしている著述でさえ、具体的な作品分析を通して、別の議

なぜ美術は教えることができないのか 美術を学ぶ人のためのハンドブック 著者:ジェームズ・エルキンス 出版社:三元社 ジャンル:教育・学習参考書 「なぜ美術は教えることができないのか」 [著]ジェームズ・エルキンス 書名で提起されている問いはわたしにとってひときわ深刻だ(肩書を見てほしい、同類なのだ)。しかも著者は「結論」のなかではっきりと答えている――。「美術を教えるという考えは修復しがたいまでに不合理である」と。 もっとも、同様の問いは珍しくはない。だが、本書では「歴史」「会話」「理論」の3章をまるごと費やしてその困難さについての分析がなされる。さらにその不合理さを第4章の「批評」に集約させる。ただし、ここでの批評とは学生たちが教員の前で作品を発表する講評のことで、そこでのやりとりについて著者はみずからも勤める美術大学での一種、異様な実例を引きながら筆を進める。 ただし、その徹底ゆえだろ

「小さな芸術」 [著]ウィリアム・モリス 「小さな芸術(レッサー・アーツ)」とはなにか。歴史に名を残す絵画や彫刻、建築(グレーター・アーツ)に対し、名もなき職人芸、生活の美、つまりは民衆芸術のことを指す。だが、なぜ「小ささ」が強調されるのだろう。産業革命以降の生活と美意識の激変が、両者の関係を無残に破壊したからだ。民衆が日々の暮らしと労働とを美しく生きられることなく、芸術は成り立たない。盛況に見えるなら、芸術がたんなる贅沢(ぜいたく)品にすり替わり、金持ちの慰撫(いぶ)に成り下がったからだ。真の意味での芸術の復興のためには、この「小ささ」の復興が絶対に欠かせない。 強い信念に支えられたモリスの口調は、たいへん理想主義的だ。が、裏腹に随所で攻撃的な性質をはらむ。具体的には「そうした贅沢品のせいでわれわれの家はがらくたで一杯になって芸術は息もつまらんばかりになり」「新しい建設の始まりが明らかに
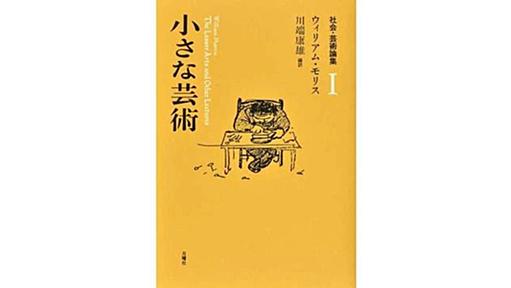
「目で覚える 動きの美術解剖学」 [著]ロベルト・オスティ ギリシャ彫刻の傑作の一つである神官・ラオコーン。制作時期は、紀元前2~紀元1世紀とされる。ラオコーンの表皮を剝(は)いだと仮定すると、その下から精密な解剖図が現れるという。上腕二頭筋の下にある小さな筋肉「烏口腕筋(うこうわんきん)」まで再現されているのだから驚きだ。 人体解剖が積極的に行われるのは14~16世紀のルネサンスである。しかし紀元前のギリシャ彫刻家は、それ以前から皮膚下の様相を正確に理解していた。彼らも解剖を行っていたのか? 真実は闇の中だ。 「解剖」と聞くと、すぐに医学を予想する。しかし、本書を通じ気付いた。解剖は医学だけのためにあらず。走ったり、笑ったり、考えたりする時、身体はそれに合わせた表情をとる。解剖とは、身体の多様な表情を誠実に汲(く)み取るための知性であり、私たちをあっと驚かせる芸術も、その基本の先に生まれ

本書には80篇(へん)ほどの短い文章が収まる。それぞれは大概、2、3の東西の絵画に触れつつはじまる。文章に添えてまず図像が置かれる。該博な知識で細部や背景が言及されるのは当然だが、一般の美術書と大いに異なるのは、絵画が鑑賞されているのではないことだ。では、なにが語られるのか。短いおよそ80の文章は、自身の絵画制作と並行して書かれた。とはいえ、制作の自己解説でもない。書くにせよ描くにせよ、人はま

ISBN: 9784622090939 発売⽇: 2022/11/22 サイズ: 22cm/331,7p 「ネオ・ダダの逆説」 [著]菅章 日本の戦後前衛美術で際立つ存在感を示したネオ・ダダ(ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ)を論じた「日本で初めてのまとまった書籍」である。もっとも、最初に手掛けられた文章は1990年代末に着手されている。「あとがき」では本書の効果の半分が「図らずも熟成を待ちながら寝かせた古酒」に喩(たと)えられている。「新たに仕込んだ新酒」が「時空を超えてブレンド」されているからだ。 どのあたりが新酒なのだろう。著者はかねてネオ・ダダが「戦後美術史の徒花(あだばな)」になりはしないかと危機感を抱いてきた。グループとしてのネオ・ダダは、赤瀬川原平、荒川修作、篠原有司男(うしお)、吉村益信や、周辺の工藤哲巳や三木富雄、建築家の磯崎新といった綺羅星(きらぼし)のごときアーティ

「性と芸術」 [著]会田誠 美術館での展示に市民団体から抗議文が出されるなど、いくたの難儀と直面してきた連作「犬」。その作者が23歳のとき初めて描いたこれらの絵画について、制作の動機や意図について思い余すところなく書いたのが――帯に「ほぼ『遺書』である」とある――本書の根幹をなす第1章「芸術 『犬』全解説」である。 そもそも、画家はみずから自作の「全解説」など行わない。作品は作品をして語らしめるべきで、作者の饒舌(じょうぜつ)がどれほど「悪趣味」かは、本人も十分すぎるほどわかっている。それでもみずから「最悪のサンプル」と呼ぶ「全解説」を刊行したのは、「ネットに溢(あふ)れる悪評に対して作者としてきちんと応えよう」というのが大きかったようだ。 その意味では、本書を一種のSNS論と受け取ることもできる。というのも、SNS、とりわけここで問題となっているツイッターでの「呟(つぶや)き」はわずか1

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く