
側転するって凄い...! 多脚ロボってマジでカッコいいですよね。多脚って聞くとタチコマとかEVA仮設5号機とか連想しちゃって胸が熱くなります。アーマードコアでも多脚しか使いませんよ俺。 表裏全方向対象デザインの6本肢ロボット*ASTERISK [DigInfo TV] (西條鉄太郎)
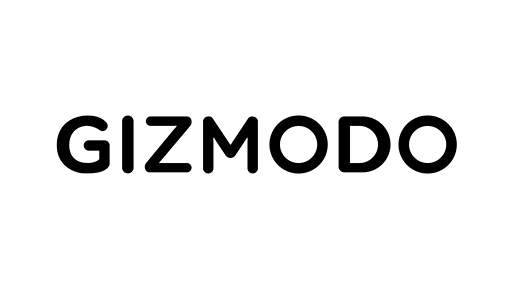
筑波大発のベンチャー企業「サイバーダイン」(茨城県つくば市)は、放射線被曝(ひばく)を防ぐ金属製防護服を着用した人の作業負担を軽減するロボットスーツを開発し、7日、報道陣に公開した。 福島第一原発など放射線量が多い現場での活用が期待される。 同社によると、被曝量を半減させるためには重さ約40~50キロのタングステン製の防護服が必要とされるが、移動や長時間の作業が困難だった。ロボットスーツは最大60キロの重量まで耐えられるよう金属の強度を上げ、防護服を支えるフレームをつけ、歩行など脚の動きを支援する。ロボット本体はバッテリーを含めて約15キロあるが、重さを感じずに動かすことができるという。 原発事故を受け、国内の原発プラントメーカーが7月、医療・福祉用ロボットスーツ「HAL」を開発した同社に依頼した。同社では冷却装置が付いたタイプのロボットスーツの開発を急いでいる。社長の山海嘉之・筑波大教授
等身大ボトムズやフリーキックマシン「カストロール1号」を生み出した鉄アーティストの倉田光吾郎さんが、「乗れるロボットが作りたい」と発言していたのが昨年の1月。それからたった1年程度の月日しか経過していないのですが、全長4mの人間が搭乗可能な鉄製ロボットを作っている最中で、ある程度の形は仕上がっていると聞いたため、その制作風景を見せてもらうことに。 当初は倉田さん1人で作っていたのですが、途中からロボット制御ソフトウェア「V-Sido」の開発者・吉崎航さんも制作に参加。その経緯や、これから作りあげていく制御系の構想などについてもいろいろと聞いてきました。 これが乗って操縦できる巨大鉄製ロボット「クラタス」(仮称)。制作者の倉田光吾郎さんによれば、「人型四脚エンジン駆動陸戦兵器型トイロボット」とのこと。 倉田さんが制作した、「クラタス」のスケール感をつかむための模型。人間と並んだ時、これくらい

印刷 関連トピックスホンダ東京電力原子力発電所アシモのプロフィル ホンダの二足歩行ロボット「アシモ」が、東京電力福島第一原発の事故現場に投入される可能性が出てきた。ホンダは、人間に近い作業ができるアシモの技術を応用し、専用ロボットを開発。人が近づけない放射線量の高い場所で作業することを検討している。 活用が検討されている機能は、人のように滑らかに動く腕の技術。モーターで動く肩やひじ、手首の微妙な力加減を、コンピューターで調整できる。 ホンダは、アシモを原型として、腕の技術を生かした事故処理専用ロボットの製作をめざしている。現場は足場が悪く、転倒の危険もあるため、足回りは二足歩行ではなく、タイヤや、戦車のようなクローラー(無限軌道)を使うとみられる。 関連リンク〈日刊工業〉原子力機構、原発用ロボ完成−50メートル先まで線量測定(6/22)「原発作業60歳以上で」 165人応募、議論呼ぶ
沖電気工業と岡村製作所は11月4日、座面と背もたれにロボット技術を採用し、自然な座り心地を目指したオフィスチェア「LEOPARD(レオパード)」のコンセプトモデルを発表した。2009年5月末の商品化を予定しており、価格は未定。 沖電気工業が2005年6月に発表した脚型ロボット「ロボットレッグ」のメカニズムと、岡村製作所の持つオフィスチェアのノウハウを基にして共同開発した。ゲストを迎えるラウンジや、コミュニケーションのためのパブリックエリアでの使用を想定したモデルだという。 ロボットレッグは「人間が跳躍や着地などをバランスよく行えるのはなぜか」を分析し、人間の大腿部から股関節周辺の筋肉のメカニズムを参考にして開発したロボット。このロボット技術を、LEOPARDの座面から背もたれにかけて採用した。使用にあたって電源は不要となっている。 座面は大きく傾斜しており、自然に深く座ることができる。座る

Microsoft® Robotics Developer Studio 4 enables hobbyists and professional or non-professional developers to create robotics applications targeting a wide range of scenarios. This release is an update that has the functionality of the previous RDS 2008 R3 Standard Edition with the addition of support for the Kinect sensor and a defined Reference Platform, also referred to as MARK (Mobile Autonomous
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く