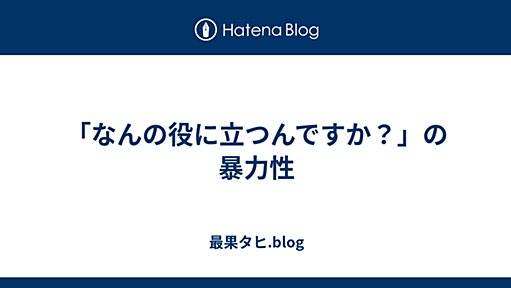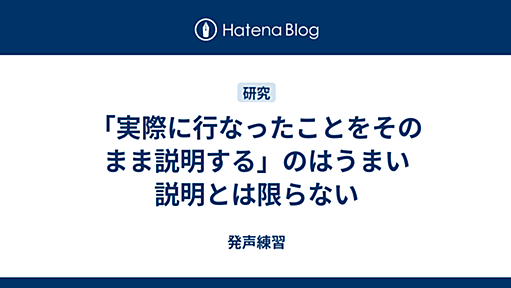研究室用に書いた文書を転載します。主に工学系(コンピュータサイエンス系)分野の査読付き学会や論文誌に投稿することを想定しています。 以下は論文を書くときに個人的に気をつけていることです: メッセージをシンプルに:要するに何が言いたいのかが一言でサマライズできていること。記憶に残ること。 メッセージが伝わらないと、そもそも査読で落とされるし、たとえ学会で発表できたとしても誰も覚えていてくれない。実際、国際学会でも発表論文の多くが誰にもリファーされず、翌年になると忘れられている (どんな論文がどのくらい参照されているかはGoogle Scholar, Microsoft Academic Searchなどでわかる)。 問題はなにか・なぜこの問題が重要なのか・問題の原因は何か・どんな解決案を提案するのか・その効果は本当か・他にどんな研究があるか(なぜそれらの既存研究ではだめなのか)・誰のために役