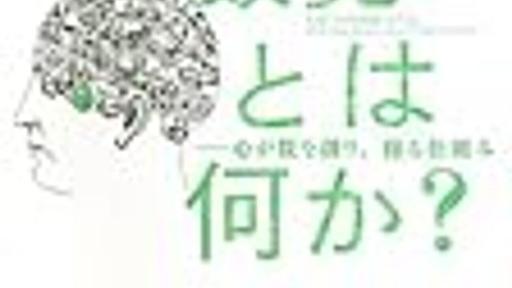●Tyler Cowen, “Risk vs. uncertainty”(Marginal Revolution, December 13, 2005) フランク・ナイト(Frank Knight)やオースリア学派の著作に目を通したことがあるようなら、「『リスク』と『不確実性』の違いって何だ?」って疑問に思った経験があるに違いない・・・よね? ニューロサイエンス(神経科学)がその答えのヒントを提供しているようだ。 実験に参加した被験者たちは、fMRIで脳の活動を観測されながら、曖昧な(ambiguous)賭けに臨んだ。 実験の一つでは、2種類の箱が用意された。「リスキーな」箱の中には、赤色のカードと黒色のカードがそれぞれ20枚ずつ入っている。もう一つの「曖昧な」箱には、赤色のカードと黒色のカードが合わせて40枚入っているが、その内訳がどうなっているか――赤色のカードと黒色のカードがそれぞれ