
アジャイル開発の外部委託が「偽装請負」だと疑われないためにすべきこと、厚労省が公表した疑義応答集を読み解く(前編)。Agile Japan 2021 アジャイル開発において開発担当者を外部のベンダに依頼した場合、必然的に発注側の企業とベンダ側の開発者が1つのチームとなり密なコミュニケーションを行います。 すると、発注側の企業がベンダの開発者の業務遂行に対して具体的な指示を行う、いわゆる「偽装請負」とみなされる可能性があるのではないか? という疑義が以前から呈されていました。 この疑義に対して、どのように対処すれば偽装請負と見なされないか、その指針が今年9月に厚生労働省から「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」として公表されています。 オンラインで11月8日に開催されたイベント「Agile Japan 2021 Day 0」では、この疑義応
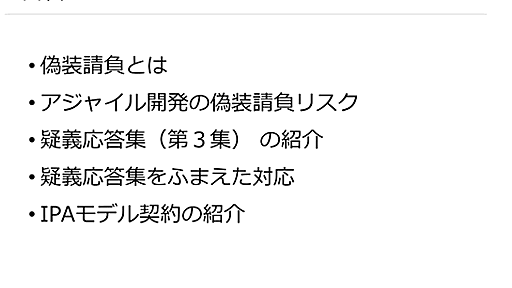
楽しくインターネットサーフィンをしていたら、以下みたいな記事を見ました。 コインチェック経営陣、しどろもどろの謝罪会見。社長が筆頭株主なのに「株主と相談します」(全文) これに対して「ハフィントン・ポスト大丈夫かよ」とか「投資契約書もろくに見たことないんじゃないか」みたいな批判が周りで聞かれました。なぜ批判されるかというと、タイトルで言いたいことが「しどろもどろの社長が、筆頭株主なのに株主と相談する、といって質問から逃げてけしからん」的なニュアンスに見えてしまうのですが、知識がある人から見ると「そんなの当たり前じゃん」というギャップがあるからだと思います。 せっかくなのでこの件について説明したいと思います。 まず、よくある誤解として「過半数の株を持っているのであれば、なんでも決められるのでは?」という点です。会見でも以下のような場面がありました。 > ――筆頭株主はどなたか。 > 大塚氏:

ファイナンシャルアドバイザリーに関する用語を分かり易く解説する「ビジネスキーワード」。本稿では「株主間契約」について概説します。 株主間契約の概要 株主間契約は、複数の株主が存在するM&Aでは一般的に株式譲渡契約と平行して準備される契約書で、各株主が契約当事者となり締結される。株式譲渡に至る交渉での合意事項など、クロージング後から有効となる株主間での取り決めを契約として文書化したものである。 上場会社を対象企業としたM&Aの場合は、一般少数株主が存在するため、少数株主保護の観点から一部の主要株主のみでの株主間契約には実務上制約が多い。一方、そもそも限られた株主のみで構成される非上場会社においては、関連法規制に則れば、自由に株主間の合意に基づいて契約を締結することができる。 投資実行当初は、さほど気にならない「細かいルールの文書化」とも思えるが、有事の際の備えとなるのが株主間契約である。ここ

柴田: 「しば談」の第一回目は、習い事のマーケットプレイス、サイタを創業して売却した有安伸宏さんににお越しいただきました。まずは、簡単に自己紹介をお願いします。 有安伸宏さん(以下、敬称略): 19歳の時に初めて起業して以来、今まで4つ会社を作り、うち3社を売却してます。ネット系の創業経営者として、あわせて15年位の経験があります。直近に作った会社は、習い事のレッスンのマーケットプレイスを運営するコーチ・ユナイテッド株式会社。その会社を2013年に上場企業へ売却、2016年2月に社長を退任して、今に至ります。 個人でエンジェル投資もやっていて、家計簿アプリのマネーフォワード社、ファッションECのMaterial Wrld社など、コンシューマ向けの事業に投資しています。あとは、Tokyo Founders FundというExit(注:IPOもしくはM&A)を経験した日本人8人でやってるファン

PacRim VenturesのKevin LawsがVenture Blogで「Beauty Contests and Venture Valuations」という文章を書いている。未公開企業のValuation(企業価値)はどう決まるかがテーマである。未公開企業の企業価値というものが、いかにarbitrary(自由裁量的、気紛れ、恣意的)な決められ方をするかということを、初心者向けに説明したものである。 「This is because venture valuations represent a form of what economist John Maynard Keynes called a "beauty contest".」 「The venture business is driven by the same logic when setting valuations.」

小池さんは、小さいながらも、従業員を5人使い配管工事を営む会社の社長です。この会社は小池さんが20年ほど前に設立し、最近は業績も安定してきています。小池さんは、この10年間、騙されて金を取られたり、親しい友人に紹介されて仕事をしたらその取引先が倒産したり、色々な目にあいました。そのおかげで、若干の法律知識を身につけていました。 その一つが取引先から個人保証をとることでした。初めは取引先に対して「個人保証してくれ」とはなかなか言いにくかったのですが、弁護士に「基本契約書 」というものを作ってもらい、その中に「連帯保証人」の欄を作り、「うちの会社では、いつも、この契約書を使っています」と、自然な会話で、取引先から押印してもらうのです。取引先の倒産この基本契約書が役に立つときがきました。取引先の設備会社がつぶれ、その社長の飯田さん一家が逃げてしまったのです。小池さんはこの設備会社振出の870万円
自分が起業してからというもの、ビジネスアイデアや初期的な資金調達に関する相談などをこれから起業する人、起業した直後の人から相談を受けることが多い。 そんな中で、いつも聞いていて辛くなるのが、創業後しばらくした後の「創業株主同士での株式に関する問題」を聞いた時。 これ、めちゃくちゃ多い。 本当に。 創業株主が会社を去ってしまうことがあっても、資本政策については後戻りが難しいため、何かあった時のために「創業株主間契約書」を結んでおくことはすごく重要。 今日は、なぜそれが重要か、そしてどういう内容の契約をしておけばいいのか、についてちょっと書いてみる。 (法律・税務が絡む話なので、実際にはちゃんと弁護士・税理士に相談することをおすすめする) photo credit: -Snugg- via photopin cc 創業株主間での株式に関する揉め事はものすごーーーく多い! 創業者間での株式に関す

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く