

そこそこユーザビリティの高いフォームを作った 入力内容の検証とか、郵便番号変換を備えた、そこそこ使いやすいフォームのテンプレートを作りました time2014/01/18 hatenabookmark- 去年末実家に帰省していた時に、jQueryの練習&業務で使うために、フォームバリデーションとか郵便番号変換とかを備えた、そこそこユーザビリティの高い入力フォームをコーディングしていたので、ここで公開しておきます。 フォームサンプル ソースお持ち帰り用 (Github) ここで"そこそこ"と言っているのは、もともと業務でユーザビリティ改善案として使うことが目的であって、ベストを目指してもサーバ制約やコスト的な観点で使えないことがあるから、そこは目指さないよという意味です。そもそも、フォームは必要悪ですし、ベストはフォームが存在しないことですね。 フロントエンド実装だけです(サーバ側スクリプト
「CEATEC JAPAN 2013」会場にて開催された「アクセシビリティセミナー2013」のセッション1「企業のWeb担当者、Web制作者必見! 企業WebサイトにおけるJIS X 8341-3:2010対応の実践例」の資料です。講師および資料作成を担当したのは、ウェブアクセシビリティ基盤委員会 作業部会2委員で、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の澤田氏です。 なぜアクセシビリティに取り組むのか、その理由をキヤノンサイトの歴史を紐解きながら解説。取り組みの具体的な内容については、2013年のリニューアルにおける施策を中心に紹介。JIS対応で得られる効果や苦労している点は、企業のWeb担当者の方々にとって大変参考になる内容かと思います。Read less

オープンソースの集まりで1度しか実際にお会いしていませんが、お願いがあります。 富士通アクセシビリティ・アシスタンスというサービスが、2013年8月20日で提供終了します。つまり、あと20日。このソフトは視覚障がい者や色覚障がい者の方がどのように色を見ているかを確認できるツールです。Webサイト制作をしている人なら、今は必要なくても、いつか必要になるソフトです。 8月20日までにダウンロードすれば、8月21日以降もローカル環境で普通に使えるので、なんとかメディアで紹介して頂き、提供終了するまでに、少しでも多くの人に知ってもらいたいと考えています。 紙媒体だと、とても間に合わないのですが、ネット媒体なら、なんとかなるかも!と思い、お願いしたいと思いました。 視覚障がい者や色覚障がい者という障がいに興味がないかもしれませんが、外見では判断できない障がいなので、気付いていないだけなのです。 よか

主に高齢者や障がい者のウェブアクセシビリティを向上するため、富士通のWebサイトが「JIS X 8341-3:2010」に対応した。達成度は「AA」の評価。 富士通は7月8日、同社サイトのトップページがWebコンテンツの日本工業規格「JIS X 8341-3:2010」に対応したと発表した。主に高齢者や障がい者のWebアクセシビリティ向上が目的だという。 JIS X 8341-3:2010は、2008年12月に発表された「WCAG 2.0」に協調する形で2010年8月に公開されたもの。客観的な試験によって、アクセシビリティの達成状況を確認できることが、従来の規格とは異なる点だ。達成度は3段階(A/AA/AAA)で評価され、総務省による「みんなの公共サイト運用モデル」では、2014年度末までに「AA(一部準拠)」を達成することが望ましいとされている。今回の取り組みにより富士通のサイトは「AA

2004年6月に出された JIS X8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第三部:ウェブコンテンツ)は、2009年が工業標準化法による5年サイクルの見直しの時期にあたり、技術の進歩や、国際基準のWCAG 2.0との整合性などを考えて、2010年8月20日には改正されました。 改正版との違いを簡単にまとめると、 改正版では、WCAG 2.0(Web Content Accessibility Guidelines 2.0)との国際協調を大きな柱としているため、世界標準と共通の達成基準及び実装方法になりますが、支援技術のサポート状況などによっては、日本のユーザーに合わせた対処をしなければならない可能性があります。 改正版では、決められた試験を通して適合の有無を客観的に証明できるようになり、「JIS Q 1000 適合性評価・製品規格への自己
2010年6月11日 アクセシビリティの定義、ユーザビリティとの違い アクセシビリティ・エンジニア 中村 精親 「アクセシビリティとユーザビリティに配慮する」 Webサイトの制作において、このような文面を見かけることがあります。しかしながら、両者の違いやそれぞれを向上させる効果についてはあまり理解されていないのでは、と感じることもあります。 「ユーザビリティは考慮したいけれども、アクセシビリティはそのうち」 このような考えのWeb担当者の方もいらっしゃるようです。 これはひとつにはアクセシビリティの定義が明確ではなく、人によって認識、理解がさまざまであることに起因しているのではないかと考えています。 そこで本稿では、アクセシビリティの定義についてひとつの考え方を示し、また、混同されがちなユーザビリティとの違いを明確にすることで、アクセシビリティ向上の必要性や、その意義について考えてみたいと

Webサイトの品質維持には、リンク切れや不要なファイルを少なくすることが重要です。今回は、Webサイト品質の問題点発見とその解決へのスピードを格段に上げる自動チェックツールを8つ紹介します。日本アイ・ビー・エムが提供するIBM Rational Policy TesterやW3Cリンクチェッカー、W3Cマークアップ検証サービス、リンク切れカッター、Web Developerなどのフリーツールも紹介 数百ページ~数万ページというWebサイトでは、人的な検査だけですべての問題点をチェックするのは実質的に不可能に近い。また、ページ数が少なくても、チェック漏れがあっては意味がない。 自動チェックツールを利用することで、問題点発見とその解決へのスピードは格段に上がる。現代のWebサイトでは、理想的な品質管理を実現するには、何らかのツールの利用は必須だともいえる。 最も効率良く診断できる専門ツール手前
「みんなの公共サイト運用モデル」は、高齢者や障害者を含む誰もが地方公共団体のホームページやウェブシステムを利用することができるよう、ウェブアクセシビリティの維持・向上を実現するための取組モデルです。(全体像は以下のとおり。) このモデルは、平成16年11月から「公共分野におけるアクセシビリティの確保に関する研究会」(座長:市川 熹(あきら) 千葉大学教授)において検討が進められ、平成17年12月に策定・公表されました。
sashaです。 naoya君が前回のエントリーで振ってくれたように、ジョエルテストの話から、ユーザビリティ・テストをどこまで行うかという話になりました。 私が今まで見たユーザビリティ系の記事の中には、追求したら悟りが開けそうな、限りなく奥深いものもありましたが、適度に深く、満遍なくカバーしているユーザビリティ・ガイドライン(原文)を見つけ、以降これを参考にしています。少し前に翻訳しましたので、今日はそれをご紹介いたします。 一般ユーザー向けのWebサービスでは、全部のチェック項目が該当するわけではありません。個人的には、各項目のスコアより、「スコアの説明」という欄を重視しています。現状では何が問題であり、どう解決するべきなのか、そういった思考のプロセスが、「ユーザーのことを思うこと」だと思うのです。 いま、ウノウではフォト蔵のデザイン見直しを行っております。私たちのデザインを省み、
公開日 : 2009年1月28日 (2018年1月17日 更新) カテゴリー : アクセシビリティ 前回のコラム記事「JIS X8341-3 改正:パブリックコメント受け付け」で触れたように、2009年9月に新しく改正される予定のJIS X8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針 − 情報通信における機器・ソフトウェア・サービス − 第3部:ウェブコンテンツ」は、W3C(World Wide Web Consortium)において2008年の12月に「勧告」(Recommendation)されたWCAG 2.0(Web Content Accessibility Guidelines 2.0)という指針がベースになっています。前バージョンのWCAG 1.0が勧告されたのが1999年5月なので、WCAG 2.0は、アクセシビリティのW3C指針として、実に9年ぶりのバージョンアップということ

公開日 : 2009年11月5日 (2018年7月21日 更新) カテゴリー : アクセシビリティ 先のコラム記事「改正JIS X8341-3のベース「WCAG 2.0」とは?」で、WCAG 2.0(Web Content Accessibility Guidelines 2.0)についての概略を紹介しました。今回は、WCAG 2.0を読み解くにあたって知っておきたいこと(具体的に、どういったドキュメント体系になっているのか、どう読んでいくと良いか)について触れてみたいと思います。 WCAG 2.0 のドキュメント体系 ちょっと複雑ですが、WCAG 2.0は複数(下記の4つ)の文書で構成されています。これは、旧バージョン(WCAG 1.0)での反省を基に、「本文」の記述が将来に亘っても陳腐化しないように配慮されているからです(逆に言うと「本文」は汎用的/普遍的な記述に終始しており、具体的な

Accessibility is the Web. 「エー イレブン ワイ」は、Webアクセシビリティの情報提供Webサイト。 ユーザーフレンドリーでみんなが利用できるWebコンテンツづくりをサポートします。
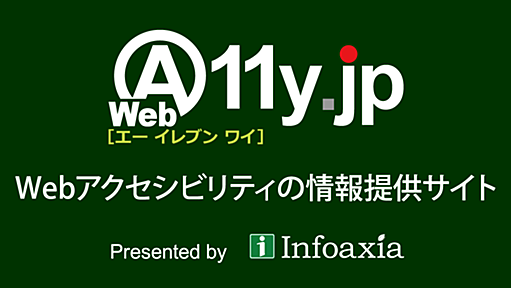
Webサイトのアクセシビリティを高めるための方法や国内外の関連情報など、さまざまな角度からWebアクセシビリティに関する話題をご提供していきたいと思います。 当Blogの更新情報は、Twitter経由でも配信しています。興味のある方はぜひ、@mlca11yをフォローしてください。当Blogへのご意見・ご質問は、Twitter経由でも受け付けております。 Blog移転のお知らせ 誠に勝手ながら、このたび当アクセシビリティBlogを移転することになりましたので、お知らせいたします。移転先のURLは http://www.mitsue.co.jp/knowledge/blog/a11y/ になります。大変恐れ入りますが、ブックマークやフィードリーダーなどの設定変更をお願いいたします。 なお、旧URL(http://accessibility.mitsue.co.jp/)は今後もご利用いただけます
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く