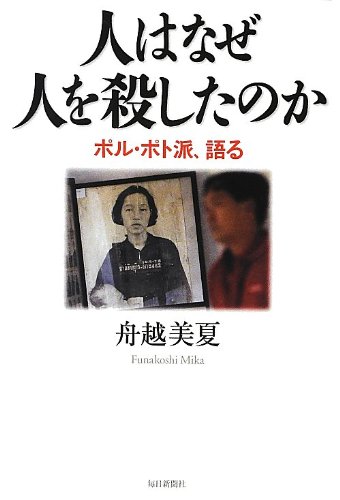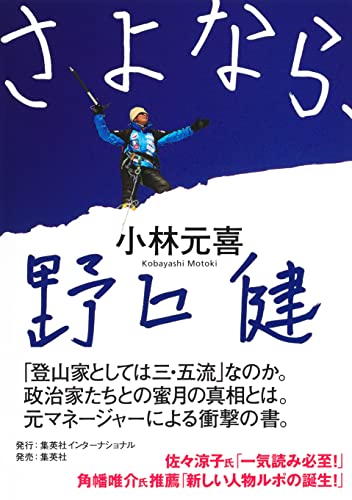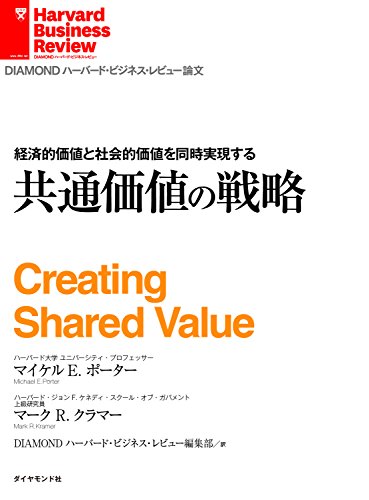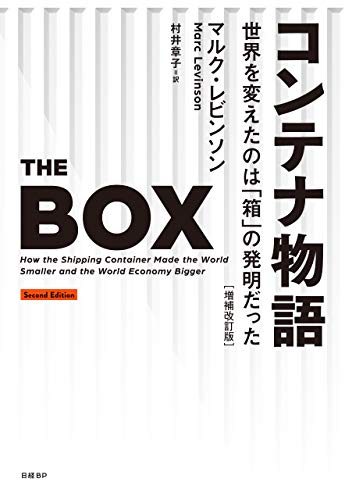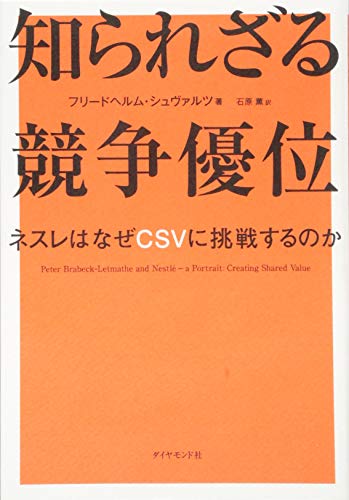googleアナリティクス 4 への移行(このブログへの設定)を何とかすませた…かもしれません(出来ていないかもしれません…)
さて、この6月に、時期的にぴったりの小説『ダロウェイ夫人』を読了したのでその感想です。

素敵な小説でした
【目次】
あらすじ
現在と過去を自在に行き来し、青春時代を回想する「意識の流れ」の文体で、クラリッサ・ダロウェイの1923年6月、第一次大戦の傷跡残るロンドンのある一日を描く。モダニズムの代表作。
(Amazon公式サイトよりの引用)
上記にまとめられている通りです。初夏の瑞々しく溌溂とした空気のロンドンを舞台に、タイトルになっている「ダロウェイ夫人」こと、保守系政治家の妻であり、裕福な家庭の夫人でもある51歳のクラリッサ・ダロウェイ視点だと「自宅でパーティーを開いた。懐かしい人々と再会して、偉いお客さんも来てくれて、無事終わった(終盤、少しばかり影がさすけれど)」…だけの話です。これで文庫本にして340ページ位の長さ。

ロンドンに梅雨はないでしょうね
独特の語り口
拙ブログで小説の感想記事は、久しぶりですね。小説に書かれた6月中に何とか読み終わろうとしていましたが、終盤では読み終わるのが惜しくなりました。
とても魅力的な小説でした。この小説は、基本全てを統括するような語り手(3人称)がいるのですが、いつの間にかクラリッサ・ダロウェイをはじめとした登場人物達が語り手となって(1人称)、その時の語り手が見聞きしたことや思ったこと、過去の記憶と、人の意識の移り変わりをそのまま描き出す手法をとっています。こういう手法を「意識の流れ」というそうです。

花屋~
例えば、クラリッサが自宅でのパーティーに飾るための花を花屋に買いに行くと、その花屋の店員に語り手が移り、その人の主観で見えている人・ものが描写されます。そんな風に、クラリッサに仕えるメイドや元カレのピーター、夫であるリチャード、そればかりかすれ違っただけの人、その場に居合わせた人、そういった赤の他人がまたすれ違っただけの人…と沢山の人が語り手となっていきます。
人間の意識なので、その時の語り手が意識する人やもの、注意の対象、感情が目まぐるしくくるくると移り変わっていく様も面白いです。「今この時・この場所(小説の本来の舞台である6月のある水曜日のロンドン)」に留まらず、何十年もの過去の記憶や、それにつながる場所を思い出したり、またその時の関係者と「今」会って話したり…1日の出来事を描いた話なのに、何十年もの時の流れの中を往還する描き方が楽しいです。
“私”はあらゆる場所に存在する
そして、家族や友人知人のみか、たまたま同じ場所に居合わせ、すれ違うだけの者同士があたかも揃って交響楽を奏でているかのような描写。まるで個々が世界という大きな歌の一節であるかのように。これが流れるような美しい文章でつづられていきます(原文も良いのでしょうが、丹治 愛氏の訳文がおそらく素晴らしい)。

公園とか~
…突然彼は目を閉じ、よいしょとばかりに片手をあげ、葉巻の重い吸い殻を投げ棄てる音、歩き過ぎる人びと、高まったり低まったりする往来のざわめきを掃き去った。下へ下へと彼は沈んでゆく。眠りの羽毛のなかへと沈んでゆき、ついにその羽毛に覆われてしまう。
ピーター・ウォルシュが陽のあたっているベンチでいびきをかきはじめたとき、隣りにすわっていたグレーの服の子守女はふたたび編み物をとりあげた。グレーの服を着、一心不乱にしかし静かに両手を動かしている彼女は、あたかも眠る者たちの権利を護る闘士のようであり、また空と木々の枝からなる薄明の森の世界に立ちあらわれる霊的存在のひとつのようでもあった。小径をたずね、羊歯の群生をかき乱し、大きな毒人参の草を踏みにじる孤独な旅人は、空を見あげると、不意に騎馬道の果てに巨大な人影を認める。(以下略)
…「どこにいるんですか?」とヒュー・ウィットブレッドはつぶやくように言った。と、たちまち、日がな一日レイディ・ブルートンのまわりに打ち寄せる奉仕の灰色の潮に、ひとつのさざ波が生じた。その潮は高まり、遮断しつつ、彼女をきめの細かい薄織物で包み、そうすることで衝撃を消し、妨害を和らげ、ブルック・ストリートの屋敷のまわりに目の細かい網を広げていた。その網にはいろいろなものがかかっていたが、三十年にわたってレイディ・ブルートンに仕えている白髪頭のパーキンズは、そのなかから正確に即座に必要な情報を拾いあげ、ピーター・ウォルシュの滞在先を書きとめ、それをミスタ・ウィットブレッドに渡した…
(以上、どちらも集英社文庫版『ダロウェイ夫人』より引用)

本作で結構重要なポジションにいるビッグ・ベン
このことは、娘時代の以下のクラリッサの言葉に端的に表されている気がします。
「自分があらゆる場所に存在している感じがするの」「あらゆる場所に」「わたしはあれ全部なのよ。だからわたしなり誰かなりを知るためにはその人を完成させている人たちを、そしてその人を完成させている場所も、見つけださなければならないのよ。一度も話しかけたこともない人、たとえば通りを歩いている女やレジに立っている男にも、私は奇妙な親近感を感じる。木々や納屋にさえ。」
作中で、ビッグベンが打つ時の音も、何らかの役割を負わされている気がします。
見え隠れする闇
上記のクラリッサの世界観?で言うと、この小説で彼女と対になる存在と言えるセプティマス・ウォレン・スミスとも、つながりがあるといえるかもしれません。
とはいえ、小説の設定では彼はクラリッサとは赤の他人と言って良い存在です(間接的に薄~いつながりはあるといえばある)。『ダロウェイ夫人』はセプティマスのある1日を描いた話とも言えます。
セプティマスは第一次世界大戦(1914年~1918年)に志願して出征し、仲の良かった上官を戦争で亡くたこともありシェルショック(PTSDのようなもの)を負っています。病んでいるので、不思議なヴィジョンを見たりします(これは神経衰弱を患っていた作者のウルフが実際に見聞きした幻覚が元になっているそうです)。
このように、『ダロウェイ夫人』では、初夏の瑞々しいロンドンの空気を生き生きと描写していますが、随所に戦争の傷跡、クラリッサが過去にスペイン風邪に罹患したこと、彼女の老いや死を意識する描写もあり、このことが小説を味わい深いものにしています。
無関係と見えていたセプティマスとクラリッサの物語は、この小説(で描かれる一日の)最後に、ほんのうっすらと交錯します。さて、それはどういった形?
これは、実際に読んでいただいてのお楽しみです…

薔薇~
『ダロウェイ夫人』は、読んでいて現世の瞬間ごとの煌めきと闇とを堪能できる、奥深く美しい小説でした。

初夏~
それでは、また!