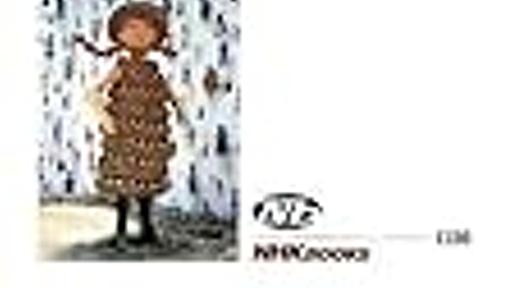あとがきによると、稲葉振一郎の勤める社会学部1年生向けの授業を元にしたとのことで、元々一般教養科目としての性質があったようで、「社会学」入門であると同時に一般教養である。 一般教養であるって、よくわからない言い方になってしまったw 全部で14講に分けられているのだけれど、本格的に「社会学」の話になるのは実は第9講から。 例えば、最初のいくつかは理論とは何かとか、方法論的個人主義と方法論的全体主義の違いについてとか、もちろん社会学と絡めて語られているけれど、より一般的な考え方の話であるし、第7講と第8講のモダニズムの話は、いわゆる前衛芸術や社会学以外の学問の話となっている*1。 大学の授業というのは、結局先生の専門をがーっと話されたりするので、1年生の時にこうやって包括的な話をしてくれる授業があるのは、大変よいのではないかなと思った次第。 社会学なのに全然社会学の話しないじゃねーかって思った