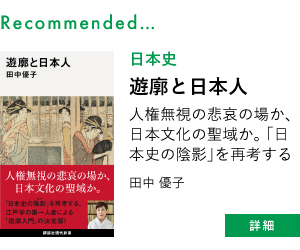日本の共働き世帯数、日本人の労働時間、日本の労働生産性、事業所の開業率……
現代の「日本の構造」、どれくらい知っていますか?
『日本の構造 50の統計データで読む国のかたち』では、少子化、格差、老後など、この不安な時代に必要なすべての議論の土台となるトピックを橘木俊詔氏が平易に解説します。
※本記事は、橘木俊詔『日本の構造 50の統計データで読む国のかたち』から抜粋・編集したものです。
貧困大国ニッポン
貧困とは文字通り、所得が低いので日常の経済生活に困るほどの状態にいることをさす。貧困には「絶対的貧困」と「相対的貧困」の2種類の定義がある。
「絶対的貧困者」とは、人が生きていくうえで、食費、衣服費、住居費、光熱費などのように最低限の生活をするのに必要な金額を設定して、それ以下の所得しかない人を貧困とするものである。
国によっては、この額を正確に定めて「貧困線」と定義しているが、日本では学問上で計算された統計的な公式の「貧困線」は、今では政府から提出されていない。昔はまがりなりにもそれを計測していたが、今はそれがなされていない。その理由は計測にさまざまな問題があることによる。
「相対的貧困者」とは、国民の所得分配上で中位にいる人(すなわち所得の低い人から高い人まで順に並べて真ん中の順位にいる人)の所得額の50%に満たない所得の人をさす。
50%は先進国が加盟する国際機関であるOECDの定義であるが、EU(ヨーロッパ連合)ではもう少し厳しくて、60%を用いている。当然のことながらEUの方がOECDよりも貧困率は高くなる。相対的貧困は他の人々と比較して、どれだけ悲惨であるかに注目している、と考えてよい。すべての国が同じ基準での定義・計測なので、国際比較の信頼性はある。