 古典的な理科の実験の疑問
古典的な理科の実験の疑問
たぶん、各世代を通じて理科の授業その他で目にしたであろう実験です。
浅い皿に水を張り、真ん中にロウソクを立て、火を付けます。
そこに、コップ(ビーカー)をかぶせるとどうなるか? という実験。
聞きたいのは次の2点
1 実験結果を覚えていますか? 特にコップ内の水面の高さについて。
2 水面が上昇するのですが、その理屈を覚えていますか?(教えてもらいましたか?)
ついでに、
3 あなたは理科という科目が好きですか?
※何も資料を見ずに回答いただけると幸いです。
正解不正解を問う質問ではないのです。あなたが覚えている通りで正解ですから、教えてください。
注意) 超真面目な質問です。ネタにしていただいてもいいですが、1と2は回答願います。
- 回答の条件
-
- 1人2回まで
- 登録:
- 終了:2018/06/01 13:15:05
回答(9件)
a-kuma3 4974
4974 2154
2154
 12pt
12pt
>1 実験結果を覚えていますか? 特にコップ内の水面の高さについて。
覚えてます。
この絵の感じならこうなるはずと。
>2 水面が上昇するのですが、その理屈を覚えていますか?(教えてもらいましたか?)
覚えてます。
ただ、実際に授業で教えてもらったか、とか、実験をしたか、という記憶がありませぬ。
あの有名な本を持っていたはずなので、そちらで知ったのかも、という気がしなくもなく。
# 載ってましたよね?
>3 あなたは理科という科目が好きですか?
今の子は、生活という科目に丸められちゃって、結局、理科の授業数が少なくなってかわいそうだなあ、と思うくらいには好きです :-)
(追記)
>水面の高さは、コップの下から1/5である。
>という説明でしたか?
記憶にないです。
答え合わせ的なやつで書いてあるところも目にしましたが、ふうん、そうかなあ、という感じ(今だから言えるのですね
先の回答で、「この絵の感じならこうなるはずと」って、わざわざ書いたのは、水がたっぷり入ってたかどうかが記憶になくてです。
libros 367
367 89
89
 11pt
11pt
1.覚えてます。かなり興奮しました。
2.教えてもらいました。ただ言葉で教えてもらうより、実験で体感するほうがぐっと体にはいってくる感じでした。
3.好きです。計算が苦手であまりよい成績をとれませんでしたが、そうでなければ理系に進みたかったです。
この実験、どれ程の認知度があるんでしょうか。
「島田荘司の『水晶のピラミッド』は何なの!? 誰もツッコまなかったの!?」と激しく問いたいんですけど。
でも、溺死する前に、酸欠・火傷・圧死その他で死んじゃいそうです。
それと、空気ベースの混合気だと、3000度は無理そうだし。
3000度はさすがに無理ですねえ。水蒸気で満たすのも蒸し焼きになりそうで無理っぽい。
ええっと、爆発的燃焼させる部屋と、被害者の部屋を隔離して、一方的に空気を抜く のは難しいでしょうか(思いつき)。
GM91 1091
1091 94
94
 11pt
11pt
1)経験なし
2)略
3)大好き
教科書には載って無いはずなので、未経験が標準かも知れませぬ。
漫画やアニメでも、見たこと無いですか?
はい、初めて見たです。
不覚。oTL
SyN 4
4 0
0
 11pt
11pt
1. 覚えている
2. 知っている
3. 小学生の頃の理科は好きな分野と嫌いな分野がありました。
科学的なことは好きでしたが、自然の観察などは嫌いでした。
ありがとうございます。
では、ロウソクの実験などは、好きな方ですね?
自分でやってみましたか?
質問者から
たけじん多少回答がありましたので、補足というか本題というか、追加の質問です。
水面の高さは、コップの下から1/5である。
という説明でしたか?
(私はこの説明で納得していました。)
みやど 1086
1086 197
197
 11pt
11pt
1 その実験をした覚えも見た覚えもありません。水を張らずにやって「火が消えた」のなら覚えています。
2 上の通り。
3 分野によります。
その実験は、燃焼ガスの上方置換だから、理科の授業でしょうか?
理科の授業です。ただし「火が消える」実験であって、ガスの捕捉としてやったわけではありません。ガスの捕捉だとしたら熱で空気より軽くなって、冷えれば今度は二酸化炭素は空気より重くなるはずですが。
ニャンざぶろう 767
767 128
128
 11pt
11pt
>1 実験結果を覚えていますか? 特にコップ内の水面の高さについて。
教えてもらったときには酸素が燃えて二酸化炭素になると体積減るとか
間違っている説明だったように思います。
1)最初にビーカーを被せたあとは
内部に閉じ込めた空気がろうそくで加熱され膨張するため
コップ下側から外に溢れ出す挙動があるはずです。
2)同時にろうそくの燃焼により、空気の20%を占める酸素成分の一部が消費されるので
ビーカー内部の気体体積が減り、コップ内に水が導入され水位は上がるはずです
3)ビーカー内の酸素が消費されてろうそくが燃えられなくなると
徐々に内部の空気温度が下がり更に水位が上昇するはずです。
>2 水面が上昇するのですが、その理屈を覚えていますか?(教えてもらいましたか?)
実は結構複雑な挙動をすると思います。
ろうそくが燃える時に、酸素は
O2→2H2O 02→CO2 の経路で消費されますが
O2(体積1)→ 2H2O水蒸気(体積2)→ 2H20常温液体(体積ほぼ0) <速やかに進行
O2(体積1)→ CO2(体積1)→ CO2水に溶解した状態(体積ほぼ0) <水に溶けるには時間かかる
つまり酸素が燃えた時点では気体体積は増える。水蒸気が凝結することで体積が減る。
燃えるのがパラフィンなら H20とCO2はほぼ1;1で生成されるので
20%体積の酸素
→ 13.3%体積のCO2 + 13.3%体積の水蒸気 (+6.6%)
→ 13.3%体積のCO2 + 少量の水 (-6.6%)
→ 水に溶解したCO2 + 少量の水 (-20%)
とプロセスが進み
最終的に空気中の酸素成分が消費されることで
内部の空気の約1/5の減った体積分水面が上昇する効果の部分と
上記1)での
加熱膨張でコップ内部で膨張していた空気やCO2が
コップが常温に戻ることで体積が減りその分内部が減圧されて
水位が上昇する分も考える必要があると思います。
と結構いろんな要素が絡んでくるんで
コップ体積の1/5の水位上昇を、一律に観察するのは困難じゃないでしょうか。
(最初にコップかぶせるときに一定角度傾けてかぶせるとか工夫が必要でしょう)
>3 あなたは理科という科目が好きですか?
はい好きですね。
そうなんです。この実験は要素が複雑なんです。
ご指摘、的を得ていて、やはりちゃんと考えられる人もいるのだと、感慨深いです。
サディア・ラボン 832
832 83
83
 11pt
11pt
1 学校では実験はしませんでした。
アニメの一休さんに出ていて、
何冊かの本でも見た事があります。
2 水面が上昇する理由は、学校で教えてもらいましたし、
本にも載ってましたし、
一休さんにも出てました。
3 理科は好きです。
一休さんの時代にそんなこと分かるわけないですね。どっちみち後生の創作でしょうけれど。
後生→後世
質問者から
たけじん水面は、全体の1/5まで上がる。なぜならば、コップの中の酸素が消費されるからだ。
が、最初に読んだ説明。小学校低学年。
あれ?二酸化炭素は?と疑問が生じたけど、注釈に、二酸化炭素は全て水に溶け、水蒸気は液体になるので、体積増加は無い。と説明があり納得。
つい最近まで、これが正しい仮説と思っていたのです。
銀鱗 65
65 9
9
 11pt
11pt
1.火が消えたことは覚えていますが、水についてはあまり記憶が無いです
2.前述のとおりなので教わったかは覚えてないです
3.ゆとりの間は大好きでしたが、今は物理以外は好き…かな…
火が消えるだけなら、学校でやったのだと思います。
水を吸い上げるのは、結構インパクトがあると思うので、覚えていないのであれば、やっていないのでしょう。
質問者から
たけじんこの水位が上昇する現象は、ミステリ作家の琴線にふれるらしく、奇妙な場所で溺死体というトリックに結びつきます。名探偵コナンでも、そんな話がありました。
でも、どんな説明をしようとも、死なないんですわ、被害者。コナン君の推理とは別の犯人がいるはず。
テレビだと、745回容疑者か京極真(後編)がそれ。ちゃんと検討すると、殺せません。
hathi 216
216 49
49
 11pt
11pt
1 実験結果を覚えていますか? 特にコップ内の水面の高さについて。
実験した記憶、見た記憶はありますし、コップ内の水面が上昇した記憶はあるのですが、どのくらい上昇したのかの記憶は残っていません。イメージ的には、コップの内部の高さの1/5~1/3~1/2のような、どうもはっきりしません。
2 水面が上昇するのですが、その理屈を覚えていますか?(教えてもらいましたか?)
たぶん理屈のようなものを説明されたのでしょうが、どんな説明があったのか、そのときの先生も、学年というか、小学校だったか、それもはっきりしません。 でも、中学で自分で実験したのを記憶しているのかもしれません。
ただ、最近、何かの拍子にその実験を想い出して、あれは大気中の酸素が燃焼で消費される実感だったと思いはじめて、それでは、つじつまが合わないので、何の実験だったのか、高さは本当に1/5~1/3~1/2のよう上がったのか、記憶自体を怪しんでいます。
3 あなたは理科という科目が好きですか?
中学のときには、化学と物理系が大好きでした。 小学校では、特に理科が好きだった記憶はないです。
4 水面の高さは、コップの下から1/5である。という説明でしたか?
実験の目的や観測結果に関して、説明があったのかも記憶にありません。
実験を想い出したときには、1/5近く上昇しておかしくないと最初思いましたが、(それでイメージもかなり水面が上昇したものに書き換わった可能性もあります)、中学のときには燃焼範囲も知っていたので、中学校で実験したのなら、もしも目に見えて水面が上昇したらそれはおかしいと自分で考えたろうと思います。 もしも、そうした実験をしたときに水面が大きく上昇したら、「高温で膨張している燃焼ガスが、ガラスで温度低下して体積縮小した結果だ」という説明を受けたか、自分で考えたろうと、今は思いますが、すっかり忘れていました。 コップをかぶせたとき内部温度が平均で300℃近い状態だったとすれば(かぶせ方次第です)、室温に下がれば、1/2まで上昇してもおかしくないですから、、、 そうすると、あの実験は、ボイルシャルルを教わったときなのかな?
-
 たけじん
2018/05/10 17:28:51
ここ数日、科学的な考え方を見直す機会を与えてくれた、この実験の手強さでグルグルしています。
たけじん
2018/05/10 17:28:51
ここ数日、科学的な考え方を見直す機会を与えてくれた、この実験の手強さでグルグルしています。 -
実は酸素は大して消費されないんです。ロウソクの燃焼条件は、1気圧下では酸素濃度15%前後まで。それ以下では火が消えるのです。
反応速度論他化学の知識があれば、その燃焼条件は考えられたのに、酸素は全部消費されると思い込んでいたんです。ほんの数日前まで。
だから、「酸素を使うのでコップの1/5まで水位が上がる」はほぼ間違いだったわけです。
どうしましょう、水晶のなんとか。 -
> ロウソクの燃焼条件は、1気圧下では酸素濃度15%前後
ああ、本当だ。酸素は全部燃えると思い込んでました。まさに目からウロコです。
「ほら水位が1/5上がったでしょ」と言わなかったうちの先生はめっちゃ誠実だったのか。 -
もっと言うと、二酸化炭素がそんなに簡単に水に溶けるんですかね。
簡単に溶けるなら、水に息を吹き込んだだけで炭酸水ができるはずですが。 -
炭酸水は、飽和量を上回って融かしこんだものです。だから、1気圧にすると、ガス化してしまいます。常温常圧では、気の抜けたコーラ程度しか溶けません。
-
こちらで「ムーミン」のチョウの変態が早すぎる件を質問しております。
http://q.hatena.ne.jp/1532738731



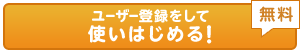

>ファラデーさんの”ロウソクの科学”には、載っていません。
2018/05/10 16:33:16おっと、そうでしたか。
じゃあ、授業でやったということなのかなあ。
学研の科学と学習は両方とも買ってもらってたので、そちらで読んだ可能性もあるかな...
回答したので絶賛カンニング中(いや、試験場から退出してるから、答え合わせ的なやつか
2018/05/10 18:10:50