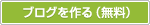ノモンハン桜はどこへ行った(8) ホルステイン河 [ノモンハン旅行]

ホルステイン河跡
ノモンハン桜はどこへ行った(8)
ホルステイン河
ノモンハン集落から程近いところにホルステイン河がある。ほとんど高低差はないもののこのあたりは分水嶺であり、ノモンハン集落から西にホルステイン河は流れハルハ河に合流する。合流点は日本兵には「三つ又」と呼ばれた。激戦地域のひとつである。
訪れたのはホルステイン河の上流にあたり、水は干上がり、葦が一面を覆っていた。草原とは異なる、というのは地面は乾燥した泥地であり、植物も葦だけが茂る。ちょうど川幅を示すのであろう、20mから50m幅で葦原は続いているのである。ホルステイン河の下流、ハルハ河への合流地点は国境に近く近寄れなかった。
緩衝地帯を設けているので国境線から10kmまでしかガイドは連れていってくれない。そのため、ホルステイン河が完全に干上がっているのかどうかは確かめられなかった。
ノモンハン集落はちょうど水源に近く、現在すむ300人の集落が水をくみ上げるので干上がっているのではないだろうか。
強い風が一方向に吹き続ける。集落に人を見かけることはない。ノモンハンは人の声のしない風音だけが笛のように鳴リ続ける草原の集落だった。
ノモンハン桜はどこへ行った(7) 建設ラッシュとバブル [ノモンハン旅行]

草原の野生にら、海拉尓は「野生のにら」という意味
ノモンハン桜はどこへ行った(7)
建設ラッシュとバブル
満州里も海拉尓の街は建設途上でいくつものビルが建設中だった。1階は商店でその上は住宅用である。地震がないのでつくりも簡単そうである。マンションは一軒20万元(約250万円)という。牧畜と牧畜加工、貿易以外に産業は取り立ててないにもかかわらず、急ピッチで建設されている。石炭は少し出るようで満州里の南に炭鉱がある。古い家々はレンガ積み平屋であり、建物全体がレンガによる朱色をしており、集落の色となっている。また必ず煙突がある。冬には石炭を燃やし暖をとるのだろう。阿木古郎(あんぐろ)の街で石炭を燃やす匂いがした。ずうっと以前、嗅いだことのある少し懐かしさもある。この匂いがあると必ず誰かが一酸化炭素中毒を警戒した。もちろん一酸化炭素が無味無臭と知識としては知っている。
新しい住宅群には煙突などない。電力かガスだろうがこれも他の街から送られてくるのだろう。もともとここにはそれほど多くの人口を抱える産業、生活基盤はない。
集合住宅は誰が買うのか、一見して疑問に思う。これはバブルとなるのではないかと日本人らでささやきあった。辺境の地なので中国政府の優遇政策があるのかもしれない。満州里はロシアとの国境貿易が盛んではあるが、数年前に比べて貿易高は減少している、沿海地域を通じた貿易のほうが有利になっているという。
満州里にはロシア人が多くいた。カラオケやホテルのサービス、商店などにも出稼ぎに来ているロシアの若い女が多くいた。ロシアから朝早く来て、中国製雑貨品、電気用品を買って日帰りするロシア人の「担ぎ屋」も多くいる。これらロシア人を相手にした商店も多数ある。最近移住したり通ったりしているのであり、戦前からの白系ロシア人ではない。看板にはロシア語が必ず記してある。ロシアからは木材、工業原料、金属材料などが輸入される。確かにこの地方には樹木が一本もない。
ノモンハン桜はどこへ行った(6) 放牧 [ノモンハン旅行]

放牧された馬
ノモンハン桜はどこへ行った(6)
放牧
草原が広がりほとんど人も人家も動物も見かけることはない。
放牧されているのは主に、羊と乳牛。ヤギもいたし馬もいた。まれに駱駝もいた。羊は小さい群れで100頭くらいから大きい群れなら1000頭近くいる。乳牛は50頭から100頭の群れだろうか。人はほとんど見かけない。
中島さんによれば、駐屯していた戦中に見たのは羊と馬だけで、馬も背の低い蒙古馬だったという。しかし蒙古馬はまったく見かけない。駱駝も減っているだろう。当時、乳牛はいなかったから、最近馬に変わって牧畜に導入された。
運搬には車がすでに取って代わっており、駱駝や運搬馬は必要ない。駱駝は手のひらが珍味だと言っていたが、実際には食用には適さない。馬は乳牛に変わっている。しかもすべてホルスタイン種であり、肉牛は見当たらない。放牧なので丸々と太ってはいない。冬には牧舎でとうもろこしを食わせるのだろうか。冬は7ヶ月ある。零下40度にも達する。羊もほとんどがめん羊である。蒙古の羊は肉用が主だったというが、見かけたのはめん羊ばかりだった。肉用の羊はよりうまいという。
中島さんによれば、乳牛と肉牛をかけ合わせれば一代限りだがいい肉牛になると言う。実際やっているかどうか知らない。これだけ放牧した乳牛が増えれば、牛のげっぷによるメタンガス増加と地球温暖化にさぞかし貢献しているかもしれない。
馬はいたが、オートバイで羊を追っている風景もみた。蒙古馬ではなく、すらりとした西洋馬の系統。ナーダムの競馬用ではないか。移動用にはほとんど使われていない。輸送はトラックに切り替わっている。牧羊犬が立派だった。毛並みは見事に美しく体つきも大きく、腹もへこんでいる。ドッグフードなど食べずに肉を喰らい駆けまわっているからであろう。
ノモンハン桜はどこへ行った(5) 草原の生活 [ノモンハン旅行]

ゲルの人
ノモンハン桜はどこへ行った(5)
草原の生活
モンゴル人は、土地を耕すことをしない。穀物や野菜を栽培しない、野菜も採集している。新巴尓虎右旗(しんばるがうき)での昼飯では、黄色い花びらを炒めた料理を食べたが、これは野生の花であった。にらも採集する。野生の草花でビタミンを補給するのが伝統的な食事だ。
耕作している土地はない。海拉尓発の列車窓から線路沿いにじゃがいも、葱畑をわずかに見かけた。それ以外に畑を見ることは一切なかった。
満州里(まんしゅうり)や海拉尓(はいらる)、阿木古郎(あんぐろ)の町では、もちろん今は野菜を買うことができる。中国の地域から野菜や日常生活用品が送られてくるのであり、市場は品物にあふれている。
街中の市場では、ピーマン、ジャガイモ、きゅうり、なす、きくらげ、セロリ、葱、香菜などの野菜が豊富にあった。種類が驚くほど多くかつ新鮮だ。当然のこと他の地方から運んでいるのだろう。
阿木古郎の住宅裏の市場には、ナス、ピーマンがあった。男が大きな包丁を手に持ち、肉の大きな塊をそのまま切って売っていた。冷蔵庫などない。ホテル一階のマーケットは近代的なものでポリスチレンの容器に分けて売っていた。スーパーマーケットスタイルである。長いナスとこれまた長いピーマンがあった。
草原にところどころ池があり、この水場で馬も羊も水を飲む。近づいてみたが泥水。まれに井戸があり、くみ上げて家畜に飲ませているところもある。草原では水脈の通るところを20mから30m掘れば水は出る。水脈にしたがって1kmごとに連なっている井戸を見た。
放牧は個人経営で国から土地を借り、広い放牧地を簡単な柵で区切り、境をとしている。夏なので農家はゲルで放牧地内を移動する。レンガつくりの家がまれに見えるが冬家畜を囲う場所だ。ゲルも家も車で数キロ走ってやっと出会えるほどにまばらに点在している。
満州里も海拉尓も阿木古郎も一歩街を出れば見渡す限り平原である。これらの街は平原のなかに忽然と姿を現す。広い平原に人工的に建設した町である。ほとんど平らな平原なのだからどこへ町をつくろうが自由に建設できそうなものである。街なかは4車線の広い道路であり、東西南北にまっすぐ伸び、そしてまっすぐ地平線に消える。
阿木古郎の街で夕食前に散歩したが、食堂はあるものの、それ以外は衣料品店、なべ・台所用品日用雑貨店、オートバイ修理店、など。喫茶店らしきものはない。食堂で牛乳出し紅茶をどんぶりで飲んだ。一杯1.5元。
7月なので午後八時半ごろまで明るい、商店は八時過ぎには閉まってしまう。
建設されているのはレンガコンクリート製の数階建てのビルばかりで、二階以上は集合住宅。田舎なので高層ではない。ビルといってもレンガ造りであり、その上に白いしくいを塗っている。地震がないので比較的簡単な構造のようだ。新たに建てられている住宅はこの集合住宅ばかりで一戸建ての建築を見かけることはない。古い平屋住宅はレンガ作りで、町の回りに点在するが、街中では見つけることはできない。
伝統的な生活様式は急速に一掃されつつある。
驚いたのは、海拉尓北のキプチャクハン遊営地のゲルである。アルミの骨組みに鉄製の扉のゲル。なかには市販の木製のベッドが2つに市販の布団が敷いてあった。放牧生活とて昔のままではない。
商店は中国語、モンゴル文字、ロシア文字で書かれている。街中であれば半地階と半一階は、商店が入っている。現地商店の看板ばかりで大都市に比べるとマクドナルドやKFCなどの看板がないのが、大きな違いである。建築の仕方の流行なのだろうか、都市から入ってきた同じ様式の集合住宅が続々と建設されている。伝統的な町は急速に姿を消している。
ノモンハン桜はどこへ行った(4) 甘珠尓廟 [ノモンハン旅行]

カンジュール廟にて
ノモンハン桜はどこへ行った(4)
甘珠尓廟(かんじゅーるびょう)
ホロン湖のある新巴尓虎右旗(しんばるがうき)から阿木古郎(あんぐろ)へいたる途上に甘珠尓廟(カンジュール廟)がある。ノモンハン戦争で日本軍が海拉尓から最初に兵を進めたところである。ノモンハン集落の北西にある。甘珠尓廟はラマ教の廟である。モンゴルにはあちこちにラマ教の廟がある。甘珠尓廟は文化大革命で破壊されたが、最近人々の寄付によって再建された。立派な建物群である。この廟も平原に突然現れる。
ラマ僧が住み、色鮮やかに飾り立ててある。靖国神社より広いであろうほどの敷地にいくつかの建物がある。黒いかわらに赤を基調に壁が塗りたてられている。千年近くにわたりモンゴル遊牧民の文化の中心であったろうし、ラマ僧はモンゴル社会の支配者であった。梅毒はラマ僧を通じて広められたと言われている。
仏塔や廟の屋根には大きな青銅製の鈴が下げられていて、不断に吹く風にゆれカランコロンカラコロンといくつかの音色が混じった、哀愁を帯びた低い音を絶えず奏でる。同じようにつくられているように見えても、鈴の形や肉厚の違いで音程や音色が微妙に異なるのであろうか。また境内では太く長い薄茶色の線香が焚かれ、細い煙がたなびくが、常に吹いている風によってたちまちのうちに消える。廟の四方は見渡す限りの平原である。
日本軍は司令部を置いたノモンハン北方の将軍廟は戦闘で破壊されたままである。今ではその跡さえないという。
ノモンハン桜はどこへ行った(3) ノモンハン戦争 [ノモンハン旅行]

ハルハ河とコマツ台地
ノモンハン桜はどこへ行った(3)
ノモンハン戦争
ノモンハン戦争は、日本軍の敗北だった。とともに日本陸軍はこの敗北を隠した。ノモンハン戦争は日本陸軍が遭遇した初めての大がかりな近代戦であった。
ほとんど遮蔽物のない広大なモンゴル平原においては、戦闘は投入する火力の勝負で決まる。強力な火砲と戦車、航空機戦力、そしてそれら戦力の連携的な集中的な動員、すなわち兵站と輸送力がこの勝敗を分ける。対抗する日本陸軍の戦術は、夜襲と白兵戦のみである。
当初、日本軍は制空権を支配していた。しかし、ソ連空軍が次々に増強されるのに対し、日本陸軍の航空機は消耗するばかりで補給されず、やがて制空権もソ連側に移った。
関東軍は虎の子の戦車師団を投入した。安岡戦車隊ある。戦車そのものの性能は、戦車砲の性能、甲板の防御性能においてソ連軍戦車に格段に劣っていた。戦闘で戦車隊の半分近くが損耗する事態になり、虎の子の戦車師団が全滅する事態を恐れて、逆に戦車隊を引き上げさせた。戦車隊は広大な草原での陣地戦において不可欠の戦力である。これを引き上げさせたのである。
ノモンハン戦争において、日本軍はソ連・モンゴル軍の圧倒的な火力の前に壊滅的な敗北を喫した。主力である第23師団は75%にも及ぶ損耗をこうむった。75%とは戦闘に参加しなかった人員をも含めての損耗率であり、実際の戦闘に参加した師団員だけからすれば90%にも及ぶ壊滅的被害を受けた。通常30%の損耗を受けると部隊としては機能しないと言われているから、いかに壊滅的敗北であったかが明白であろう。
この結果、ソ連・モンゴル側の主張する国境線が画定し、このあと関東軍はソ連・モンゴルに戦闘をしかけることはなかった。日本兵はノモンハン戦争で18000人以上戦死したが何のために死んだかまったくわからない。
日本陸軍はノモンハンの敗北の教訓を汲み取らなかった。まず、敗北自体を隠した。ノモンハンでの敗北は軍事機密とされ、ノモンハンについて語ることは禁じられた。生き残った兵たちは内地に帰ることはなく、さらに激戦地に送られた。敗北の原因は装備や戦略の前近代性にあることが明白であるにもかかわらず、公的に認められることはなかったし、対応策はとられなかった。もっとも装備の前近代性の克服は、最終的には経済力、生産力に依存しているから、簡単に克服できるものではない。作戦の非近代性はまったく省みられなかったし、批判さえされなかった。「作戦はすばらしかったが、兵が弱かった」というのである。それどころか、参謀である辻政信はこの後もガダルカナルやインパール作戦を立て、同じ敗北と犠牲を繰り返した。日本陸軍の参謀は敗戦の責任を負う必要はないのである。
ノモンハンでの敗北の教訓はなんら省みられることなく、第二次世界大戦、米国との戦争に突入する。
ノモンハン桜はどこへ行った(2) 「ノモンハン戦争」 [ノモンハン旅行]

ノモンハン戦場跡にて 不発弾
ノモンハン桜はどこへ行った(2)
「ノモンハン事件」と「ハルハ河戦争」
ノモンハンはホロンバイル平原の南端、中国とモンゴルの国境に近い集落である。ノモンハン村は戦後になってできた。現在は300人ほどが住む。戦前は集落などなく遊牧民の夏の遊営地のひとつであり、夏のあいだゲルがいくつかあっただけであった。地図にも載っていなかった。
日本では「ノモンハン事件」と呼ぶが、ソ連・モンゴルでは「ハルハ河戦争」と呼ぶ。正式に戦線布告していないから、事件あるいは事変なのである。「支邦科事変」とおなじである。「戦争にあらず、事変と称す」。
関東軍・満州国はハルハ河を国境と主張し、ソ連・モンゴル側は、ハルハ河東方10kmから20kmを国境と主張した。しかも、関東軍がハルハ河を国境と主張しはじめたのは、昭和10年くらいからである。
関東軍は、自身の主張する国境線であるハルハ河を、モンゴル騎兵軍が馬に水を飲ませるために越えたことをもって越境があったとし、攻撃をはじめたのである。脅威があったわけではない。関東軍が仕掛けたのだ。しかも、日本の国境ではない、属国・満州国の国境なのだ。
そもそも平坦な草原である。国境線が10km、20km動いたからといって、経済的にも社会的にもほとんど意味をなさない。遊牧民は馬や羊とともに国境を越えて自由に行き来していたのである。参戦した兵士のほとんどがモグラしか住まない土地だと言い、戦友は何のために戦い犠牲になったのかと述懐している。
この戦争の原因は、日本軍の陰謀的な戦略によっている。これを体現したのが関東軍の参謀である。モンゴルからチタを占領しバイカル湖南端のイルクーツクにいたり、シベリア東半分を切り取ろうという8号作戦を構想した。この構想にとって国境線の主張の違いは格好の口実である。
「ノモンハン戦争」はその手始めであった。日本軍による国境線変更の主張は、この作戦のための言いがかりとなった。辻政信や服部卓四郎らの妄想がこれを作りあげた。しかし決して辻らの個人の突発的な作戦ではない。戦前の日本の侵略的体質のなかでは、より冒険主義的な戦略を提示すればするほど、そのことによって陸軍内で、さらには日本政府内で有力な地位を占めることができたのである。それまで、また事件後も同じ行動様式で日本陸軍内の地位と主導権を獲得してきた経過がある。石原莞爾しかり、武藤章しかり、関東軍全体がしかりである。歴史全体を総括してみれば、このような冒険主義的高級軍人が次から次へと生まれてくるのは、戦前の日本の侵略的体質がつくりだした結果といえるであろう。
8号作戦の構想はこのように日本陸軍内の主導権を得るという内向きの性格を多く持っていた。関東軍の高級軍人はこれを実行する現実的な戦略も軍備もたなかったし、参謀は彼我の軍事力を測る力も作戦能力も持たなかった。唯一持っていたのは、大言壮語し人に責任を押しつける能力でる。ジューコフが言うとおり、高級軍人はまったく無能であった。
「ノモンハン戦争」は日本軍が遭遇した始めての近代戦であった。ノモンハンでの敗北は、日本陸軍が装備においても戦略・戦術においても前近代的軍隊であることを白日のもとに曝した。
しかし日本軍上層部はそれを隠し続けた、教訓を汲みとることもしなかった。
ノモンハン桜はどこへ行った(1) ホロンバイル草原 [ノモンハン旅行]

ホロンバイル草原
ノモンハン桜はどこへ行った(1)
ホロンバイル草原
2005年6月末から7月にかけてノモンハンを訪れた。
このあたりをホロンバイル平原と呼ぶ。満州里(まんしゅうり)南方のホロン湖とノモンハン西方のバイル湖からこの名はきている。
この地方の第一の印象はなんと言っても、木々さえない見渡す限りの平坦な草原である。草原は平らであるので、ジンギスハンたちは馬に乗りまっすぐに走り抜けたろう。360度視界に地平線が見える。空気は乾き緩やかな風が常に吹き抜ける。見渡す限りの草原は雪解けの後、5月から成長したものであり、短い夏に花を咲かせて10月の初雪でそのサイクルを終える。
遠くから見ると緑の絨毯であるが、近づくと地面は砂礫地にまばらに草が生えているだけだ。地面には石と砂と黒いぶどう粒のような羊の糞、牛糞がそこらじゅうにある。寝転がることはできない。糞は土に還りかけている。
木々は一本もない。年間300mmほどと雨量は少なく半年以上雪に覆われるため、樹木は育たない。草原は春から秋にかけての半年間だけであり、残りの7ヶ月間は雪に覆われる。ただし雪はそれほど積もることはない。
牧草の種類はよく知らないが、十数種類の草が混在している。日本でも見かける草々、タンポポ、野生にら、アザミ、野生の葱、オオバコなども見かけた。自然に生えるままである。野生のにらから海拉尓(はいらる)という地名になった。ちぎればにらの匂いがする。
ノモンハン桜と日本兵が呼んでいたのは、もちろん桜ではない。樹木でさえない一年草であり、多くの白い小さな花をつける。草原を何度か歩いたがこのノモンハン桜を見つけることはなかった。わたし自身見たことはない。兵士の記憶で言い伝えられていることを知っているだけだ。日本兵たちは「桜」と呼ぶことで、異国の平原のなかに日本的なものを無理に見つけようとしたのであろう。それは兵たちに応じてさまざまな種類の日本的なものであったに違いない。そしてその思い多くは草原に消えた。