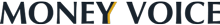記事提供:『三橋貴明の「新」日本経済新聞』2016年8月2日号より
※本記事の本文見出しはMONEY VOICE編集部によるものです
「聖域」を根底から溶解せしめる「本質的脅威」としてのポケモンGO
ポケモンGOが日本解禁になってから、10日が過ぎました。
解禁直後のメディア上での大騒ぎは少々落ち着きがでてきたようですが、いまだ路上では、ポケモン探しで徘徊する方々が、例えば我が町京都の路上でもあちこちで散見されます。
その間、少なくとも「巷」では賛否両論があれこれと論じられました。
しかしどういうわけか、(歩きスマホは危ないよ、という論点を除けば)TVメディア上では、「賛成意見」が大多数で、「いかがなものか」という論調は、筆者の知る限り(というか、少なくとも筆者が出演したTV番組では)、ほぼ皆無の状態、でした。
もちろん、一部では、「こんなことに打ち興じている人を心の底から侮蔑します」という少々過激な批判もあり、かつ、それを擁護する向きもあったようですが、
http://www.huffingtonpost.jp/2016/07/28/yaku-mitsuru-kobayashi-yoshinori_n_11234382.html
そういう批判は瞬く間にすさまじい批判にさらされてしまったようです。
http://news.mynavi.jp/news/2016/07/31/056/
この「巷」と「テレビ」の間の温度差は、かなりのもの。
例えば、楽屋で眉をひそめている方々も、オンエアになると皆さん、その批判のトーンが随分とまろやかに。一方で、ポケモンGO賛成派は「水を得た魚」の様に喜々としゃべりまくる――という情景に何度か遭遇しました。
そしてそんな風潮を逆撫でする様にオンエア中に筆者が一部批判的な事を申し上げると、共演者からちょっと普通では考えにくいような言葉で罵られたりもしました(どうやら電波にはハッキリとはのっていなかったようですが)。
ところで筆者はこれまで、「全体主義論」の研究を理論的かつ実証的に進め、その内容を例えば拙著『凡庸という悪魔』にて公衆の皆様に解説して参りましたが……
https://www.amazon.co.jp/dp/4794968191
そんな筆者から見てみれば、
「やれやれ、こんなゲームごときの話しでも、『沈黙の螺旋』が展開し、『凡庸という悪魔』が徘徊しているんだなぁ――」
と、げっそりした気分になったものでした。
もちろん、しょせん「ゲーム」の話――ではあるのですが、実を言いますと、この問題は、「日本の現代」を読み解くのに格好の「材料」になっているように思います。
ついては今回は、(これまで連続して論じてきました「大型経済対策」についての議論を一旦お休みにして)この「ポケモンGO現象」について、少々長文になりますが(4000字超!)、できるだけ簡潔に解釈してみたいと思います。