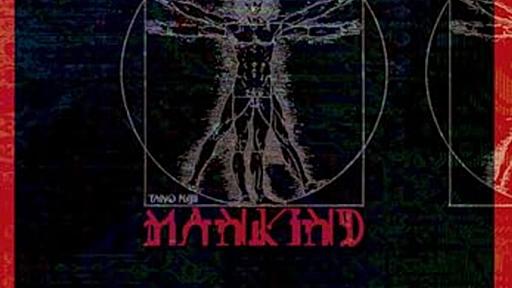ざっくりあらすじ『南総里見八犬伝』八犬士とは?さて、後編となる今回は、『八犬伝』に登場する八犬士たちのエピソードのご紹介です。 八犬士とは、伏姫(ふせひめ)の手から飛び散った8つの玉のうちの1つを持ち、後に里見家に集結することになる8人の剣士たちです。出身も性格もばらばらでキャラが立っているため、8人のうちの誰が好き?という話でファンは盛り上がりました。8人それぞれ、浮世絵や団扇(うちわ)、すごろくなどのグッズ展開もされています。個性豊かな八犬士を演じる歌舞伎の役者もまた、話題となりました。 八犬士たち(画像タップで拡大できます)仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌八犬士が持つ玉にはそれぞれ、儒教における八徳「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の文字が浮かんでいます。そして玉を手に入れた剣士たちに共通するのは、「犬」の名字を持ち、体のどこかに牡丹(ぼたん)の花の形のアザがあることです。 すべてのは