ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有


『大航海』と『潮』と『熱風』と『中央公論』が同時に送られてきた。 白川静論、関川夏央さんとの対談、貧乏論、諏訪哲二さんとの対談である。 『大航海』と『熱風』は一般書店ではなかなかみつからない媒体であるから、読者サービスとしてここに掲載することにする。白川静論は25枚。ちょっと長いよ。では、どうぞ。 白川先生から学んだ二三のことがら 白川静先生は、私がその名を呼ぶときに「先生」という敬称を略することのできない数少ない同時代人の一人である。私は白川先生の弟子ではないし、生前に講筵に連なってその謦咳に接する機会を得ることもなかった。けれども、私は書物を通じて、白川先生から世界と人間の成り立ちについて、本質的なことをいくつか教えて頂いた。以下に私が白川先生から学んだ二三のことがらについて私見を記し、以て先生から受けた学恩にわずかなりとも報いたいと思う。 私が白川先生に学んだ第一のものはその文体であ
4月にリニューアルされソーシャルブックマーク機能を備えた「Yahoo!ブックマーク」の登録人数が、Yahoo!検索結果の各URLごとに表示されるようになった。これによりサイトを訪問する前にユーザーからの人気度をある程度把握することができる。 検索結果のURL右横に表示されている「○人が登録」というリンクをクリックすると、そのURLを登録している「人気のタグ」「利用者名」「コメント一覧」「URLにリンクを貼っているブログ一覧」などの情報を閲覧できる。 また、すでに登録済みのURLには、Yahoo! JAPAN IDでログイン時にYahoo!ブックマークの登録済みアイコンが表示される(上記画像で表示されている赤い星のアイコン)。

善の研究 <全注釈> (講談社学術文庫) 作者: 西田幾多郎,小坂国継出版社/メーカー: 講談社発売日: 2006/09/08メディア: 文庫購入: 2人 クリック: 42回この商品を含むブログ (26件) を見る 西田幾多郎『善の研究』(1911年)と言えば、岩波文庫か、岩波版・西田全集を紐解くのが普通だった。 ところが、昨年に、西田研究者の小坂国継さんの注釈がついた『善の研究』が講談社学術文庫から刊行された。 難読の漢字にルビが振られ、各種の哲学用語・哲学者についての注釈と各章解説が巻末ではなく、本文中に挿入されている。西田哲学をこれから学ぼうとする学生にはうってつけ。学生時代に、こういう本があれば嬉しかった。 昭和11年、改版時の序文より。西田の文章は独特のリズム感があり、格調が高いと思う。 フェヒネルはある朝ライプチヒのローゼンタールの腰掛けに休らいながら、日麗らかに花薫り鳥歌い蝶

トランスコスモスは6月11日、先端情報技術分野において、創造性とリーダーシップを発揮する人材の育成支援を目的とした社会貢献活動の一貫として、東京大学と共同で産学連携教育プログラムを展開すると発表した。 同プログラムは、2種類の演習と奨学金制度で構成。研究テーマやビジネスモデルのアイディア発掘から、それを具現化するための研究活動までを一貫して支援する。 第1弾は、プロジェクト演習「イノベーションケーススタディ」として、7月3日と10日の2日間、東京大学大学院工学系研究科・技術経営戦略専攻において、イノベーションサービス開発事例を題材とした講義を行う。 さらに、「米国IT企業視察プログラム」として、受講者から選考された学生20人程度を9月下旬に、米国シアトル、サンフランシスコ、シリコンバレーを視察する海外研修を実施する。 また、東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻(AIS)に入学を予定し

Googleはプライバシーと対立し、ユーザーを監視している――英プライバシー擁護団体Privacy International(PI)が6月9日、このような調査結果を発表した。 同団体の調査報告書「Privacy Ranking of Internet Service Companies」の2007年版(暫定版)では、AmazonやApple、Google、Yahoo!、Microsoftなどのネット関連企業が消費者のプライバシーを十分に保護しているかどうかを調べている。 PIはプライバシーポリシーや新聞記事、政府機関への提出書類などの公開されている情報を、企業の現・元スタッフによる情報、技術分析などを元に各企業のランクを決定した。ランクは「プライバシーを保護し、強化している」から「消費者を広く監視し、プライバシーと対立」まで6段階にわたる。 Googleはこの調査で最低ランクの「消費者を

「タダより怖いモノはない」とたたき込まれてきたのだが・・・。また「安かろう悪かろう」とも言われてきた。 なのに最近,有料サービス/製品に劣らないモノが,タダで手に入るのはどうして? この問いに答える書籍を,ロングテール理論の提唱者クリス・アンダーソン氏が書き進めている。タイトルも,ずばり“FREE”とか。彼のベストセラー“The Long Tail”は,ほとんどを“タダ”でダウンロードできるようにした。となると次作の“FREE”も“タダ”で読めるのでは・・・。 ともかく,ネット上のサービスやコンテンツは“タダ”が当たり前。言うまでもなく,Googleは無料サービスを次々と世に送り出している。 コンテンツもほとんどがタダ。有料化できるのは,よっぽど待てない金欲,色欲に関するコンテンツか,非常に有益で面白いニッチなオンリーワンコンテンツくらいか。いくら優れたコンテンツでも,代替となるモノが地球
最近知人から「小学生に見せる面白い実験ない?」みたいな話を向けられました。 見せて面白いとなると、やはり「科学マジック」的というか、ちょっと不思議に感じるような現象がいいでしょう。 検索してみると、出るわ出るわ。 どうやら日本の理科教育振興の主力武器の一つのようです。 まあご多分にもれず私もこういうのは大好きで、子供の頃はウチでいろいろ試行錯誤して台所を汚したもんです。 ただ改めて科学教育という観点から考えてみると、「科学マジック」は必ずしもよい影響ばかりとは限らないような気がしてきました。 科学マジックを教育に使う場合、大まかには 1. 面白い、不思議な現象を見せる 2. ここには実はこんな法則が隠れているのです 3. 科学ってスゴイですね という流れになると思います。 ところがこれ、よく考えるといわゆる「水伝」の構造とそんなに変わらない。 1. 水に声をかけると物が腐らない 2. 実は

「感情労働」時代の過酷 以下の「「感情労働」時代の過酷」の記事は現代の傾向を象徴しているのではないだろうか。 「感情労働」時代の過酷 (AERA:2007年06月04日号) http://www.asahi.com/job/special/TKY200706050068.html 看護の領域などで知られる、「感情労働」という言葉がある。「肉体労働」「頭脳労働」と並ぶ言葉で、人間を相手とするために高度な感情コントロールが必要とされる仕事をさすものだ。・・・平たく言えば、働き手が表情や声や態度でその場に適正な感情を演出することが職務として求められており、本来の感情を押し殺さなくてはやりぬけない仕事のことだ。・・・そしてここにきて、この「感情労働」があらゆる職種に広がり始めている。 ・・・「ひと相手の仕事は昔からあっただろうと、働く側の問題点を指摘する声もありますが、一概にそうではないと考えま

コラム〜リサーチャーの日常 人生を通じてマッチクオリティーを追求する 知識の幅が最強の武器になる という本で初めて知った「 マッチクオリティー 」という言葉は、経済学の用語で、ある仕事をする人とその仕事がどれくらい合っているか、その人の能力… 2021.05.04 2021.05.13 311 view 3.ビジネスリサーチの報告書作成 聞き手の頭に入りやすい資料作成〜聞いて理解する人と読んで理解… 【 相手に合わせた 資料作成 】最初に結論を述べてから、それを裏付けるデータを提示するという構成は、欧米流のロジカルシンキングの基本になっていますが、日本のビジネスパーソ… 2021.02.03 2021.05.13 974 view 1.ビジネスリサーチの基本・心構え すべては「依頼」から始まる〜社内リサーチャーと社外リサーチャ… 【 リサーチャー とは 】企業で企画系の仕事をしていると、上
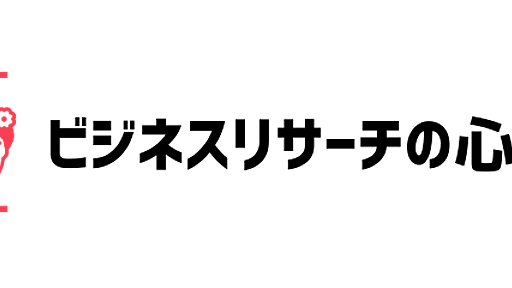
2007年06月12日 共感を求める場で、違った価値観の表明は「思いやりに欠ける」 ムラ社会だとか、女同士のコミュニケーションとかそういった括りで語るつもりはない。しかし、タイトルのように考える人は存在するし、シチュエーションによっては誰しもが持っている一面であろう。勿論、男にも女にもだ。 b# - 好きなもののことを語る気持ち 共感を求めているのであり、意見は求めていない 前回のエントリについて言及を頂いた。 「~が好き」といった直後に「私は好きじゃない」といったように,全く違う価値観を示すのはちょっと思いやりに欠けるような気がする。盛り上がりに水を差してる気がする。「なぜ,それを今いうの?」と思う。 b# - 好きなもののことを語る気持ち幾度となくどこかで小さな話題となる「悩みごとを相談する時、相手は答えを求めていない」といったようなとこだろうか。 疑問なのは、自分の好みを表明すること
なぜだろう。feecleのせいかな、他の個人的(性的)な気掛かりのことか。よくわからない。twitter的なものはなにかネットの意識を変えるのだろうか。あるいは今頃私はmixi的なネットワークの領域に入ってきたのか。なんとなくだが、はてなをはじめたころの親密さの感覚もある。 はてなが変わってきたのかもしれない。ぶくまについては批判はない。どうにでもなればいいんじゃないかと思いつつ、じゃ、自分ではどう思うかというと、あまり関心が持てなくなりつつある。 増田は? 増田もなんかテンプレ化してきているように思う。話題のテンプレというより、参加数のシュレショルドと実際には、Mr/Miss増田というかコアが生まれつつあるのだろう、そのあたりの活動が臭いというかうるさいというか。そのあたりは、増田から出たらいいんじゃないかとも思う。たぶん、増田はシステム的ななにかの工夫が必要なんだろうと思うがそれがなん

松岡農水大臣の自殺について、石原都知事が、「死をもってつぐなった。彼もやはりサムライだった」という意味のことを言ったのだそうで、この発言に対して、様々な波紋が広がっている。 「どこがサムライだよ」 「美化すんなよ」 「恥ずかしいことをして、黙って死ぬのがサムライなのか?」 と、まあ、ふつうに考えれば、上記のような感想を抱くのも、当然といえば当然だ。 でも、言った人が石原さんである以上、ふつうに考えてはいけないのだと思う。「サムライ」みたいな言葉について、石原先生のような人は、一般人であるわれわれが考えるよりもずっと深いところでものを考えていたはずなのだからして。とすれば、彼の言う「サムライ」は、ただの「サムライ」ではない、と、そう考えなければいけない。 「サムライ」という言葉を、一般的によく使われている意味で、「誇り高い」、あるいは、「出処進退のきれいな」という意味で解釈すると、知事のコメ

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く