

スペック低くても「問題ない」 日本マイクロソフト、文科省“子ども1人にPC1台”対応パッケージ提供(1/2 ページ) 日本マイクロソフトは2月4日、教育用のPCやクラウドサービスなどを一般向けより低価格で提供する「GIGAスクールパッケージ」を教育機関向けに発売した。文部科学省の掲げる“子ども1人にPC1台”施策に準拠したノートPCや、「Office 365」など教育関連サービスを全国の自治体や私立学校などに提供し、教育分野でのさらなる市場拡大を狙う。 【修正履歴:2020年2月4日午後6時22分 事実に基づきタイトルの一部を修正しました】 文部科学省は2019年12月、「GIGAスクール構想」を発表した。児童生徒一人一人に合わせた教育を実現するため、23年までに全国の小中学生1人にPC1台を用意することや、学校の通信環境を整備することなどを目指している。1月30日には、PCや校内LAN工

政府は2019年12月5日、教育用ICT(情報通信技術)環境の整備拡充などを盛り込んだ総額26兆円規模の総合経済対策を閣議決定した。注目すべき対策が、義務教育課程である小中学校への大規模なパソコン導入に向けた予算措置だ。国内PC市場がまるごともう1つ生まれるほどの規模だが、パソコンメーカーには単純に喜べない事情がある。 整備の目標について政府は「全学年の児童生徒1人ひとりがそれぞれ端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指す」と対策に盛り込んだ。 小中学校に在籍する児童・生徒数930万人に対し、現在の教育用PCの導入台数は160万台と普及率17%にとどまる(2019年3月時点、文部科学省調べ)。新たな経済対策により教育現場で短期に導入される新規のPCは約770万台となり、更新も含めれば1000万台に達する可能性がある。 国内PC市場(MM総研調べ)は2018年度実績で1183万台。国内市
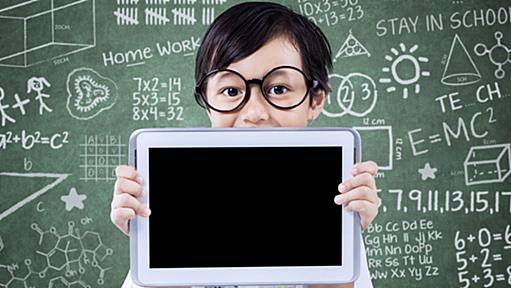
アーカイブ2022年8月 (1)2022年2月 (1)2021年11月 (1)2021年9月 (1)2021年5月 (1)2021年3月 (1)2021年1月 (1)2020年12月 (1)2020年11月 (2)2020年10月 (3)2020年9月 (1)2020年8月 (3)2020年7月 (1)2020年6月 (2)2020年5月 (4)2020年4月 (2)2020年3月 (2)2020年2月 (1)2020年1月 (1)2019年12月 (4)2019年11月 (3)2019年10月 (5)2019年9月 (4)2019年8月 (5)2019年7月 (6)2019年6月 (7)2019年5月 (7) はっきり覚えていないのだが、たぶん20年前のことだと思う。S・アール・エスとIフォレストが協業を始め、Sくらインターネットができた直後ぐらいの話だ。 土曜日だったか、日曜日だったか

[東京 18日 ロイター] - 13日に開かれた経済財政諮問会議で、安倍晋三首相が教育現場でパソコンが1人に1台ずつ普及するのは当然との見解を示していたことが、18日公表された議事要旨で明らかになった。政府の経済対策に盛り込まれる公算が大きそうだ。 【図解】在任歴代最長へ、アベノミクスの成績は 会議では柳川範之議員(東大教授)が「全国的にしっかりICT(情報通信技術)環境を整備し、全自治体の教育現場でIT端末の利活用が推進されるようにすべき」と提唱。議長を務める安倍首相は「パソコンが1人当たり1台となることが当然だということを、やはり国家意思として明確に示すことが重要」と強調した。 首相が策定を指示した経済対策では、学校用パソコンの普及も案として議論されている。[nL4N27V2LS] (竹本能文)

リンク HANPEN-BLOG 規格的にアウトなUSB Type-C変換アダプタが売られている話 USB Type-CをUSB Standard-Aに変換するアダプタは規格的にアウトです。 133 users 147

台湾ASUSTeK Computerは9月3日(現地時間)、独ベルリンでAndroid搭載の7インチタブレット「ASUS MeMO Pad 7」を発表した。発売時期、地域、価格などは発表されていない。 ASUSは、米Googleのオリジナルブランドタブレット「Nexus 7」のメーカー。昨年6月にはNexus 7よりややスペックが高い「MeMO Pad HD 7」を発表した。新モデルは、さらにスペックが上がり、薄く、軽くなっている(記事末にスペック比較表を付けました)。 前モデルの丸みを帯びたデザインから一転してシャープな、“クラッチバッグ(女性がパーティーなどで手にしている小型のハンドバッグ)にインスパイアされた”デザインになっている。 プロセッサは64ビットのIntel Atom Z3560(1.83GHzクアッドコア)なので、64ビット対応の「Android L」にアップデートすれば

「ようやくスタートラインに立てた」――ソニーのPC事業を引き継いだ新会社「VAIO株式会社」が7月1日に発足した。当面は国内限定で事業を展開。第1弾として同日、「VAIO Pro 11/13」などソニーから引き継いだ2シリーズ3モデルを、通販サイト「ソニーストア」で発売した。 社長に就任した元ソニーの関取高行氏は、「いたずらに価格競争に陥らない」と、高付加価値製品に注力することを示唆。2015年度の販売台数目標は「年間30~35万台」になると述べた。 ソニーの13年4月期のPC販売台数はグローバルで560万台。新会社の販売台数はその5~6%に激減することになる。販路も「ソニーストア」のみに絞り、ソニー時代より規模を大幅に縮小して早期の黒字化を目指す。 人員数はソニー時代の4分の1以下 「早くて変化に強い組織」 VAIO株式会社は、日本産業パートナーズ(JIP)がソニーからPC事業を引き継い

MM総研が5月21日に発表した2013年度(13年4月~14年3月)の国内タブレット端末出荷台数は、前年度比30.5%増の748万台だった。10年度にタブレットが登場して以来の倍増ペースが続いていたが、ここに来て落ち着いた。 OS別シェアではAndroid(45.7%)がiOS(43.8%)を抜き、初めて1位に。3位のWindows(10.5%)は、通期出荷台数で初めて2けたシェアを獲得した。 メーカー別シェアは4年連続でAppleが1位(43.8%)。2位はGoogleと共同開発した「Nexus 7」や自社ブランド端末を展開するASUS(17.4%)、3位は富士通(6.7%)、4位はソニー(5.8%)、5位はAmazon(4.9%)だった。 回線別ではWi-Fiタブレットが67.0%、セルラータブレットが33.0%と、Wi-Fiモデルの比率が上昇傾向に。画面サイズ別では9インチ未満が61

英非営利団体のRaspberry Pi Foundationは4月7日(現地時間)、超小型コンピュータユニット「Raspberry Pi」の新製品「Raspberry Pi Compute Module」を6月ごろに発売すると発表した。SO-DIMM型基板に最小限のチップを実装した小型版で、産業用途などを想定している。 ノートPCなどに使われるメモリモジュールSO-DIMMの基板に、プロセッサとしてBroadcomのSoC「BCM2835」と512Mバイトメモリ、4GバイトeMMCフラッシュメモリを搭載。Rasberry PiをSO-DIMM型に凝縮した格好で、汎用SO-DIMMコネクタを使ってさまざまなシステムを設計できる。価格は100個ロット時で30ドル程度になるという。

米GoogleのオンラインショップGoogle Playの日本版に1月20日、台湾AcerのChromebook、「Acer 720 Chromebook」が登場した。「近日発売」となっており、価格はまだ不明だ。米国での販売価格は249ドル(約2万6000円)。 日本でChromebookが一般向けに発売されるのはこれが初だ。 【UPDATE】1月21日午前7時現在、Acer 720のページは「Acer C720 Chromebook はお住まいの国ではご利用いただけません。」に変わっている。 Chromebookは、Googleが2010年12月に発表した「Chrome OS」搭載のNetbook。アプリケーションやユーザーデータのほとんどをクラウド上で提供するため、起動時に多様な設定を読み込む必要がなく、起動後数秒でアプリを利用でき、どこからでもデータにアクセスできるのが特徴だ。 Ac

米マイクロソフト(MS)社のパソコン用基本ソフト(OS)「ウィンドウズXP」のサポートが来年4月に終了するのを前に、関連業界がパソコン買い替えを促すサービスや、ウイルス対策の強化を打ち出している。国内ではXP搭載のパソコンがまだ相当数使われているとみられる中、ボーナス商戦を控え、特需への期待が高まっている。 XPは平成13年発売の“12年選手”。データ処理速度の遅いパソコンでも動かしやすいため根強い人気がある。ただ、サポート終了後はウイルス対策などが施されなくなり、「データが盗まれるだけでなく、サイバー攻撃の踏み台に使われ、周囲も危険にさらされる」(MS)恐れがある。 XPを使っている古いパソコンでは新しいOSに対応できず、安全性を保つには本体の買い替えが必要となる。調査会社IDCジャパンの推計によると、6月末時点で国内のXP搭載パソコンは法人向けだけで約1080万台にのぼり、大きな買い替
HGSTは11月4日、クラウドストレージや大規模データセンター向けに6Tバイトの3.5インチHDD「Ultrastar He6」の出荷を開始した。 ヘリウムガスを充填した業界初のHDDシールドドライブ。空気の7分の1の密度であるヘリウムガスで満たすことでプラッタの回転を円滑にし、従来製品と同じ厚さながら7枚構成による大容量化を実現した。 4Tバイトの3.5インチHDDと比較した場合、アイドル時で約23%、1Tバイトあたりで約49%省電力化しているという。密閉構造のため、液冷方式の冷却も可能。 ディスク回転数は7200rpm、データバッファ容量は64Mバイト、質量は約640グラム。 関連記事 HDDの記録密度をさらに2倍に HGSTがナノテク新技術 ナノテクを駆使してHDDの記録密度を2倍に高める新技術をHGSTが開発。 日立GSTが新社名「HGSTジャパン」に Western Digita

東芝は、パソコンに内蔵されているハードディスクドライブ(HDD)の故障を最大3カ月前に予知する技術を開発した。166万台分の稼働データを分析し、故障するまでの経緯をパターン化。読み込み速度の変化やエラーの回数など43項目を調べて故障の可能性をはじき出す。 東芝は2008年から自社製のノートパソコンにHDDの動きを細かく記録するソフトを入れており、利用者の同意を得てデータを集めた。HDDは様々な情報を記録するパソコンの重要部分で、故障を予知できれば事前に修理に出したり、データを保存しておいたりできる。 東芝は13年度中に、有料で故障を予知する企業向けサービスを始める。将来は個人向けにもサービスを提供するという。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く