EnterpriseZine(エンタープライズジン)編集部では、情報システム担当、セキュリティ担当の方々向けに、EnterpriseZine Day、Security Online Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。


3省が集まって電子書籍について議論している。電子書籍のフォーマットについて世の中的にはePubでまとまりつつあるが、SONYとAppleではDRMが違い保護されたコンテンツについての互換性がない。どの端末もDRMのかかっていないPDFは読めるが、文字の大きさに応じて流し込みを変えることはできない。日本語処理ではルビ、禁則、縦中横の扱い等に課題があるし、マンガを美しく表示するにはベクタグラフィクスも欲しい。 そういう意味じゃ電子書籍の規格が分断していることによる問題は確かにあるけれども、役所が乗り出したところで音楽の時のように特許の藪が絡んだDRMの一本化までは望むべくもなく、実際のところ何をどう統一しようとしているのかが見えない。理論上はDECEのようなDRM相互運用性の枠組みを応用すれば、電子書籍でも本棚ポータビリティを実現できる可能性はあり、出版社による協力の必要な領域ではあるのだが。
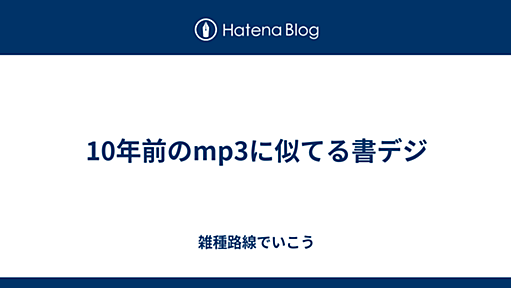
ライターを続けつつブログも書く者として意識して使い分けている。商業メディアでは妙なことを書くと媒体の責任になるから、記事も慎重に書くし編集のチェックも厳しい。ブログは個人の責任で書くものだし、厳密な裏取りはせず、素早くさらっと書く代わりに、ネタ元を明らかにした上で不確実な事柄は断定を避け、指摘に対しては迅速に対応する。記事に対する反響や、誤りを修正するプロセスを通じて自分自身が事実に近付くことを期待している。今回も元記事を書いてこそ、虚偽もあったがTwitterや2ちゃんねるへの書き込みを知り、最終的に元の音声まで辿り着くことができた。 そういった手法そのものが無責任だという指摘もあるが、限られた時間とリソースでタイムリーに物事を論ずるには現実的な方策ではある。終風翁のように一次情報が開示されずとも推論で嘘を見破れる方もいらっしゃるようで、試行錯誤を通じて騙され難くなりたいとは思う。一方で

id:shi3zの乱暴な物言いは彼の個性で別に不快ではなかった。id:lalhaの私を慮ったフォローは嬉しかったが、クズ云々で話がそれて大事な議論が途中で吹き飛んでしまったのは残念だ。しこたま金霧島やら赤霧島を飲んで酔っ払って論うには微妙な話題だし、僕も言葉足らずだった。僕もブログは正義を執行する道具として不向きだと感じているが、公開可能な範囲で考えていることを整理してネット界隈のフィードバックを得る道具としては、そこそこ機能するのではないか。 「ブログやら報告書やらを書いただけで"俺はやるべきことはやった”などと主張するのは自己満足もいいところだ。そんなもの、意思決定が実際に可能な人間は誰も読んでないし、意思決定が可能な人間にいくら技術的な話をしても無意味。それどころかそれを公然と指摘することで潜在的なリスクを増大させることが害悪だ」 僕は未知の脆弱性や未公表の脆弱性情報について、ブログ

P2Pを通じた児童ポルノ流通は、現行児童ポルノ法で児童ポルノの配布として既に違法化されているし、著作物にしても送信可能化権で手当てされている。問題はP2Pを通じた児童ポルノ流通が法規制されていないことではなく、違法であるにも関わらず法執行できていないことだ。仮に新法でP2Pを規制したところで児童ポルノの配布が違法性阻却される訳ではないし、いずれにしても被疑者の故意性は裁判所が判断することになるだろう。 Winny等の利用者に限定して、児童ポルノが共有状態になることを回避する義務を課し、その回避義務に違反した行為を過失犯として処罰する方法が考えられるのではないか。 問題はP2Pやワームを通じて現に権利侵害情報が流通していることであり、これは立法を通じた違法化によって実態として改善される訳ではない。既知の違法なファイルについてアンチウイルスと同様の手法でサーバーや端末が識別することは技術的に難

ネット上にあふれる児童ポルノ対策として、警察庁は、ネット利用者が違法なサイトを見ようとしても接続できなくする「ブロッキング」制度を民間のプロバイダー(接続業者)が自主的に運用できるよう、6月2日にプロバイダーなどと協議会を発足させる。 違法サイトの画像がネット利用者に次々にコピーされ、他のサイトに転載される現状に歯止めをかけるのが狙い。来年度にも官民共同で実証実験を始め、技術的な課題などを検討する。法整備の遅れから、児童ポルノ対策の「後進国」と国際的に批判されている汚名を返上できるか注目される。 「これは、あの時に撮影された映像じゃないか」 昨年9月、神奈川県警が児童ポルノ投稿サイト「さくらんぼ女学院」を摘発した時、捜査幹部は、投稿されている動画の一つに見覚えがあることに気づいた。 同県警は2005年3月、児童ポルノを撮影した男を児童福祉法違反容疑で逮捕した。問題の動画に映っていたのは、こ
ハックルの中のひとは結局はてブをどうして欲しかったんだろうね。あれから諸々考えたんだけれども、できることって大してないよね。まあ、/.のモデレーションとかも考えられるけど。で、ひとが傷つくのって文脈無視の罵詈雑言よりは、的を射た批評的言説だと思うわけですよ。分かってるだけに傷つく、みたいなさ。そういうのって書きようによっちゃ名誉棄損に当たる場合もあるけれど、そうでもない場合だって多いし、違法有害情報をみつけたら消しましょう、みたいな話じゃないんだよね別に。 終風翁といい池田信夫氏といい、東浩紀氏といい、書けばブクマの集まるはてブリッチが、群がってくるネットイナゴに批判的だったけれど、ネガコメの書き捨て的な側面とか、ネガコメ野郎に限って妙に上から目線であることは気に障るけれども、あまり思いつめるようなものでもないな、とも思う。だいたい気にしなきゃいいんだし。 けど実際問題として気にしてしまう

今月のトリレンマ。この問題は4年近く前から巻き込まれた縁もあってパブコメを書こうとも考えたんだけど、パブコメ対象となっている約款改正そのものは別に突っ込みどころがないんだよね。中身を説明している別紙1は諸々考えさせられるのだけれども。 という訳で解説記事を書くことにした。ポジショントークとしてはお願い僕の仕事を増やさないで!IPv6 Prefix NATはトラブルのもとになりそうだからやめて!10GPONを議論している時代にPPPoEってボトルネックにならない?とか。 総務省のインターネット政策懇談会などで数年間かけて議論されてきた次世代ネットワーク(NGN)とインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)との相互接続方式を巡る調整が最終局面を迎えている。2つの方式が検討されているが、それぞれに一長一短がある。

時に殺伐としたネガコメとかあるし、それが響き合っちゃうし、自分も凹まされることあるからねえ。けど書いたエントリがホッテントリに入ると嬉しいし、励まされつつ時に傷つく、みたいな。ネガコメが理由でユーザーの退会騒ぎとか既に起きているし、いずれ誰かが自殺しても別に驚かないよ。で、そんときはてなが道義的責任を問われるかについて、遠からず真面目に考えなきゃいけないのかな。 本来はカッターほどだった言葉の殺傷能力を、サバイバルナイフくらいに、あるいは日本刀ほどに増幅してしまう力が、インターネットには、中でも取り分け「はてなブックマーク」にはある。 だから、そこを管理運営しているはてなという会社には、実はとても大きな責任があるのだ。そこで事故が起きないように気をつけたり、誰かが誰かを傷つけたりしないよう見張っている道義的、かつ社会的責任があるのだと、ぼくは申し上げたのである。 はてなブックマークは仲介者

残念なことに日本社会では理知的でフラットな議論は相手を選ばないとできない。そしてブログは公開する相手を選べない。Webがそういう同調圧力を飛び越えて個を確立するツールとなることを期待してはいるが、今のところ日本語圏ではネット上に別の世間をつくって新たな同調圧力を増幅させているかにみえる。 例えば日本語のブログで或る予算の使い途について課題を整理しつつ建設的な提案をしても「このエントリーを財務省が読んだら仕込んでいる政策玉に予算が下りない」とか勝手に慌てて国会議員に報告がいき、取引先のお偉方から勤務先の役員に「こんなことを書く社員を放置していると、御社はこの案件から外されますよ」とか丁寧にご注進して下さる。それが日本的ムラ社会の現実だ。 たまたま話の分かる役員なら「ちゃんと個人的な意見と断っているし、正しい当たり前のことしか書いてないじゃん」で済むとして、普通の日本企業じゃ「正しいか否かの問

ネット上にあふれる児童ポルノ対策として、警察庁は、ネット利用者が違法なサイトを見ようとしても接続できなくする「ブロッキング」制度を民間のプロバイダー(接続業者)が自主的に運用できるよう、6月2日にプロバイダーなどと協議会を発足させる。 違法サイトの画像がネット利用者に次々にコピーされ、他のサイトに転載される現状に歯止めをかけるのが狙い。来年度にも官民共同で実証実験を始め、技術的な課題などを検討する。法整備の遅れから、児童ポルノ対策の「後進国」と国際的に批判されている汚名を返上できるか注目される。 「これは、あの時に撮影された映像じゃないか」 昨年9月、神奈川県警が児童ポルノ投稿サイト「さくらんぼ女学院」を摘発した時、捜査幹部は、投稿されている動画の一つに見覚えがあることに気づいた。 同県警は2005年3月、児童ポルノを撮影した男を児童福祉法違反容疑で逮捕した。問題の動画に映っていたのは、こ
第二類医薬品のネット販売が向こう2年間は認められることになった。とりあえずめでたい。この猶予期間を使って本人確認の強化、医療機器との連携など、薬局店頭よりも安全な販売を目指していけるといいんじゃないかな。 追記: コメントにあるように、ごく一部が例外的に認められたに過ぎない。詳しくはケンコーコム等による行政訴訟の記者会見を津田さんがtsudaっている。 市販薬のインターネット販売を規制する省令を公布したものの、ネット事業者などの反対を受け、一部の販売を2年間に限り認める改正省令案をまとめた厚生労働省は22日、来週改正省令を公布する方針を固めた。6月1日に施行する。 改正省令は風邪薬や漢方薬など、副作用リスクが中程度の「第2類医薬品」については、同じ業者からの継続購入者に限り、インターネットや電話を通じた通信販売を2年間認める内容。
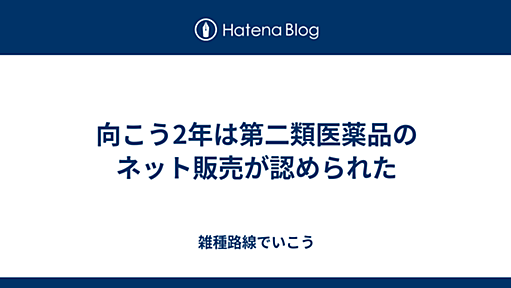
兵庫大阪でみつかった豚フルが東京で流行っていないはずがない。なぜ「患者第一号は渡航者」って建前に拘って国民生活に打撃を与え、労力ほどの意味はない検疫ばかりに注力し続けるのか。員数主義で無駄に兵力を浪費した戦中と何も変わらないじゃないか。けど、こういう本当のことを医系技官が堂々と書けるようになったことは時代の進歩だ。大本営発表を垂れ流している新聞の不甲斐なさも浮き彫りになる。独自に医師を取材したり、それっぽい患者のPCR検査くらいやってみろよと。飲めば「あれは戒厳令の演習なんだよ」って話になるが、どこか「関東防空大演習を嗤ふ」的なコラムを書く気骨あるジャーナリストはいないのか。まあ、それが活字媒体の緩慢な自殺なんだろうな。南無。 国内の新型インフルエンザ対策の一番の功労者は、神戸の開業医の先生でしょう。 「何かおかしい、新型インフルエンザかも?」としてPCR検査を決めなければ、今頃まだ「検疫

楽天なりケンコーコムが厚労省から天下りを受け入れて、何年か粘り腰で頑張れば現実的な手打ちもできるんじゃない?役所も最初は叩いて既得権者の顔を立てつつ、成長産業に雇用の受け皿を広げられれば御の字ということで。最初はみんな新興勢力でも、現実を受け入れて徐々に新たな既得権者へと育っていくんだよ。 また、一般的な戦術論からすれば、そもそも両者が対立する構図に持ち込んだ時点で、新興勢力はほぼ負けが決まっている。なにしろその土俵は、相手が勝つように決められており、既得権者がガチンコで勝負なんてことは絶対にしてくれないのだから。 (略) たとえば今回の医薬品ネット販売については、単に新興勢力側が「今まで通りやらせろ」というのではなく、同時に薬剤師会主導によるネット販売を支援していく、というような握りや手打ちも同時に水面下で進めるべきだ。 しかし改正薬事法に「対面販売の原則」を盛り込む際、ネット業界と何ら

そもそも3人乗り自転車は永らく使われていたところ、実は道路交通法で規制されていたのだと警察が「交通の方法に関する教則」を約30年ぶりに改定して禁止を明記したら、親の大反発を食って安全基準策定に転換した経緯があり、これは決して需要喚起のための規制緩和ではない。 基準を見直すことで需要を掘り起こすことはいいのだが、いくら母親が望んでいるとしても結果的に子どもの事故が増えたらだれが責任を取るのか。母親に自転車の3人乗りをしなくても生活できる環境を作ってやることこそ優先されるべきではないのか。 うちも解禁前の3人乗り自転車を今も次男三男の保育園の送迎に使っているし、長男が小学校に入る前、妻は三男を抱っこ紐で抱いて4人乗りで送迎していた。幸いなことに、これまで事故は起こっていない。 3人乗り自転車の安全基準が需要を掘り起こすための規制緩和という認識はミスリードで、もともと3人乗り自転車は広く使われて

あれれ力武さんとは日経デジタルコアか何かの会合で何度かお会いしているはず。仕事上の経歴はプロフィールを参照のこと。おやじさんから「…で,今なにやってんの?」と聞かれたら、公開して差し支えない範囲だと、こんな風に答えるのかなあ。 緊急経済・雇用対策のIT周辺・次期e-Japan戦略へ向けた提言 (ICTビジョン懇SWG) ネットの安全・安心へ向けた民間自主的取り組みの具現化 (違法有害・総セク・安心協) ホワイトスペースを使った通信の解禁へ向けた働きかけ (総合的な法体系ほか) 日本経団連の取り組んでいる高度ICT人材育成への協力 (九大・筑波での講義ほか) マルチナショナル・クラウドのサーバー日本誘致へ向けた政策課題の洗い出し (これから) 技術か政策にかすっていれば炎上する前に首を突っ込みたい性質なので、他も諸々に手を染めている。これは個人のブログなので直接的には仕事のことを書かないよう

ドイツでゲームと暴力事件の因果関係を巡る議論が再燃している。この30年でゲームが急激に普及した割に、ゲーム大国である日本じゃ少年による重大犯罪が減っているのだから統計的根拠は薄い。では個別の乱射事件がゲームへの没入と何ら因果関係がないかというと、彼らが暴力表現のあるゲームで遊んでいたこともまた現実で、遺族にとって犯罪被害とは確率ではなく個々の現実なのだ。 学校の生徒や教師などを巻き添えに15人もの死者を出した、ドイツの銃乱射事件。17歳の少年が犯行に及んだのは、近所の女の子にふられてしまったのが動機の一つと言われているようですが、Times Onlineでは、犯人が暴力表現のあるゲームをプレイしていた事実を受けて、ビデオゲームと犯行動機の関連性が議論されています。 個別の事案について、彼らがそもそも暴力的だから暴力表現のあるゲームをプレイしているのか、或いは暴力表現のあるゲームを通じて内な

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く