多くのソーシャルブックマークサービスにあなたのサイトを対応させたくありませんか?たくさんあるRSSリーダーの追加ボタンにうんざりしていませんか? Add Clipsはソーシャルブックマーク追加ボタンやRSSリーダーへの追加ボタンを1つに統合して、どのソーシャルブックマーク/RSSリーダーを使っているユーザーにも対応できるオールインボタンを提供するサービスです。( → AddClipsの使い方をみる)

http://www.geekpage.jp/blog/?id=2007/2/5 レベル 0 このレベルの人はSBMを見ることはありません。例えば、SEOを調べることはあっても関連リンクにSBMと表示されるくらいで、 そのリンクをクリックすることはしません。彼らはレベル0以上になろうとも思いません。 ありがちな発言 「でりしゃす?はてブ? 何それ?ブックマークを共有するの?craigslistより便利なの?」 レベル 1 このレベルの人たちはブックマークを共有することが流行っていることは知っています。 でもlivedoor clip は利用してもlivedoor Readerは知らなかったり、はてブを参考にしてもDel.icio.usは見たことがありません。 残念ながらプロバイダがニフティなのでニフティクリップは利用できるのに、レベル1の人たちはそれを知りません。 ありがちな発言 「ブック

えーと、またまた検索の話です。反響が悪いのですが、自分でトコトン追求していきたいので、お暇な方はお付き合いください。 今まで書いてきた ・自分が探した記事の検索方法を明記する ・これまでの過去記事検索から学んだ記事検索を早くする方法 ・自分のブックマークがあてにならないのは、記憶が曖昧だからだ さらに ・明日は明日の風が吹く - 自分が探した記事の検索方法を明記する/これまでの過去記事検索から学んだ記事検索を早くする方法(from 『斬(ざん)』) の記事から気が付いた事ですが、オレが必要とする検索したい記事ってのが、多くの人とはかなり違うのかな?って思いましたね。求めてるものが元々異なれば、検索方法も違って当たり前だな、と。 それで、オレが欲しい記事ってのを考えた。最近(1,2週間)の記事なんかは、探しやすい方法がいっぱいあるので、困らない。つまり、今まで書いてきたことは、検索する時に困

2006年10月16日 ソーシャルブックマークサービスといじめ 無断リンクにまつわる何だかなぁって話って記事で、感じたことをそのまま文章化して、「いじめ」という単語を出してしまった訳だが、似たような感触を感じていた人もある程度いたようで、自分自身も考えるキッカケになった訳だし、それはそれでよかったのかもしれない。 今の知識が浅はかなままこれ以上「いじめ」について語るのは自分の首を絞めるようなものだが、ツッコミ待ちという意味と今後も考えたい問題だという事でもう少し書いておこうと思う。 結論から言えば、ソーシャルブックマークサービス(今回ははてブ)と、誰か一人或いは少数(今回は tinycafe氏)の構図は「いじめ」とは呼ばないと判断している。 根拠を述べる前に「いじめ」とは何かを考えなければならないだろう。 * いじめとは何か 前回の件が「いじめ」に似ていると感じた構図だが、一体それは何故な

初めて出会った人との間に共通の友人がいると「世界は狭いですねぇ」などという。こうした狭い世界、あるいは小さな世界の現象を解析し、工学的に応用しようとする動きがあちこちで見られるようになってきた。例えば、ネットワークトポロジの決定シミュレーション、エージェントの協調設計、PtoP(Peer-to-Peer)アーキテクチャにおける分散検索(分散インデックスによる検索)、グリッドコンピューティング、コミュニティコンピューティングなどにおける応用である。本コラムでは、この「狭い世界」の特徴を概観し、ソフトウェアシステムへのさまざまな応用を考える。 狭い世界という現象は、心理学者のスタンリー・ミルグラムが1960年代後半に提唱した「6次の隔たり(Six Degrees of Separations)」という概念から発展している。この概念は、社会において人間同士がどのように結ばれているのかを明らかにす
ネットワークにおいて、あるノード(ネットワークの要素)からほかの任意のノードにたどり着くのに、少数の中継ノードを経由するだけでよいという性質を示す言葉。知り合いの知り合いが意外にも旧知の人であったときに使う「It's a small world !」(世間は狭い!)という英語表現に由来する。 ネットワークに関する研究は数学分野では18世紀のレオンハルト・オイラー(Leonhard Euler)以来、グラフ理論として古くからあった。1950年代ごろ、数学者のポール・エルデシュ(Paul Erdos)とアルフレッド・レーニイ(Alfred Renyi)はそれを発展させ、ネットワークの形成についてエルデシュ・レーニイモデル(ERモデル)を考案している。同じころ、社会科学の分野でも政治学者のイシエル・デ・ソラ・プール(Ithiel de Sola Pool)らが人的ネットワークの政治的影響力につい
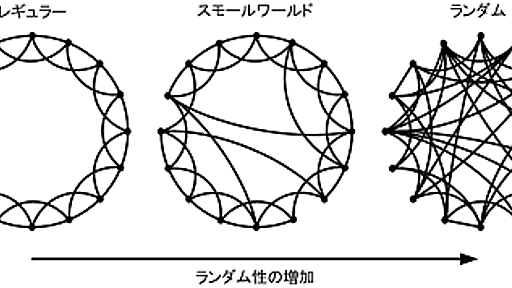
僕は、SBMサービスのhot entryなどの多くの人の手によってフィルタリングされたブックマーク一覧を見るのが大好きなのだが、ランキングに出てくるブックマークは、時間軸に依存するし、それ以上にこちらがチェック可能なURLは有限なので、そこを構成するユーザー層は、SBMサービスごとに性格が異なってしかるべき。 さらに言うと、これはまだ現時点の感覚だけど、hot entryみたいな集計でトップページを構成するブックマークが、そのSBMサービスの総合的なサイトの空気を決めているんじゃないだろうか。とくにコメント機能でつながっていればこそ。ここは使いたくない、みたいなので事前にフィルタリングされていれば特に。 僕にとってのSBMサービスの性格とは、hot entryのトップ10以内にどういうエントリーがあがってくるのかがポイントと思ってる。 pookmarkを使い始めてから、はてブのhot en
blog.8-p.info : del.icio.us とか livedoor クリップとか 微妙なものを全体で共有 微妙なものを全体で共有したがるのは、アンテナの更新範囲指定のころから続くはてな社の伝統。 確かに。全体で共有したら負荷が少なくなる(?)とかあるのかもしれませんが、 こんな重要情報(被お気に入りの表示)をユーザーに提供しなくてどうするんだ。 と同様、どちらかというと思想的な問題かなと思います。あえてやっていないと言うか。 被お気に入りについては、 inurl:b.hatena.ne.jp intitle:お気に入り (はてなid)でぐぐれば出てくるので特に問題はないと思います。 URI でのしぼりこみ Wikipedia のページに wikipedia とか、Flickr のページに flickr とか、URI に含まれている文字列をタグでもつけるのは不毛だと思う。 自分は

*この記事は「パラダイムシフト」という単語を覚えたので使ってみたいという欲求だけで書かれた記事です。 Blog進化論があります。進化につれて、 1.記事を売る 2.サイトを売る 3.キャラを売る という発達を遂げます。 REVの日記 @はてな - "オメガブロガーとして。"より抜粋したブログ進化論である。ブログという記事単位のばら売りが容易になったことで、このような進化形態になったことはニュースサイトをやっている私が一番強く感じている。きっかけは、他のサイトで見かける一つの記事。その記事が気に入って、そのブログの最近書かれた記事を読んで気に入ったら巡回リストに入れている。気がつけば書き手が好きになっていたりするものだ。 しかし、世の中にはいきなり進化した状態でブログ界に飛び込んでくる人がいる。それが有名人ブログ。有名人がどんな記事を書くのか気になって人が集まってくるのだろう。そして良い記事

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く