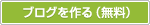1月26日(日) 『日刊ゲンダイ』に掲載されたコメント [コメント]
〔以下のコメントは『日刊ゲンダイ』1月26日付に掲載されたものです。〕
*巻頭特集:今ごろ、動き出す奇怪…自民党政権とフジテレビの怪しい関係
法大名誉教授の五十嵐仁氏(政治学)が言う。
「国から免許を得て公共財である電波を独占利用し、巨額の広告収入を得る。今のフジは『その資格があるのか』と問われているのに、当事者の経営陣も免許を与える政権側も重大性を理解しているようには見えません」
さらに疑いたくなるのは、自民党政権とフジの怪しい関係である。別の テレビ局がこれだけの不祥事をやらかしていれば、今ごろ動き出すような奇怪な対応はなかったはず。自民党には「押っ取り刀」の実績がある。
その象徴こそ87歳の今なお、フジサンケイグループの代表に君臨する「フジの天皇」こと、日枝久氏である。
「率先してフジサンケイクラシックが開催される『富士桜カントリー倶楽部』などで安倍元首相らと“ゴルフ接待”を重ね、メディアが踏まえるべき一線を超えた。時の政権との緊張関係は緩みっぱなしで、もはや権力監視を担う報道機関を名乗る資格はありません」(五十嵐仁氏=前出)
はたしてフジの女子アナ献上の相手は人気タレントだけだったのか。女性記者に鼻の下を伸ばす自民のオッサン議員を見るにつれ、ゲスの勘繰りを入れたくもなるというものだ。
*巻頭特集:今ごろ、動き出す奇怪…自民党政権とフジテレビの怪しい関係
法大名誉教授の五十嵐仁氏(政治学)が言う。
「国から免許を得て公共財である電波を独占利用し、巨額の広告収入を得る。今のフジは『その資格があるのか』と問われているのに、当事者の経営陣も免許を与える政権側も重大性を理解しているようには見えません」
さらに疑いたくなるのは、自民党政権とフジの怪しい関係である。別の テレビ局がこれだけの不祥事をやらかしていれば、今ごろ動き出すような奇怪な対応はなかったはず。自民党には「押っ取り刀」の実績がある。
その象徴こそ87歳の今なお、フジサンケイグループの代表に君臨する「フジの天皇」こと、日枝久氏である。
「率先してフジサンケイクラシックが開催される『富士桜カントリー倶楽部』などで安倍元首相らと“ゴルフ接待”を重ね、メディアが踏まえるべき一線を超えた。時の政権との緊張関係は緩みっぱなしで、もはや権力監視を担う報道機関を名乗る資格はありません」(五十嵐仁氏=前出)
はたしてフジの女子アナ献上の相手は人気タレントだけだったのか。女性記者に鼻の下を伸ばす自民のオッサン議員を見るにつれ、ゲスの勘繰りを入れたくもなるというものだ。
2025-01-26 06:44
nice!(0)
1月21日(火) 『日刊ゲンダイ』に掲載されたコメント [コメント]
〔以下のコメントは『日刊ゲンダイ』1月21日付に掲載されたものです。〕
*巻頭特集:経営危機も深刻化…果たして国や国会はどう対応?「フジから免許を取り上げろ」の正論
報じられているように、フジ幹部が女性社員をタレントに“上納”することが常態化していたとすれば、重大な人権問題である。そんな暴挙が横行し、見過ごされてきた企業風土は報道機関として適切なのかという疑問が視聴者の間に急速に広がっているし、この問題が表面化してからのフジの対応は組織的な隠蔽と言われても仕方がない。
「公共の電波を預かるテレビ局が取材制限をし、会見の中継もさせないというのでは、国民の知る権利に応えていないことになる。他の企業や政治家の不祥事には、フジも遠慮なくテレビカメラを向けてきたはずです。今後、不祥事会見などで『フジと同様にテレビ撮影はNG』と言われたらどうするのか。悪しき前例をつくったフジには抗議する資格すらないのです。『社会の公器』が聞いて呆れる。フジにはもはや報道機関を名乗る資格はなく、メディアとしての使命を果たすことはできません」(法大名誉教授の五十嵐仁氏=政治学)
BPOの委員を務めたことがあるジャーナリストの斎藤貴男氏も本紙取材に対し、「この問題こそ、放送界の自主規制機関であるBPOで取り上げるべき」「BPOの審査対象は個別の番組だが、中居さんの出演番組という切り口でフジの問題を取り上げることができるはずだ」と話した。
「人権問題としても、メディアのあり方としても重大な疑義がありますから、今月から始まる通常国会でも取り上げる必要があるでしょう。フジテレビは政治家の子息が数多く入社していることでも有名ですが、そういうコネで不祥事を隠蔽できるような時代ではありません。問題に無理やりフタをしようとしても、世論が許さない。フジテレビが免許事業者としてふさわしいのか、国会できっちり審議すべきです」(五十嵐仁氏=前出)
*巻頭特集:経営危機も深刻化…果たして国や国会はどう対応?「フジから免許を取り上げろ」の正論
報じられているように、フジ幹部が女性社員をタレントに“上納”することが常態化していたとすれば、重大な人権問題である。そんな暴挙が横行し、見過ごされてきた企業風土は報道機関として適切なのかという疑問が視聴者の間に急速に広がっているし、この問題が表面化してからのフジの対応は組織的な隠蔽と言われても仕方がない。
「公共の電波を預かるテレビ局が取材制限をし、会見の中継もさせないというのでは、国民の知る権利に応えていないことになる。他の企業や政治家の不祥事には、フジも遠慮なくテレビカメラを向けてきたはずです。今後、不祥事会見などで『フジと同様にテレビ撮影はNG』と言われたらどうするのか。悪しき前例をつくったフジには抗議する資格すらないのです。『社会の公器』が聞いて呆れる。フジにはもはや報道機関を名乗る資格はなく、メディアとしての使命を果たすことはできません」(法大名誉教授の五十嵐仁氏=政治学)
BPOの委員を務めたことがあるジャーナリストの斎藤貴男氏も本紙取材に対し、「この問題こそ、放送界の自主規制機関であるBPOで取り上げるべき」「BPOの審査対象は個別の番組だが、中居さんの出演番組という切り口でフジの問題を取り上げることができるはずだ」と話した。
「人権問題としても、メディアのあり方としても重大な疑義がありますから、今月から始まる通常国会でも取り上げる必要があるでしょう。フジテレビは政治家の子息が数多く入社していることでも有名ですが、そういうコネで不祥事を隠蔽できるような時代ではありません。問題に無理やりフタをしようとしても、世論が許さない。フジテレビが免許事業者としてふさわしいのか、国会できっちり審議すべきです」(五十嵐仁氏=前出)
2025-01-21 06:52
nice!(0)
1月16日(木) 『日刊ゲンダイ』に掲載されたコメント [コメント]
〔以下のコメントは『日刊ゲンダイ』1月16日付に掲載されたものです。〕
*巻頭特集:やりたいことはすべて封印…大丈夫か?石破首相、ボヤキと睡眠薬の日々
日本維新と国民民主を天秤にかけ、まんまと補正予算を成立させ、昨年の臨時国会を乗り切った石破は、このやり方に自信を深めているという。
国会答弁にも自信を持ちはじめているという。「石破論法」と揶揄される国会答弁は、野党議員の質問に、「ご指摘は謙虚に受け止めます」「まったく同感です」などと、まず下手にでて、長々と説明をするが、いつまでにどうするのか、最後まで言質を与えない、というシロモノ。議事録を読むと、質問になにも答えていない。
法大名誉教授の五十嵐仁氏(政治学)はこう言う。
「少数与党の石破首相は、昨年の臨時国会と同じように、可能な限り、野党の要求を丸のみすることで、本予算の成立をはかり、6月末までの通常国会を無事に乗り切るつもりなのでしょう。しかし、はたして思惑通りにいくのかどうか。たとえ、国会での数合わせに成功し、予算を成立させ、内閣不信任案を否決できたとしても、受け身の姿勢では、7月の参院選で有権者から厳しい審判を受けるだけです。石破首相は、古い自民党を壊すと訴え、たとえ党内で冷や飯を食わされてもアベ政治を批判するなど、自分の考えを強く主張することで、国民の支持を集めていたはずです。石破政権が延命できるかどうか、最後は有権者の支持を得られるかどうかですよ。なぜ、腹をくくらないのか。いま、国際社会は揺れ、日本には難問が山積している。いまこそ、トップのリーダーシップが問われているのに、持論を封印するなんて最悪です」
もはや、石破が総理をつづける意味はないのではないか。
*巻頭特集:やりたいことはすべて封印…大丈夫か?石破首相、ボヤキと睡眠薬の日々
日本維新と国民民主を天秤にかけ、まんまと補正予算を成立させ、昨年の臨時国会を乗り切った石破は、このやり方に自信を深めているという。
国会答弁にも自信を持ちはじめているという。「石破論法」と揶揄される国会答弁は、野党議員の質問に、「ご指摘は謙虚に受け止めます」「まったく同感です」などと、まず下手にでて、長々と説明をするが、いつまでにどうするのか、最後まで言質を与えない、というシロモノ。議事録を読むと、質問になにも答えていない。
法大名誉教授の五十嵐仁氏(政治学)はこう言う。
「少数与党の石破首相は、昨年の臨時国会と同じように、可能な限り、野党の要求を丸のみすることで、本予算の成立をはかり、6月末までの通常国会を無事に乗り切るつもりなのでしょう。しかし、はたして思惑通りにいくのかどうか。たとえ、国会での数合わせに成功し、予算を成立させ、内閣不信任案を否決できたとしても、受け身の姿勢では、7月の参院選で有権者から厳しい審判を受けるだけです。石破首相は、古い自民党を壊すと訴え、たとえ党内で冷や飯を食わされてもアベ政治を批判するなど、自分の考えを強く主張することで、国民の支持を集めていたはずです。石破政権が延命できるかどうか、最後は有権者の支持を得られるかどうかですよ。なぜ、腹をくくらないのか。いま、国際社会は揺れ、日本には難問が山積している。いまこそ、トップのリーダーシップが問われているのに、持論を封印するなんて最悪です」
もはや、石破が総理をつづける意味はないのではないか。
2025-01-16 06:44
nice!(0)
1月13日(月) 『非核の政府を求める会ニュース』に掲載されたコメント [コメント]
〔以下のコメントは『非核の政府を求める会ニュース』第395号、2024年12月15日・2025年1月15日合併号、に掲載されたものです。〕
2025年・被爆80年―〝核兵器の非人道性〟を発信し、〝核兵器禁止条約に参加する政府を〟の声さらに大きく
日本被団協のノーベル平和賞受賞にみられるように、「非核」は時代のトレンドになりました。総選挙の結果、「非核の政府」を樹立できる可能性も高まりました。いま。出番のときです。今年は勝負の年になるでしょう。自公政権を撃破して、政権交代を実現する年に。
2025年・被爆80年―〝核兵器の非人道性〟を発信し、〝核兵器禁止条約に参加する政府を〟の声さらに大きく
日本被団協のノーベル平和賞受賞にみられるように、「非核」は時代のトレンドになりました。総選挙の結果、「非核の政府」を樹立できる可能性も高まりました。いま。出番のときです。今年は勝負の年になるでしょう。自公政権を撃破して、政権交代を実現する年に。
2025-01-13 07:10
nice!(0)
1月11日(土) 『日刊ゲンダイ』に掲載されたコメント [コメント]
〔以下のコメントは『日刊ゲンダイ』1月11日付に掲載されたものです。〕
*巻頭特集:防衛費だけは聖域か?「103万円の壁」自民党が財源を問うご都合主義
27年度に防衛予算は11兆円を超える見込みだが、さらに天井知らずで上昇させようとは軍事オタクの本領発揮だ。現状の防衛増税だけで賄いきれるわけもなく、さらなる負担増は既定路線である。
しかし「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代ならいざしらず、今や日本は先進国の地位から衰退の一途。1人あたりGDPは22年には韓国に、昨年は台湾にそれぞれ抜かれ、もはやアジアの代表国とも言えない。青天井の軍拡予算に耐えきれる国力など、もう残されてはいないのだ。
「財源の裏付けなきバラマキ策は問題ですが、防衛費の聖域化はより大きな由々しき事態です。米国の顔色をうかがい、さらなる国民負担を強いて、できもしない軍拡路線を貫けば、この国は外敵に攻められる前に内側から崩壊してしまう。身の丈に合った額まで防衛予算を削り、国防より生活を守る予算を優先すべきです」(法大名誉教授・五十嵐仁氏=政治学)
*巻頭特集:防衛費だけは聖域か?「103万円の壁」自民党が財源を問うご都合主義
27年度に防衛予算は11兆円を超える見込みだが、さらに天井知らずで上昇させようとは軍事オタクの本領発揮だ。現状の防衛増税だけで賄いきれるわけもなく、さらなる負担増は既定路線である。
しかし「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代ならいざしらず、今や日本は先進国の地位から衰退の一途。1人あたりGDPは22年には韓国に、昨年は台湾にそれぞれ抜かれ、もはやアジアの代表国とも言えない。青天井の軍拡予算に耐えきれる国力など、もう残されてはいないのだ。
「財源の裏付けなきバラマキ策は問題ですが、防衛費の聖域化はより大きな由々しき事態です。米国の顔色をうかがい、さらなる国民負担を強いて、できもしない軍拡路線を貫けば、この国は外敵に攻められる前に内側から崩壊してしまう。身の丈に合った額まで防衛予算を削り、国防より生活を守る予算を優先すべきです」(法大名誉教授・五十嵐仁氏=政治学)
2025-01-11 06:46
nice!(0)
1月8日(水) 総選挙の結果と憲法運動の課題(その3) [論攷]
〔以下の論攷は『月刊 憲法運動』通巻537号、2025年1月号に掲載されたものです。3回に分けてアップさせていただきます。〕
三、新たな政治への模索と挑戦
国会の機能回復
総選挙の結果、野党の協力なしには予算案も法案も通らなくなりました。いわゆる「ハングパーラメント(宙づり国会)」の出現です。このような状況の下でキャスチングボートを握ったのは国民民主党でした。石破首相は政策ごとの部分連合で、国会を乗り切ろうとしています。
もちろん、自民党としては玉木首班などを餌に国民民主党を連立に引き込もうとするでしょう。自社さ政権の前例がありますから。しかし、自民党を救った社会党や新党さきがけがどのような末路をたどったのか、国民民主党は歴史の教訓をかみしめるべきでしょう。
いずれにせよ、「一強多弱」と言われてきた政治状況に大きな変化が生まれました。安倍・菅・岸田と続いてきた国会軽視や自民党の事前審査による審議の形骸化は是正され、熟議の場としての実質を回復する可能性が生じています。
衆院の委員長などの人事によれば、立憲民主党の安住淳氏が予算委員長、枝野幸男氏が憲法審査会の会長、渡辺周氏が政治改革特別委員長、法務委員長に西村智奈美氏が、それぞれ就任しました。計27ポストのうち、野党が12となっています。野党が予算委員長になるのは1994年以来のことです。
今後の国会審議の焦点は、政治改革のやり直しです。早速、裏金を受け取っていた旧安倍派の参院議員27人と衆院の15人全員が政治倫理審査会への出席を申し出ました。政治資金規正法の再改正に向けての与野党協議も公開で行われるなどの変化が生まれています。政策活動費の廃止や第三者機関の設置が決まりましたが、引き続き企業・団体献金や政治資金パーティーの禁止を実現することが、これからの課題です。
国民民主党が要求していた「103万円の壁」の見直しに向けての動きも始まりました。詳細な内容の具体化はこれからですが、税金をめぐる協議が可視化されたことも、新たな変化として注目されます。ただし、これが国民民主党のパフォーマンスと同党を吊り上げるためのバラマキにならないよう警戒する必要があるでしょう。
また、選択的夫婦別姓の法制化に向けても新しい可能性が生まれました。立憲民主党の西村法務委員長の就任は法制化実現の布石で、野党が提出している法案の成立に向けて攻勢をかける準備にほかなりません。選挙前に賛否を問われる自民党の参院議員は、どう対応するのでしょうか。
要求実現に向けての環境変化
総選挙後の新たな国会での論戦と結びつけて、国民的な運動と世論の力による政策の実現を迫る運動が重要になります。そして、そのための条件と環境も大きく変化しました。少数政権に対して要求実現を目指す労働・社会運動によるボディーブローの威力が増大し、課題によっては実現の可能性が高まっているからです。
まず、労働運動の分野では大きな成果が期待されます。石破首相は賃上げを最重要課題とし、政府・労働組合・経済界の代表が集まる「政労使会議」と経済財政諮問会議の「特別会合」で「今年の勢いで大幅な賃上げへの協力を」要請しました。最低賃金を2020年代に1500円にする具体的な対応策を取りまとめる考えも示しています。賃上げは総選挙で野党も公約に掲げていましたから、大きく前進する可能性があります。
選挙中に各党が掲げた公約にも、共通するものがありました。自民党が反対しても野党が一致すれば実現できます。現行の健康保険証廃止の凍結・中止、大学の学費値上げのストップ、同性カップルの結婚のルールづくり、大軍拡に向けての増税阻止、応能負担に基づく税制の抜本的な改革、社会保障の充実と物価高対策・生活支援などの実現に向けて、国民的な運動を強めていくことが重要です。
80年代をピークに日本の国力は衰退を続け、もはや「先進国」とは言えない惨状を呈しています。日米構造講義や年次改革要望書などによって軍事分担と市場開放を求めるアメリカの圧力に屈し、90年代からは大企業本位の規制緩和と民営化などの新自由主義的改革が進められてきました。その行き着いた先が「アベノミクス」であり、軍事大国化に向けての安倍・菅・岸田政権の暴走でした。
それにストップをかけ、政治の方向性を大転換するチャンスが訪れたのです。要求に基づいて運動を強め、世論を高めれば政治を変えられる新たな希望が生まれました。労働・社会運動によって草の根から社会を変え、政治に結び付けていくことができるかどうか、国民的運動の真価が問われているのです。
政権交代の可能性
国会の機能回復と労働・社会運動の環境変化によって生み出された成果は、時々の選挙によって収穫されることになるでしょう。各種の首長選挙で、与野党が安易に相乗りするような悪弊を改めなければなりません。地方政治においても与党に対する明確な選択肢を提起することは野党の大きな責任です。
国政選挙でも市民と野党が力を合わせてたたかうことが必要です。それが自公政権にとってどれほど大きな脅威であるかは、「立憲共産党」攻撃や総選挙での「奇襲攻撃」に明らかです。石破首相が自民党主流の短期決戦論に屈したのは、共闘構築に向けての話し合いの時間を与えないためでした。
そのために野党共闘は一部にとどまり、立憲民主党と共産党などは小選挙区で競合することになりました。両党が競合した142選挙区で「共闘」していれば、与党系を破る可能性があった選挙区は22に上り、立憲の議席数は自民党と並んでいたという試算があります(「東京新聞」11月5日付)。1万票以下の接戦区も61ありました。
2025年には、国政選挙として参院選が予定され、東京都議選もあります。都議選の結果が参院選に影響することを嫌ってダブル選挙にするかもしれません。その場合には7月13日になる可能性があります。
それ以前にも、3月後半の来年度予算案採決の時期に危機が訪れるかもしれません。「103万円の壁」見直しという空約束で国民民主党などを丸め込み補正予算を成立させても、来年度予算もそうできるとはかぎりません。予算の成立を条件に自分の首を差し出した竹下登元首相の例もあります。石破首相はどうするのでしょうか。
7月の参院選が大きな山場になることは明らかです。野党は32ある1人区で一本化するための調整を直ちに始めるべきでしょう。そうすれば29勝3敗になるという試算もあります。2人区や3人区でも可能な限り野党候補が乱立しないように調整するべきです。
参院選で野党が勝利すれば、衆参の多数派が異なる「ねじれ現象」が解消され、本格的な政権交代が視野に入ってきます。秋の臨時国会で解散・総選挙に追い込み、自民党を撃破して新しい政権を樹立することが課題になります。参院選で衆参同日選挙になる可能性も否定できません。
むすび
諦めてはならないということを痛感させられました。まさか自民党と統一協会の腐れ縁という旧悪が、このような形で表面化するとは思いませんでした。旧安倍派を中心とした自民党派閥の裏金事件も、このような形で暴露され国民の怒りを爆発させたというのも予想外のことです。
前回の総選挙が終了した時点で多くの人が口にしていたのは、「黄金の3年間」という言葉でした。2021年夏の参院選に加えて秋の衆院選で勝利した岸田政権は、その後の3年間は国政選挙がなく、改憲発議などの政治課題に腰を据えて取り組めるというわけです。
しかし、そうはなりませんでした。実際には、押し寄せる政権批判の荒波をかいくぐるのが精いっぱいで、ほとんど目立つような成果を上げられず、軍拡ばかりに狂奔し、経済政策の失敗と物価高によって内閣支持率が2割台に低迷するという体たらくです。「黄金の3年間」どころか「泥沼の3年間」でした。
その結果、岸田前首相は続投断念に追い込まれたのです。これも菅前政権に次ぐ異例の展開であり、多くの国民の意表を突くものでした。その意外性を演出することによって国民の関心を高め、総裁選挙を盛り上げて一気に総選挙に突入して勝利するというのが、自民党の狙いだったにちがいありません。
しかし、それは成功しませんでした。選挙前には想像だにしていなかったであろう与党の過半数割れです。自公政権は一気に政治的危機に直面することになりました。これは多くの人々にとっては驚愕の結果だったでしょう。
世の中は捨てたものではありません。ときには予想を超えた望ましい結果をもたらすこともあるのです。行き詰まり大きな壁にぶち当たっていた日本にも、ようやく日が差してきたのかもしれません。明るい未来に向けての日差しが。
もう一度、声を大にして言いたいと思います。あきらめてはなりません。政治は変えられるのですから。今回の総選挙によってもたらされた驚天動地の結果のように。
(いがらし じん)
三、新たな政治への模索と挑戦
国会の機能回復
総選挙の結果、野党の協力なしには予算案も法案も通らなくなりました。いわゆる「ハングパーラメント(宙づり国会)」の出現です。このような状況の下でキャスチングボートを握ったのは国民民主党でした。石破首相は政策ごとの部分連合で、国会を乗り切ろうとしています。
もちろん、自民党としては玉木首班などを餌に国民民主党を連立に引き込もうとするでしょう。自社さ政権の前例がありますから。しかし、自民党を救った社会党や新党さきがけがどのような末路をたどったのか、国民民主党は歴史の教訓をかみしめるべきでしょう。
いずれにせよ、「一強多弱」と言われてきた政治状況に大きな変化が生まれました。安倍・菅・岸田と続いてきた国会軽視や自民党の事前審査による審議の形骸化は是正され、熟議の場としての実質を回復する可能性が生じています。
衆院の委員長などの人事によれば、立憲民主党の安住淳氏が予算委員長、枝野幸男氏が憲法審査会の会長、渡辺周氏が政治改革特別委員長、法務委員長に西村智奈美氏が、それぞれ就任しました。計27ポストのうち、野党が12となっています。野党が予算委員長になるのは1994年以来のことです。
今後の国会審議の焦点は、政治改革のやり直しです。早速、裏金を受け取っていた旧安倍派の参院議員27人と衆院の15人全員が政治倫理審査会への出席を申し出ました。政治資金規正法の再改正に向けての与野党協議も公開で行われるなどの変化が生まれています。政策活動費の廃止や第三者機関の設置が決まりましたが、引き続き企業・団体献金や政治資金パーティーの禁止を実現することが、これからの課題です。
国民民主党が要求していた「103万円の壁」の見直しに向けての動きも始まりました。詳細な内容の具体化はこれからですが、税金をめぐる協議が可視化されたことも、新たな変化として注目されます。ただし、これが国民民主党のパフォーマンスと同党を吊り上げるためのバラマキにならないよう警戒する必要があるでしょう。
また、選択的夫婦別姓の法制化に向けても新しい可能性が生まれました。立憲民主党の西村法務委員長の就任は法制化実現の布石で、野党が提出している法案の成立に向けて攻勢をかける準備にほかなりません。選挙前に賛否を問われる自民党の参院議員は、どう対応するのでしょうか。
要求実現に向けての環境変化
総選挙後の新たな国会での論戦と結びつけて、国民的な運動と世論の力による政策の実現を迫る運動が重要になります。そして、そのための条件と環境も大きく変化しました。少数政権に対して要求実現を目指す労働・社会運動によるボディーブローの威力が増大し、課題によっては実現の可能性が高まっているからです。
まず、労働運動の分野では大きな成果が期待されます。石破首相は賃上げを最重要課題とし、政府・労働組合・経済界の代表が集まる「政労使会議」と経済財政諮問会議の「特別会合」で「今年の勢いで大幅な賃上げへの協力を」要請しました。最低賃金を2020年代に1500円にする具体的な対応策を取りまとめる考えも示しています。賃上げは総選挙で野党も公約に掲げていましたから、大きく前進する可能性があります。
選挙中に各党が掲げた公約にも、共通するものがありました。自民党が反対しても野党が一致すれば実現できます。現行の健康保険証廃止の凍結・中止、大学の学費値上げのストップ、同性カップルの結婚のルールづくり、大軍拡に向けての増税阻止、応能負担に基づく税制の抜本的な改革、社会保障の充実と物価高対策・生活支援などの実現に向けて、国民的な運動を強めていくことが重要です。
80年代をピークに日本の国力は衰退を続け、もはや「先進国」とは言えない惨状を呈しています。日米構造講義や年次改革要望書などによって軍事分担と市場開放を求めるアメリカの圧力に屈し、90年代からは大企業本位の規制緩和と民営化などの新自由主義的改革が進められてきました。その行き着いた先が「アベノミクス」であり、軍事大国化に向けての安倍・菅・岸田政権の暴走でした。
それにストップをかけ、政治の方向性を大転換するチャンスが訪れたのです。要求に基づいて運動を強め、世論を高めれば政治を変えられる新たな希望が生まれました。労働・社会運動によって草の根から社会を変え、政治に結び付けていくことができるかどうか、国民的運動の真価が問われているのです。
政権交代の可能性
国会の機能回復と労働・社会運動の環境変化によって生み出された成果は、時々の選挙によって収穫されることになるでしょう。各種の首長選挙で、与野党が安易に相乗りするような悪弊を改めなければなりません。地方政治においても与党に対する明確な選択肢を提起することは野党の大きな責任です。
国政選挙でも市民と野党が力を合わせてたたかうことが必要です。それが自公政権にとってどれほど大きな脅威であるかは、「立憲共産党」攻撃や総選挙での「奇襲攻撃」に明らかです。石破首相が自民党主流の短期決戦論に屈したのは、共闘構築に向けての話し合いの時間を与えないためでした。
そのために野党共闘は一部にとどまり、立憲民主党と共産党などは小選挙区で競合することになりました。両党が競合した142選挙区で「共闘」していれば、与党系を破る可能性があった選挙区は22に上り、立憲の議席数は自民党と並んでいたという試算があります(「東京新聞」11月5日付)。1万票以下の接戦区も61ありました。
2025年には、国政選挙として参院選が予定され、東京都議選もあります。都議選の結果が参院選に影響することを嫌ってダブル選挙にするかもしれません。その場合には7月13日になる可能性があります。
それ以前にも、3月後半の来年度予算案採決の時期に危機が訪れるかもしれません。「103万円の壁」見直しという空約束で国民民主党などを丸め込み補正予算を成立させても、来年度予算もそうできるとはかぎりません。予算の成立を条件に自分の首を差し出した竹下登元首相の例もあります。石破首相はどうするのでしょうか。
7月の参院選が大きな山場になることは明らかです。野党は32ある1人区で一本化するための調整を直ちに始めるべきでしょう。そうすれば29勝3敗になるという試算もあります。2人区や3人区でも可能な限り野党候補が乱立しないように調整するべきです。
参院選で野党が勝利すれば、衆参の多数派が異なる「ねじれ現象」が解消され、本格的な政権交代が視野に入ってきます。秋の臨時国会で解散・総選挙に追い込み、自民党を撃破して新しい政権を樹立することが課題になります。参院選で衆参同日選挙になる可能性も否定できません。
むすび
諦めてはならないということを痛感させられました。まさか自民党と統一協会の腐れ縁という旧悪が、このような形で表面化するとは思いませんでした。旧安倍派を中心とした自民党派閥の裏金事件も、このような形で暴露され国民の怒りを爆発させたというのも予想外のことです。
前回の総選挙が終了した時点で多くの人が口にしていたのは、「黄金の3年間」という言葉でした。2021年夏の参院選に加えて秋の衆院選で勝利した岸田政権は、その後の3年間は国政選挙がなく、改憲発議などの政治課題に腰を据えて取り組めるというわけです。
しかし、そうはなりませんでした。実際には、押し寄せる政権批判の荒波をかいくぐるのが精いっぱいで、ほとんど目立つような成果を上げられず、軍拡ばかりに狂奔し、経済政策の失敗と物価高によって内閣支持率が2割台に低迷するという体たらくです。「黄金の3年間」どころか「泥沼の3年間」でした。
その結果、岸田前首相は続投断念に追い込まれたのです。これも菅前政権に次ぐ異例の展開であり、多くの国民の意表を突くものでした。その意外性を演出することによって国民の関心を高め、総裁選挙を盛り上げて一気に総選挙に突入して勝利するというのが、自民党の狙いだったにちがいありません。
しかし、それは成功しませんでした。選挙前には想像だにしていなかったであろう与党の過半数割れです。自公政権は一気に政治的危機に直面することになりました。これは多くの人々にとっては驚愕の結果だったでしょう。
世の中は捨てたものではありません。ときには予想を超えた望ましい結果をもたらすこともあるのです。行き詰まり大きな壁にぶち当たっていた日本にも、ようやく日が差してきたのかもしれません。明るい未来に向けての日差しが。
もう一度、声を大にして言いたいと思います。あきらめてはなりません。政治は変えられるのですから。今回の総選挙によってもたらされた驚天動地の結果のように。
(いがらし じん)
2025-01-08 05:18
nice!(0)
1月7日(火) 総選挙の結果と憲法運動の課題(その2) [論攷]
〔以下の論攷は『月刊 憲法運動』通巻537号、2025年1月号に掲載されたものです。3回に分けてアップさせていただきます。〕
二、憲法運動の成果と課題
明文改憲阻止の実績
総選挙の結果、憲法の明文改憲に賛成する自民・公明・維新・保守・参政などの政党の議席は3分の2を下回りました。憲法条文の書き換えに向けての発議は難しくなり、改憲派にとっては「冬の時代」の始まりです。立憲民主党の枝野幸男元代表が憲法審査会の会長に就任しましたので、改憲賛成派だけで突っ走ることもできなくなりました。
これまでは衆参ともに改憲派が3分の2を上回り、その気になれば、いつでも改憲発議できたわけです。そうできなかったのは、ひとえに改憲反対を掲げた憲法運動の力によるものでした。その背後には「改憲を急ぐべきではない」という国民世論がありました。総選挙後に取り組んでほしい政策として、改憲を挙げる人は産経新聞の調査でも3%しかいません。
安部首相以降、菅・岸田と続いた自公政権は任期中の改憲発議をめざしてきました。安倍元首相は現行の9条に手をつけず、新たな条項を設けて自衛隊の存在を書き加えるという「妥協案」を提示しました。「9条を守れ」という世論の壁に跳ね返され、譲歩せざるを得なくなったからです。
今回登場した石破首相は、戦力不保持と交戦権の否認を定めた9条2項を削除することを持論としていました。しかし、首相就任にあたってこれをひっこめ、安倍「妥協案」を踏襲しています。石破首相も安倍元首相と同様に譲歩する道を選ばざるを得ませんでした。
加えて、総選挙後の石破政権は少数与党に転落し、政権維持に汲々としています。最初の所信表明演説で改憲に意欲を示しましたが、「それどころではない」というのが正直なところでしょう。今後も警戒と監視を怠らず、私たちの運動によって追い込み、改憲に取り組む余裕を与えないことが重要です。
当面の改憲にとって最大のテーマになっていたのが緊急事態条項の新設です。12月5日に韓国で勃発した「非常戒厳」の発令と短時間での解除騒動は、憲法に緊急事態条項を導入することの危険性を浮き彫りにしました。これも改憲勢力にとっては大きな打撃となることでしょう。
大軍拡・戦争準備の危険性
明文改憲の危機が差し当たり遠のいたからといって、安心はできません。朝日新聞と東大の谷口研究室の調査によれば、衆院当選者のうち改憲賛成派は67%で3分の2を上回っているからです。それに、岸田前政権が進めてきた安保3文書に基づく大軍拡によって、すでに9条は「風前の灯」となっています。
憲法条文の書き換えは阻止してきたものの、9条の内実を掘り崩す「実質改憲」は着々と進行し、もはや条文の書き換えなき改憲段階ともいうべき状況に達しています。かつて自民党が自衛隊の存在を合理化するために展開していた9条の解釈を放棄し、自制も弁解もせずに堂々と戦争準備を進めているからです。
その第1は、専守防衛に基づく安全保障政策の大転換と軍拡の急進展であり、個別的自衛権から集団的自衛権の行使容認に向けての機能強化です。自衛隊は「盾」のみならず「矛」の役割も担うようになり、陸海空の自衛隊を統合する作戦司令部の創設、敵領土内の基地だけでなく中枢部も攻撃できる長射程の戦闘機やミサイルの整備、敵の攻撃に耐えうる基地機能の強靭化、南西諸島の要塞化、秘密情報の保護、武器の生産と輸出、戦時における飛行場や港湾などの軍事利用、同じく戦時に際しての地方自治体の動員と食料の確保なども準備されてきました。いつでも戦争できるようにするという構えです。
第2は、米軍の戦略転換と在日米軍の体制強化です。これまで米軍はインド太平洋軍を管轄する部隊の指揮機能をハワイのホノルルに置き、横田基地の司令官は作戦指揮の権限を持っていませんでした。今後は横田基地の位置付けを高めて宇宙軍を新設し、指揮権限の一部を付与して都心の赤坂に移転しようとしています。市ヶ谷の防衛省の近くに移して共同作戦体制を容易にしようというわけです。これも戦争できるようにするための準備にほかなりません。
自衛隊は必要かつ最小限度の実力組織であって「戦力」ではないという憲法解釈によって9条との整合性を保ってきたのが、これまでの政府の立場でした。これはすでに放棄されてしまったと言えるでしょう、「戦力であって何が悪い」と居直るような大軍拡です。総選挙の結果、これにもストップをかける可能性が生まれました。政権交代によって、このような「居直り大軍拡」を阻止しなければなりません。
憲法を変えるのではなく活かす
日本周辺の安全保障環境が厳しさを増していることは否定できません。だからと言って、大軍拡によってこの厳しさを緩和できるのでしょうか。外交や話し合いというソフトパワーではなく、もっぱら軍事力というハードパワーに頼れば、軍拡競争を煽り立てて危機の火に油を注ぐだけではないでしょうか。
日本周辺の緊張を緩和するために外交的な努力を欠かすことはできません。平和と安全のための最善の手段は、憲法の力を発揮することです。日本は軍事大国にならず、軍事力による恫喝や威嚇ではなく対話と外交によって相互理解を深めることこそ、憲法9条がさし示す道です。9条を守るだけでなく、その理念に基づいて非軍事的な対話路線を具体化しなければなりません。
「今日のウクライナは明日の日本かもしれない」と、岸田前首相は恫喝していました。正しくは、「今日のウクライナを明日の日本にはしない」と言うべきだったでしょう、「なぜなら日本には平和憲法があり、私は9条を守り実行するから」と。
中国との関係でも「台湾有事」が懸念されています。中国周辺に展開する米軍との偶発的な軍事衝突が起きる蓋然性は否定できません。もしそうなったとき、米軍とともに自衛隊が「存立危機事態」と認定して参戦すれば、ただちに「日本有事」に連動してしまいます。そのような事態は絶対に避けなければなりません。
そのためにも、9条を守るだけでなく活かすことが重要です。トランプ米大統領が返り咲き、日本に対する軍事分担要請は一段と強まるでしょう。「日米同盟」と言えば思考停止してしまう悪弊を改め、日本独自の立場から毅然として対応することが求められます。
今年のノーベル平和賞に日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が選ばれました。ウクライナ戦争で核使用をちらつかせているプーチン大統領の暴走を阻止するためにも、唯一の戦争被爆国としても、被団協を先頭に核廃絶を求める世論を高め、非核の政府を実現して核兵器禁止条約への加盟を実現しなければなりません。
二、憲法運動の成果と課題
明文改憲阻止の実績
総選挙の結果、憲法の明文改憲に賛成する自民・公明・維新・保守・参政などの政党の議席は3分の2を下回りました。憲法条文の書き換えに向けての発議は難しくなり、改憲派にとっては「冬の時代」の始まりです。立憲民主党の枝野幸男元代表が憲法審査会の会長に就任しましたので、改憲賛成派だけで突っ走ることもできなくなりました。
これまでは衆参ともに改憲派が3分の2を上回り、その気になれば、いつでも改憲発議できたわけです。そうできなかったのは、ひとえに改憲反対を掲げた憲法運動の力によるものでした。その背後には「改憲を急ぐべきではない」という国民世論がありました。総選挙後に取り組んでほしい政策として、改憲を挙げる人は産経新聞の調査でも3%しかいません。
安部首相以降、菅・岸田と続いた自公政権は任期中の改憲発議をめざしてきました。安倍元首相は現行の9条に手をつけず、新たな条項を設けて自衛隊の存在を書き加えるという「妥協案」を提示しました。「9条を守れ」という世論の壁に跳ね返され、譲歩せざるを得なくなったからです。
今回登場した石破首相は、戦力不保持と交戦権の否認を定めた9条2項を削除することを持論としていました。しかし、首相就任にあたってこれをひっこめ、安倍「妥協案」を踏襲しています。石破首相も安倍元首相と同様に譲歩する道を選ばざるを得ませんでした。
加えて、総選挙後の石破政権は少数与党に転落し、政権維持に汲々としています。最初の所信表明演説で改憲に意欲を示しましたが、「それどころではない」というのが正直なところでしょう。今後も警戒と監視を怠らず、私たちの運動によって追い込み、改憲に取り組む余裕を与えないことが重要です。
当面の改憲にとって最大のテーマになっていたのが緊急事態条項の新設です。12月5日に韓国で勃発した「非常戒厳」の発令と短時間での解除騒動は、憲法に緊急事態条項を導入することの危険性を浮き彫りにしました。これも改憲勢力にとっては大きな打撃となることでしょう。
大軍拡・戦争準備の危険性
明文改憲の危機が差し当たり遠のいたからといって、安心はできません。朝日新聞と東大の谷口研究室の調査によれば、衆院当選者のうち改憲賛成派は67%で3分の2を上回っているからです。それに、岸田前政権が進めてきた安保3文書に基づく大軍拡によって、すでに9条は「風前の灯」となっています。
憲法条文の書き換えは阻止してきたものの、9条の内実を掘り崩す「実質改憲」は着々と進行し、もはや条文の書き換えなき改憲段階ともいうべき状況に達しています。かつて自民党が自衛隊の存在を合理化するために展開していた9条の解釈を放棄し、自制も弁解もせずに堂々と戦争準備を進めているからです。
その第1は、専守防衛に基づく安全保障政策の大転換と軍拡の急進展であり、個別的自衛権から集団的自衛権の行使容認に向けての機能強化です。自衛隊は「盾」のみならず「矛」の役割も担うようになり、陸海空の自衛隊を統合する作戦司令部の創設、敵領土内の基地だけでなく中枢部も攻撃できる長射程の戦闘機やミサイルの整備、敵の攻撃に耐えうる基地機能の強靭化、南西諸島の要塞化、秘密情報の保護、武器の生産と輸出、戦時における飛行場や港湾などの軍事利用、同じく戦時に際しての地方自治体の動員と食料の確保なども準備されてきました。いつでも戦争できるようにするという構えです。
第2は、米軍の戦略転換と在日米軍の体制強化です。これまで米軍はインド太平洋軍を管轄する部隊の指揮機能をハワイのホノルルに置き、横田基地の司令官は作戦指揮の権限を持っていませんでした。今後は横田基地の位置付けを高めて宇宙軍を新設し、指揮権限の一部を付与して都心の赤坂に移転しようとしています。市ヶ谷の防衛省の近くに移して共同作戦体制を容易にしようというわけです。これも戦争できるようにするための準備にほかなりません。
自衛隊は必要かつ最小限度の実力組織であって「戦力」ではないという憲法解釈によって9条との整合性を保ってきたのが、これまでの政府の立場でした。これはすでに放棄されてしまったと言えるでしょう、「戦力であって何が悪い」と居直るような大軍拡です。総選挙の結果、これにもストップをかける可能性が生まれました。政権交代によって、このような「居直り大軍拡」を阻止しなければなりません。
憲法を変えるのではなく活かす
日本周辺の安全保障環境が厳しさを増していることは否定できません。だからと言って、大軍拡によってこの厳しさを緩和できるのでしょうか。外交や話し合いというソフトパワーではなく、もっぱら軍事力というハードパワーに頼れば、軍拡競争を煽り立てて危機の火に油を注ぐだけではないでしょうか。
日本周辺の緊張を緩和するために外交的な努力を欠かすことはできません。平和と安全のための最善の手段は、憲法の力を発揮することです。日本は軍事大国にならず、軍事力による恫喝や威嚇ではなく対話と外交によって相互理解を深めることこそ、憲法9条がさし示す道です。9条を守るだけでなく、その理念に基づいて非軍事的な対話路線を具体化しなければなりません。
「今日のウクライナは明日の日本かもしれない」と、岸田前首相は恫喝していました。正しくは、「今日のウクライナを明日の日本にはしない」と言うべきだったでしょう、「なぜなら日本には平和憲法があり、私は9条を守り実行するから」と。
中国との関係でも「台湾有事」が懸念されています。中国周辺に展開する米軍との偶発的な軍事衝突が起きる蓋然性は否定できません。もしそうなったとき、米軍とともに自衛隊が「存立危機事態」と認定して参戦すれば、ただちに「日本有事」に連動してしまいます。そのような事態は絶対に避けなければなりません。
そのためにも、9条を守るだけでなく活かすことが重要です。トランプ米大統領が返り咲き、日本に対する軍事分担要請は一段と強まるでしょう。「日米同盟」と言えば思考停止してしまう悪弊を改め、日本独自の立場から毅然として対応することが求められます。
今年のノーベル平和賞に日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が選ばれました。ウクライナ戦争で核使用をちらつかせているプーチン大統領の暴走を阻止するためにも、唯一の戦争被爆国としても、被団協を先頭に核廃絶を求める世論を高め、非核の政府を実現して核兵器禁止条約への加盟を実現しなければなりません。
2025-01-07 05:50
nice!(0)
1月6日(月) 総選挙の結果と憲法運動の課題(その1) [論攷]
〔以下の論攷は『月刊 憲法運動』通巻537号、2025年1月号に掲載されたものです。3回に分けてアップさせていただきます。〕
はじめに
驚天動地の結果でした。総選挙で自公が議席を激減させ、衆院での少数与党となったからです。選挙前に石破茂新首相は「与党で過半数維持」という目標を掲げ、「少なすぎるのではないか」と批判されました。しかし、結果は、それをも下回る歴史的大敗です、
石破氏は当初、十分な審議なしの早期解散に反対していました。しかし、自民党の総裁に選出されたとたん前言を翻し、首相に就任する前だったにもかかわらず総選挙の投開票日を口にしました。解散を助言し承認する権限は内閣にあります。首相になる前の表明は憲法違反の暴挙です。しかも、石破氏は天皇の国事行為による7条解散に反対していたではありませんか。
このような変節には理由がありました。新内閣成立への「ご祝儀」としての支持率上昇に期待する自民党内の大勢に抵抗できなかったからです。それに、野党の選挙準備が整わないうちに選挙になだれ込もうという思惑もありました。実際、野党共闘や一本化の動きは低調に終わりました。
しかし、このような奇襲攻撃は功を奏しませんでした。石破新内閣への「ご祝儀」は少なかったからです。かえって石破首相の言行不一致が大きな反発を呼び、裏金事件での国民的な批判という火に油を注ぐ結果となりました。
こうして迎えた総選挙でした。最終盤での自民党非公認候補への「裏公認料」2000万円の交付がまたもや「しんぶん赤旗」に暴露され。敗色濃い候補者に対する決定打となり自民党は歴史的な惨敗に追い込まれました。
それがいかに歴史的なものであったか。衆院での過半数割れは2009年以来、15年ぶりのことです。この結果、特別国会での首相指名選挙は決戦投票になりました。これは30年ぶりのことです。こうして過半数を下回る与党の下での首相が誕生しました。これもなんと大平正芳元首相以来、45年ぶりのことになります。
一、政治的激変を生み出した総選挙
与党の歴史的大敗をもたらしたもの
自民党の歴史的な大敗をもたらした最大の要因は、政治資金パーティーのキックバック(還流)による資金(裏金)の貯め込みでした。それがいつから、誰によって、どのような形で始められたのか、何に使われたのかは、分からずじまいです。中心となった旧安倍派では、安倍元会長の意向でいったんは止めることになったものの復活しました。その経緯も不明です。
この問題を暴露したのは共産党の機関紙「しんぶん赤旗」でした。大きな逆風を吹かせた原動力がこの報道であったことは衆目の一致するところです。こうして「政治とカネ」の問題が直撃し、政治資金規正法を改正せざるを得なくなりましたが、企業・団体献金や政治資金パーティーの禁止という根本原因に手を触れなかったために批判を招き、自民党は総選挙で敗北することになります。
しかし、自民党の大敗を生み出した要因はこれだけではありません。裏金事件は直接の敗因ですが、その根底には安倍政権以来の暴走政治とそれを引き継いだ菅・岸田前政権の4年間に及ぶ失政に対する批判がありました。政治の問題点を明らかにし国民要求の実現を目指した憲法運動をはじめとした多様な社会運動・労働運動の力がボディーブローのような効果を上げ、自民党を追い詰めてきた結果でもあります。
安保3文書と敵基地攻撃(反撃)能力論に基づく大軍拡と沖縄での辺野古新基地建設の強行への反対、反核・反原発、インボイス廃止、マイナ保険証凍結、選択的夫婦別姓と同性婚の実現、ウクライナやガザへの支援、物価値上げを上回る賃上げ要求、最賃1500円以上と時短の実現などの運動が幅広く展開されてきました。
これらの社会・労働運動を通じて、自民党政治に対する不満や怒りが国民各層の間でマグマのように蓄積されたのです。これが裏金事件によって火をつけられ、いっぺんに爆発したのではないでしょうか。「令和の米騒動」の下で生活がこれほど大変な時に、汚い手段で私腹を肥やすとはなにごとかと。
野党の明暗と共産党後退の謎
総選挙で躍進したのは立憲民主党でした。しかし、比例代表ではほとんど票が増えず、7万票・5議席増の横ばいです。逆に、小選挙区では148万票も減らしました。それでも勝てたのは自民党が立憲以上に得票減となったためで、その原因は裏金事件です。これが選挙の大争点になっていなければ、議席増もなかったでしょう。
7議席から28議席へと4倍化を達成して躍進した国民民主党も同様です。自民党を離れた穏健な保守層が。差し当たりの「受け皿」として選択したのが国民民主党でした。自民党に近く、政策的にそれほど違和感がなかったからです。
自民党の敗北と立憲・国民両党の躍進によって政治を大きく動かした主役は共産党でした。政党の機関紙が政権党を追い詰めるようなスクープを、これほど見事に放ったのはかつてなかったことです。新聞報道がこれほどの大きな衝撃を与えて政治を動かす契機になったのも、かつてないことでした。それがなぜ、共産党自体の得票増に結びつかず、議席を減らしてしまったのでしょうか。その功績を強調すればするほど、この謎は深まるばかりです。
一つの仮説は、共産党の攻勢を恐れた自民党と連合の術中に嵌まったのではないかということです。石破首相は自説を覆して「奇襲攻撃」に出ましたが、これは共闘への協議などの余裕を与えず、分断を図るためでした。共産党との共闘を望まない連合も、何とかして排除し孤立させようと待ち構えていました。
連合の意をくむ形で立憲民主党の野田新代表は「平和安保法制の再検証」という発言を行います。これに反発した共産党は共闘に消極的となり、小選挙区で積極的に候補者を擁立しました。これが問題だったように思われます。
2009年の総選挙で、共産党は半数近くの小選挙区で候補を擁立せず、間接的に民主党をアシストしました。2017年の総選挙でも、「希望の党騒動」によって民進党が分裂する下で。小選挙区での候補者を自主的に下ろして新たに発足した立憲民主党を助けました。
今回も選挙区によっては候補者を立てず自主的に立憲民主党を支援しています。しかし、全国的にこのような対応をとったわけではありません。それが支持者や革新的無党派層の失望を招いて離反を生み、れいわ新選組に流れたのではないでしょうか。これは一つの仮説にすぎません。共産党自身による検証が期待されます。
ポピュリズムによる選挙の変容
今回の総選挙で注目されたもう一つの点は、国民民民主党の躍進とともに3議席を獲得した参政党や日本保守党の進出でした。インターネットやSNSを活用しながら一般受けのする政策を打ち出して有権者の関心を引き寄せるポピュリズムの波が、日本にも押し寄せてきたように見えます。
このような現象は、都知事選での「石丸現象」や兵庫県知事選での斎藤元彦知事の再選などでも注目されました。それは三つの面での大きな変化を背景にしているように思われます。第1に選挙の当事者である政党や候補者、第2に投票する主体である有権者、第3に両者を媒介する情報手段や選挙運動のあり方です。その結果、インターネットでの動画配信、ユーチューブやインスタグラムなどのSNSが選挙の「主戦場」になりつつあります。
国民民主党の玉木代表は「永田町のユーチューバー」を自認し。選挙以前からの長い経験や蓄積があったそうです。特に効果的だったのがショート動画で、それを街頭演説などのライブ配信に結びつけました。単にSNSを活用しただけでなく、動画を効果的に使いリアルとバーチャルを結び付けて訴求力を高めたということです。
若ものを中心に有権者も変わってきています。情報を受け取る手段が新聞やテレビなどからインターネットやSNSへと変化した上に多様化し、真偽が定かでないフェイクやデマも氾濫するようになりました。騙されやすい有権者の登場、善意や正義感からの拡散、ゲーム感覚で候補者を〝推す〟活動など、従来とは異なる選挙戦が展開されています。
こうして情報環境が大きく変化しました。ネットのアルゴリズム(情報配信の処理手段)による類似情報の送信によってフィルターバブルやエコチェンバーと言われる状況が生まれ、自分と同一の意見や考え方が多数であるかのような錯覚に陥り、疑似情報の泡に閉じ込められてしまう危険性が増大するわけです。
メディの選挙報道にも問題がありました。公平性や中立性にこだわるあまり選挙の争点についての報道を手控え、公示後にかえって情報量が減ったからです。有権者に判断材料を提供するために、積極的な選挙報道に心がけるべきでしょう。
裏金事件によって急増した自民党への不信は政党全体や政治そのものへの不信感も高め、既存の政治やメディアへの信頼を低下させました。当選を目指さない候補者による公営掲示板の悪用やネットでのアクセスを稼いでビジネスにつなげようとする動きも起きています。従来とは様変わりした選挙にどう対応するのか、政党や候補者の側も、有権者も試されることになるでしょう。
はじめに
驚天動地の結果でした。総選挙で自公が議席を激減させ、衆院での少数与党となったからです。選挙前に石破茂新首相は「与党で過半数維持」という目標を掲げ、「少なすぎるのではないか」と批判されました。しかし、結果は、それをも下回る歴史的大敗です、
石破氏は当初、十分な審議なしの早期解散に反対していました。しかし、自民党の総裁に選出されたとたん前言を翻し、首相に就任する前だったにもかかわらず総選挙の投開票日を口にしました。解散を助言し承認する権限は内閣にあります。首相になる前の表明は憲法違反の暴挙です。しかも、石破氏は天皇の国事行為による7条解散に反対していたではありませんか。
このような変節には理由がありました。新内閣成立への「ご祝儀」としての支持率上昇に期待する自民党内の大勢に抵抗できなかったからです。それに、野党の選挙準備が整わないうちに選挙になだれ込もうという思惑もありました。実際、野党共闘や一本化の動きは低調に終わりました。
しかし、このような奇襲攻撃は功を奏しませんでした。石破新内閣への「ご祝儀」は少なかったからです。かえって石破首相の言行不一致が大きな反発を呼び、裏金事件での国民的な批判という火に油を注ぐ結果となりました。
こうして迎えた総選挙でした。最終盤での自民党非公認候補への「裏公認料」2000万円の交付がまたもや「しんぶん赤旗」に暴露され。敗色濃い候補者に対する決定打となり自民党は歴史的な惨敗に追い込まれました。
それがいかに歴史的なものであったか。衆院での過半数割れは2009年以来、15年ぶりのことです。この結果、特別国会での首相指名選挙は決戦投票になりました。これは30年ぶりのことです。こうして過半数を下回る与党の下での首相が誕生しました。これもなんと大平正芳元首相以来、45年ぶりのことになります。
一、政治的激変を生み出した総選挙
与党の歴史的大敗をもたらしたもの
自民党の歴史的な大敗をもたらした最大の要因は、政治資金パーティーのキックバック(還流)による資金(裏金)の貯め込みでした。それがいつから、誰によって、どのような形で始められたのか、何に使われたのかは、分からずじまいです。中心となった旧安倍派では、安倍元会長の意向でいったんは止めることになったものの復活しました。その経緯も不明です。
この問題を暴露したのは共産党の機関紙「しんぶん赤旗」でした。大きな逆風を吹かせた原動力がこの報道であったことは衆目の一致するところです。こうして「政治とカネ」の問題が直撃し、政治資金規正法を改正せざるを得なくなりましたが、企業・団体献金や政治資金パーティーの禁止という根本原因に手を触れなかったために批判を招き、自民党は総選挙で敗北することになります。
しかし、自民党の大敗を生み出した要因はこれだけではありません。裏金事件は直接の敗因ですが、その根底には安倍政権以来の暴走政治とそれを引き継いだ菅・岸田前政権の4年間に及ぶ失政に対する批判がありました。政治の問題点を明らかにし国民要求の実現を目指した憲法運動をはじめとした多様な社会運動・労働運動の力がボディーブローのような効果を上げ、自民党を追い詰めてきた結果でもあります。
安保3文書と敵基地攻撃(反撃)能力論に基づく大軍拡と沖縄での辺野古新基地建設の強行への反対、反核・反原発、インボイス廃止、マイナ保険証凍結、選択的夫婦別姓と同性婚の実現、ウクライナやガザへの支援、物価値上げを上回る賃上げ要求、最賃1500円以上と時短の実現などの運動が幅広く展開されてきました。
これらの社会・労働運動を通じて、自民党政治に対する不満や怒りが国民各層の間でマグマのように蓄積されたのです。これが裏金事件によって火をつけられ、いっぺんに爆発したのではないでしょうか。「令和の米騒動」の下で生活がこれほど大変な時に、汚い手段で私腹を肥やすとはなにごとかと。
野党の明暗と共産党後退の謎
総選挙で躍進したのは立憲民主党でした。しかし、比例代表ではほとんど票が増えず、7万票・5議席増の横ばいです。逆に、小選挙区では148万票も減らしました。それでも勝てたのは自民党が立憲以上に得票減となったためで、その原因は裏金事件です。これが選挙の大争点になっていなければ、議席増もなかったでしょう。
7議席から28議席へと4倍化を達成して躍進した国民民主党も同様です。自民党を離れた穏健な保守層が。差し当たりの「受け皿」として選択したのが国民民主党でした。自民党に近く、政策的にそれほど違和感がなかったからです。
自民党の敗北と立憲・国民両党の躍進によって政治を大きく動かした主役は共産党でした。政党の機関紙が政権党を追い詰めるようなスクープを、これほど見事に放ったのはかつてなかったことです。新聞報道がこれほどの大きな衝撃を与えて政治を動かす契機になったのも、かつてないことでした。それがなぜ、共産党自体の得票増に結びつかず、議席を減らしてしまったのでしょうか。その功績を強調すればするほど、この謎は深まるばかりです。
一つの仮説は、共産党の攻勢を恐れた自民党と連合の術中に嵌まったのではないかということです。石破首相は自説を覆して「奇襲攻撃」に出ましたが、これは共闘への協議などの余裕を与えず、分断を図るためでした。共産党との共闘を望まない連合も、何とかして排除し孤立させようと待ち構えていました。
連合の意をくむ形で立憲民主党の野田新代表は「平和安保法制の再検証」という発言を行います。これに反発した共産党は共闘に消極的となり、小選挙区で積極的に候補者を擁立しました。これが問題だったように思われます。
2009年の総選挙で、共産党は半数近くの小選挙区で候補を擁立せず、間接的に民主党をアシストしました。2017年の総選挙でも、「希望の党騒動」によって民進党が分裂する下で。小選挙区での候補者を自主的に下ろして新たに発足した立憲民主党を助けました。
今回も選挙区によっては候補者を立てず自主的に立憲民主党を支援しています。しかし、全国的にこのような対応をとったわけではありません。それが支持者や革新的無党派層の失望を招いて離反を生み、れいわ新選組に流れたのではないでしょうか。これは一つの仮説にすぎません。共産党自身による検証が期待されます。
ポピュリズムによる選挙の変容
今回の総選挙で注目されたもう一つの点は、国民民民主党の躍進とともに3議席を獲得した参政党や日本保守党の進出でした。インターネットやSNSを活用しながら一般受けのする政策を打ち出して有権者の関心を引き寄せるポピュリズムの波が、日本にも押し寄せてきたように見えます。
このような現象は、都知事選での「石丸現象」や兵庫県知事選での斎藤元彦知事の再選などでも注目されました。それは三つの面での大きな変化を背景にしているように思われます。第1に選挙の当事者である政党や候補者、第2に投票する主体である有権者、第3に両者を媒介する情報手段や選挙運動のあり方です。その結果、インターネットでの動画配信、ユーチューブやインスタグラムなどのSNSが選挙の「主戦場」になりつつあります。
国民民主党の玉木代表は「永田町のユーチューバー」を自認し。選挙以前からの長い経験や蓄積があったそうです。特に効果的だったのがショート動画で、それを街頭演説などのライブ配信に結びつけました。単にSNSを活用しただけでなく、動画を効果的に使いリアルとバーチャルを結び付けて訴求力を高めたということです。
若ものを中心に有権者も変わってきています。情報を受け取る手段が新聞やテレビなどからインターネットやSNSへと変化した上に多様化し、真偽が定かでないフェイクやデマも氾濫するようになりました。騙されやすい有権者の登場、善意や正義感からの拡散、ゲーム感覚で候補者を〝推す〟活動など、従来とは異なる選挙戦が展開されています。
こうして情報環境が大きく変化しました。ネットのアルゴリズム(情報配信の処理手段)による類似情報の送信によってフィルターバブルやエコチェンバーと言われる状況が生まれ、自分と同一の意見や考え方が多数であるかのような錯覚に陥り、疑似情報の泡に閉じ込められてしまう危険性が増大するわけです。
メディの選挙報道にも問題がありました。公平性や中立性にこだわるあまり選挙の争点についての報道を手控え、公示後にかえって情報量が減ったからです。有権者に判断材料を提供するために、積極的な選挙報道に心がけるべきでしょう。
裏金事件によって急増した自民党への不信は政党全体や政治そのものへの不信感も高め、既存の政治やメディアへの信頼を低下させました。当選を目指さない候補者による公営掲示板の悪用やネットでのアクセスを稼いでビジネスにつなげようとする動きも起きています。従来とは様変わりした選挙にどう対応するのか、政党や候補者の側も、有権者も試されることになるでしょう。
2025-01-06 10:30
nice!(0)
1月5日(日) 『日刊ゲンダイ』に掲載されたコメント [コメント]
〔以下のコメントは『日刊ゲンダイ』1月5日付に掲載されたものです。〕
*巻頭特集:誰もが身構え異常な緊張…大連立か政権交代か、激動政局と国の行く末
確かに、石破政権の部分連合は、各党の要求を丸のみしたサービス合戦となっていく。今年は都議選と参院選があるからなおさらだ。減税バラマキ・ポピュリズムが横行する。
そうならないように、大連立で腰を落ち着けた政治をやるべきではないか、という趣旨は一見、マトモに見えるが、冗談ではない。
「与党第1党と野党第1党が組むなんて、選挙結果を踏みにじるものです。正反対の民意を自分たちの都合でくっつけることに何の正当性もありません。戦争や災害に対する緊急避難以外は許されないことです」(法大名誉教授・五十嵐仁氏=政治学)
これが憲政の常道というものだ。加えて、これが野田元首相周辺から出てきたことにも「危険なにおい」がプンプンする。野田といえば、選挙公約になかった消費税引き上げの「3党合意」を自公と交わし、事実上の大連立を組んだ末、自民党に政権を手渡した戦犯だ。それだけに、いくら口で「対決」を言っても、どこか信用できないところがある。石破とは「熟議を好む」シンパシーもあるからなおさらだ。そこにもってきて、元側近の提言だ。やはり、水面下で、そういう話があるのか。だとしたら、今度も敵に塩を送ることにならないか。米国ベッタリ、軍拡大連立になりはしないか。そんな心配がよぎってくる。
*巻頭特集:誰もが身構え異常な緊張…大連立か政権交代か、激動政局と国の行く末
確かに、石破政権の部分連合は、各党の要求を丸のみしたサービス合戦となっていく。今年は都議選と参院選があるからなおさらだ。減税バラマキ・ポピュリズムが横行する。
そうならないように、大連立で腰を落ち着けた政治をやるべきではないか、という趣旨は一見、マトモに見えるが、冗談ではない。
「与党第1党と野党第1党が組むなんて、選挙結果を踏みにじるものです。正反対の民意を自分たちの都合でくっつけることに何の正当性もありません。戦争や災害に対する緊急避難以外は許されないことです」(法大名誉教授・五十嵐仁氏=政治学)
これが憲政の常道というものだ。加えて、これが野田元首相周辺から出てきたことにも「危険なにおい」がプンプンする。野田といえば、選挙公約になかった消費税引き上げの「3党合意」を自公と交わし、事実上の大連立を組んだ末、自民党に政権を手渡した戦犯だ。それだけに、いくら口で「対決」を言っても、どこか信用できないところがある。石破とは「熟議を好む」シンパシーもあるからなおさらだ。そこにもってきて、元側近の提言だ。やはり、水面下で、そういう話があるのか。だとしたら、今度も敵に塩を送ることにならないか。米国ベッタリ、軍拡大連立になりはしないか。そんな心配がよぎってくる。
2025-01-05 06:28
nice!(0)
1月1日(水) 新年、明けましておめでとうございます [日常]
年の初めにあたり、去年出した年賀状をアップさせていただきます。
謹賀新年
昨年の年賀状に「天下大乱の兆しあり」「今年は選挙の年になりそうです」と書きました。実際、そうなりました。岸田前首相が退陣し、総選挙で与党が過半数を割ったからです。
今年も都議選と参院選があります。それに再び総選挙が実施されるかもしれません。与党を撃破して政権交代を実現する年にしたいものです。
昨年5月に新著『追撃』を刊行し、続編の『撃破』を2月に同じ学習の友社から出す予定です。論攷や談話などは21本、講演などは27回、街頭演説なども16回、『日刊ゲンダイ』でのコメントは91回になりました。言論の力で政治を変えたいと願っています。
老いに抗してメンズカーブスで体力を維持し、野党共闘の再確立で政治を立て直す年にしたいと思います。
2025年元旦
2025-01-01 06:41
nice!(0)