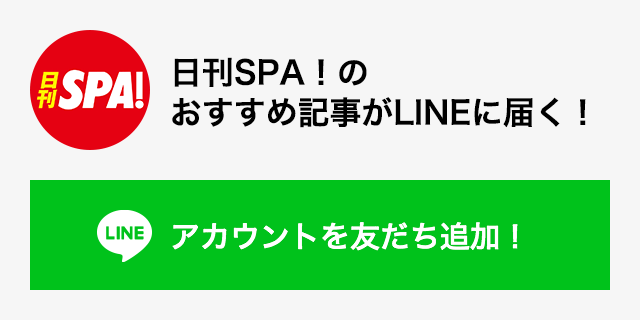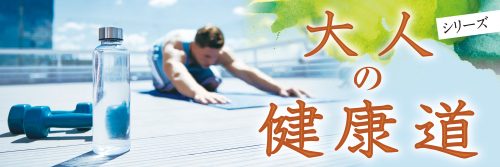選択的夫婦別姓で日本はどう変わるのか?「子どもの約50%が反対」専門家が“杜撰な法案”の危険性と指摘するワケ
選択的夫婦別姓で日本はどう変わるのか?

東京あかつき法律事務所 岩本拓也弁護士(56歳)
「別姓を導入すべき」と考える国民は26%

令和6(2024)年7月7日のJNNの夫婦別姓に関する調査結果 (別姓導入賛成は26%)
1
2
立教大学卒経済学部経営学科卒。「あいである広場」の編集長兼ライターとして、主に介護・障害福祉・医療・少数民族など、社会的マイノリティの当事者・支援者の取材記事を執筆。現在、介護・福祉メディアで連載や集英社オンラインに寄稿している。X(旧ツイッター):@Thepowerofdive1
記事一覧へ
記事一覧へ
【関連キーワードから記事を探す】
この記者は、他にもこんな記事を書いています