前回買った8.4インチタブレットがAlphawolf(Headwolfの別ブランド)のApad1と言う機種。発売と同時に購入したのが昨年の9月のことでした。あれからまだ半年たっていないのに、もう新型くらいならまだしも2世代目の新型というハイペースで8.4インチタブレットを投入しているHeadwolfさんのFpad7という機種をやはり発売と同時に購入いたしました。前世代のFpad6やApad2で導入された高解像度ディスプレイやバッテリーの増量と言った特徴はそのままに、Apad1からはHelioG99のまま据え置かれていたSOCがMediatekのDimensity7050に変更されたのがFpad7です。今回はAlphawolfによる姉妹機Apadは無しということらしいので迷わずFpadを購入しました。まだ届いて4日ほどしかたっていませんが、とりあえず第一陣ということで簡単なレビューなどしておきたいと思います。
わたしにとって8.4インチタブレットに蓋つきケースは必須!ということで本体注文と同時にAmazonで購入しておきました。ちなみに「LINEのお友達登録で純正ケースプレゼント」みたいなこともやっているらしいのですが、Headwolfさんがどうなっているかは知らないのですが、他のメーカーで同様のことをやっていた時に申し込んだら「Amazonで星5レビューを書くのが条件」と言われたのでやめた経験があり、今回も同様のことがあり得なくもないのでパスしました。腐って落ちぶれようともわたしはレビューワーの端くれの自負はあるので、サクラレビューは書きたくないのですよ。
ただ、わたしが注文したものはなぜか品切れとなっており、上記のものはどう見ても同じものですが価格が1000円ほど高くなっております。なんでやねん。あるいは発売前のセット申し込みだったから知らないうちに値引きされていたのかも。
FpadやApadは周囲の構造などが同じであり、制作側としては部品を共通化することでコスト削減を狙える、当然価格も安くなる双方の利点があります。それゆえに旧型の欠点であるイヤホンジャックの位置が悪い、という部分まで受け継いでしまうのですが。で、試しにApad1のケースをはめてみたところ、全くはまりませんでした。外側は両機種とも全く同じなのですが、Fpad7はディスプレイ部分がはみ出ているんじゃないかと表現していいほど厚みがあり、Apad1のものではサイズが合わないのです。本ケースはFpad6用として作られたようで、どうやら先代からこの厚みに変わったようです。おそらく増量されたバッテリーのせいでしょう。ゆえに本体も重くなっており、Apad1が313gだったのに対しFpad7は387gとだいぶ重くなっています。それに加えてケースもFpad7用は重く作られており、Apad1が純正ケース込みで413gだったのにFpad7はケース込みで570g。これは持った瞬間ちょっとズッシリ来る重さです。と、言っても先日やはり買ったスマホ、V MAX PLUSはケース込み577gなのでそれより軽いんですけどね。
このようにケースが重いのは、本体の重みを受け止めるためにある程度丈夫に作る必要があったらでは、と思われます。が、Fpad7でケースの蓋を折り曲げて横置きしようとすると、えらく簡単にひっくり返ります。Apad1のケースが蓋部分だけで三つ折りなのに対し、Fpad7は背面半分まで使った三つ折り型なので重量に耐え切れないのではないかと思われます。立てて使う場合は蓋に頼らず、スタンドを使った方がいいでしょう。この重さを欠点と思う人は少なくないと思いますが、わたしはむしろ武器になると考えています。その理由はのちほど。
電源オォォォンで起動。これは速い! Apad1より圧倒的に速いです。起動すると”7”の文字を使った派手な壁紙が目立ちます。ちなみにApad1は"6"を使ってました。これって世代を表してるのでしょうか? とは言ってもApad1はむしろFpad5に性能は近く、"6"なFpad6と同等なのはApad2の方なんですが。
ぱっと見た感じ、Apad1ほど色が青い!とは感じません。相変わらず寒色系の色合いなのですが、Apad1のようにちょっと不自然なほどの色合いではありません。個人的には暖色系の方が好みなのですが、まぁまぁナチュラルに近い色かな、と思います。
で、使ってみて驚き。コンパス系のソフトが全然使えません。いくつか試したのですが磁場センサーがデバイスにない、って言われて使えませんでした。Apad1の時はやたら指摘されたコンパス。Fpad7ならどうなんだろ、と真っ先に使ってみたのですが。これってウチだけ? ウチの環境だとセンサー切れてる? それとも最初から入ってない? Fpadは磁場センサー使えなくてApadは使えるとかなんでしょうか。Amazonの販売ページを見ると、Apad1やApad2の説明文(検索されやすいように機種の後ろにダラダラ書いてあるやつ)に「方位磁針」の四文字はありますがFpad7やFpad6には無いので、ハナッからないのかも知れません。ただ、GoogleマップではV30TやV MAX PLUSのようなアウトドア向けとは比較にならないものの、Apad1並み程度には方向についてきてくれたので、ひょっとしたらソフトの設定によるのかも知れません。まぁコンパスソフトは最近使おうとするたびに動画系広告が出てきてイラッとさせられるのでこういう時以外は使わないですけどね。
実は今までのと8.4インチタブレットと比べて一番のパワーアップなのでは?と感じたのがWiFi6対応。大容量のソフトやアップデートの速度が段違いです。まして2.4GHzしかつかえなかったT30と比べれば天と地の差があります。そこそこの性能のスマホならもうあって当たり前だったWiFi6ですが、やっとタブレットにも搭載してくれたかと感無量。ようやくタブレットも安いスマホ並みの性能になる時代になってくれたのです。
ディスプレイのレートは60Hz。同じSOCを搭載したV MAX PLUSでは60Hzだとかなりガクついて不快に感じるほどでしたが、Fpad7ではそこまでガクガク感な印象はなく、かなり速く動かしてもちょっと残像が多い程度。正直Dimensity7050は60Hzに不向きなSOCなんじゃないかと考えていたのですが、そこは調整の仕方次第だったようです。ただ、ディスプレイが大きいのでその分60Hz前提のスマホよりちょっと残像が気になるのも確か。そろそろタブレットも90Hz対応を考えてもいいかも・・・。あ、だからと言ってRedmi Pad SE 8.7で使っている8.7インチパネルは絶対使わないでくださいね。あれ、90Hz対応なんですけど解像度低いし、何よりわたしにはデカ過ぎです。先日Redmi Pad SE 8.7の実機に触れられるお店でつかんでみたんですけど、指が突っ張る感じで持っている快適さがありませんでした。ましてケースを付けるとなると・・・。わたしは人並み外れて手が小さく、なにより指が短いので、あの8.7インチは10インチ以上の大型と同じにしか感じられませんでした。もっとベゼルを細くして幅を狭くしてくれればギリギリ使いやすくなるかも知れませんが。なので8インチ級は8.4インチが限界にこだわって作り続けて欲しいです。よって8.8インチのタブも発売中&発売予定のものがありますが、わたしは買いません。
本機はSIMに対応。性能的にライバルと言っていいALLDOCUBEのiPLAY60miniTURBOがSIMに非対応なのでこれはリード。タブレットにわざわざSIMは入れないという人も多いでしょうし、わたしも基本実験の時以外はタブレットにSIMを入れて動作させたりはしません。が、このタブレット業界ではSIMとGPSがセットになっており、SIMが入らない機種はGPS機能も省略される、が絶対の法則になっています。iPLAy60miniTURBOもそうならRedmi Pad SE 8.7のWiFiモデルもそうです。SIMは要らないけどGPSは欲しい、そういう人は必然的にSIM可モデルを選ぶことになるのでこの仕様は歓迎。
povo2.0と楽天モバイルのSIMは差し込んだだけで使えました。ただApad1の環境をコピーして使いだしたので、ひょっとしたらそっちのAPNがコピーされただけ、という可能性はありますが、少なくともAPN設定を行えば使えます。またmineoのシングルauSIMも試しました。これはAPNも入っていなかったので手動設定ですが、しっかり入力すればちゃんと通信できます。通信は4Gまでで5Gは無し。SOC自体は5Gに対応しているのでやろうと思えばできるはずなんですが、価格優先で4Gまでに抑えたんでしょうね。
OSはAndroid14でApad1と同じ。使い勝手もほとんど一緒です。同じメーカー同じAndroidでも機種が違えば多少違う部分もあることが多いのですが、この二機種の違いを見つけることは困難です。今のところわたしが見つけた違いは、スケジュールによる電源ON/OFFがApad1の「午前午後表記」から「24時間表記」に変わったくらいです。Apad1ではなぜか時間を午前に設定しても午後になるという謎現象が起こることがあったので、24時間表記の方が確実で分かりやすくて歓迎です。
Fpad6/Apad2からの引継ぎではありますが本機の特徴の一つが2560x1600の高解像度に対応したこと。タブレットの最低限度必要な解像度は1920x1080と考えているわたしにとって、より高解像度になることは歓迎。低いのは論外です。
で、この数日1920x1200のApad1と2560x1600のFpad7の二機種を比べて意図的に同じ作業をさせてみたんですが、正直に言いますと違いは全く感じませんでした。一般的コンテンツの大半が一辺1080までしかないスマートフォンでの利用を前提としているためか、それくらいまでで収まる程度の解像度で処理しているらしく、Kindleで買えるわたしが所有しているコミック程度では判別できませんでした。ディスプレイの色がナチュラル寄りになったこともあって高解像度の写真やイラストを眺めるなら本領発揮するかも知れませんが、わたしの利用の仕方じゃないもので。
と、ここ数日徹底的(当者比)で使ってきたFpad7。Apad1より明らかによくなっているのが
・色味(個人の好みにもよります)
・電源オフからの起動の速さ
・WiFi6接続によるダウンロードの速さ
・バッテリーの持ち
です。ほぼ同じ程度の残量パーセンテージからほぼ同作業で比べてもFpad7の方が数字の減りが遅いことが確認できています。これは多少Apad1バッテリーが利用によって劣化したのかも知れませんが、それ以上にFpad7のバッテリー容量が多いことが理由でしょう。一方明らかに劣っていると思ったのが
・磁場センサーが使えない
ことです。まぁ使わないといえば使わない機能ですが、あったのがなくなるのはイヤだ、という人はApad3が出るのを待ったほうがいいのかも知れません。
と、いうわけで、仮に両者のどちらを買うか、と問われれば、ほとんどの人は価格が安くて十分サクサク動くApad1の方で十分かな?と思います。色味はフィルターソフトである程度調整効きますし。発売直後と同じ1万円引きクーポン出てますし。
Fpad7が確実に優れていると感じる機会はもちろんありますが限られているので、上級機種を使うという満足感が最大の長所かと思います。
最後にとっておいた「重さ」の課題。一般的には重さは欠点として扱われますが、わたしはむしろ安定につながる武器と考えています。軽くて薄いのが絶対正義、とされるモバイル端末業界ですが、わたしは異なる意見を持っています。
「ある程度の重さは安定につながる。ある程度の大きさは持ちやすさにつながる」
これがわたしの持論です。少々指でつかみにくくても重さとほどよい大きさのおかげで安定して持てる、という状況は誰よりも理解しているつもりです。
なによりこの重さのおかげでApad1最大の欠点である、時折シングルタッチが効かなくなる、わたしいうところの「貼りつき」問題、これが抑えられる可能性があるからです。少なくともわたしの手元のApad1では「接続の接触が甘く、少し緩むと転送される電気信号が弱くなり、エラーを起こす」が理由と考えて間違いなく、再び「貼りつき」が起こるたびに一度電源をスタンバイ状態に戻して表と裏の両方がからグっと位置をずらしながら数回「押し込み」して(ダメならやり直す)起動する必要があります。うまくはまれば数日くらい「貼りつき」の再発を抑えられます。蓋つきケース必須とわたしが考えるのはこの「押し込み」作業の際にディスプレイにかかる圧を分散させるためです。Fpad7の場合、Apad1よりも格段に重い本体とケースの重量によって接続の接触がよくなり、動作の安定性につながるのでは? という期待が持てるのです。少なくともわたしは持っています。
で、今のところ「貼りつき」は起こっていません。まぁたかが四日くらいで結論付けることはできませんけどね。本当に起こらないのかちょっとドキドキしてます。前に使っていたiPLAY50miniPROのように一年近くたって「貼りつき」し始める例もありますので絶対を言うことはできませんが、どこまで持ってくれるのか、それともやっぱり「貼りつき」して単に重いといわれる機種になってしまうのか、これからが注目です。
とは言え、今年に入ってもう二台もAndroid端末買ってる。もう当分買わないぞ! よっっっっっっぽどのものが出ない限りは!!
ぼちぼちNon-KのCoreUltraが出るし、久々にPC組もうかな。久々過ぎてちょっと気力湧かないけど。














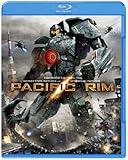
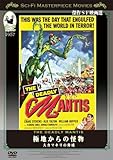





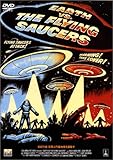











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます