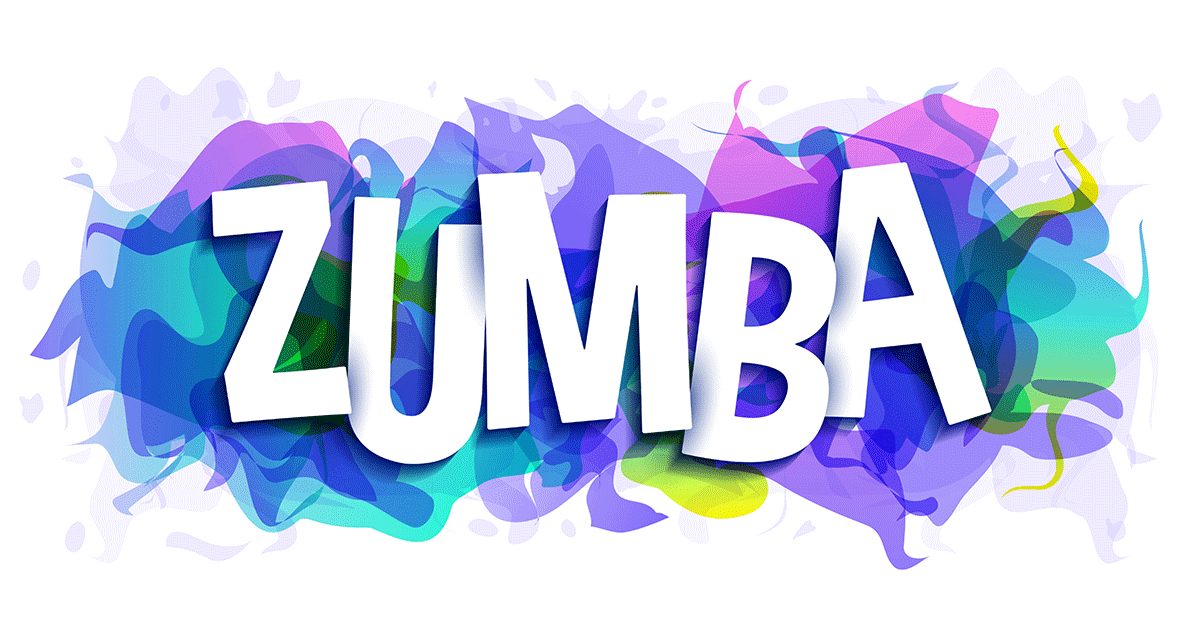- 締切済み
コンデンサの静電容量と端効果
コンデンサの静電容量を求める問題のときによく端効果を無視するをいうのがありますが、端効果がどのように静電容量に影響するのでしょうか?電気力線が端のほうで膨らみを持つということは、端のほうの電束密度が小さくなるということなので、そこの所の電界も強さも小さくなるということですよね、と云うことは同じコンデンサの中でも端のほうは電位差が小さいことを意味していて、それにより静電容量(C=Q/V)に影響が出るということですか?しかし計算上は、金属板間の電界を平等電界と考え静電容量も一定と考えると云うことですか?私の理解で間違ってないでしょうか?あと、もしそうだとすると、実際のコンデンサに蓄えられる電荷は端のほうが少なくなるということでしょうか?基本的なところの理解があまりないので、勘違いが多々あると思いますが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- foobar
- ベストアンサー率44% (1423/3185)
回答No.1